インタビュー連載 ~環境保全のヒトビト~ みんなで一緒に気候変動対策を、一歩前へ。
2022/07/07
第3回は、気候エネルギーグループの田中健さんのインタビュー。
WWFに入局した経緯や、「気候変動イニシアティブ(JCI)」を通じた気候変動対策への取り組みと意義、そこにかける想いについてお話を伺います。
スタッフ紹介

気候・エネルギーグループ非国家アクタープロジェクト担当
田中 健(たなか・けん)
九州大学修士課程修了後、福岡県庁、経済産業省で廃棄物管理やリサイクルなどの環境保全行政に従事、日本のリサイクル企業の海外ビジネス展開を支援。その後、日本科学未来館にて科学コミュニケーターとして、国内外の科学館、企業、研究機関などと連携し、科学技術や研究者と一般市民をつなぐ様々なプロジェクトを担当。2018年8月にWWFジャパン入局。気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative: JCI)等、企業や自治体など非国家アクターの気候変動対策の強化に取り組む。大学時代から海外ドラマを観るのが大好き。気に入ったシリーズは何度も観る。今はまっているのは医療ドラマのグッド・ドクター。
気候変動対策に不可欠な存在、非国家アクターたちをつなぐ
――田中さんのご所属は、気候・エネルギーグループ、つまり地球温暖化問題を担当するセクションですね。まず、取り組まれている具体的なお仕事について、簡単に教えていただけますか?
私のメインの業務は「気候変動イニシアティブ」という、日本の非国家アクターが集うネットワークの運営です。

非国家アクターというのは、政府以外の主体、たとえば企業や自治体、NGOや大学、宗教団体などさまざまな非政府の主体のことです。
気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative略称:JCI)は、こうした非国家アクターが「パリ協定」の掲げる目標達成を目指して集い、参加する「場」であり、気候変動の取り組みを盛り上げ、前に進めるさまざまな活動を展開している組織になります。
具体的な活動には大きく二つの柱があります。一つは、気候変動を取り巻く政策の動向や参加メンバーが取り組む先進的な対策について、国内外でのイベントの実施を通じて、情報提供・発信します。これにより、参加メンバーが気候変動対策のレベルを引き上げる後押しとなることを期待しています。
もう一つは、JCIに参加する約700団体のメンバーの声を一つにして、政府に対して非国家アクターがどのような気候変動対策やエネルギー政策を求めているかを声明として届ける「アドボカシー活動」があります。
――自主的な温室効果ガスの排出削減に取り組むだけでなく、非政府という立場から、国に対してもあるべき政策を求めているわけですね。この非国家アクターが重要な役割を果たすようになったきっかけはどういったものだったのでしょう?
そうですね、2015年に「パリ協定」が成立した頃から、非国家アクターの気候変動対策における役割がすごく重要性を増していて、これからは政府だけでなく色々なアクターが一緒にやっていくことが「パリ協定」の実現には不可欠といわれるようになっていました。
そんななか、2017年にアメリカのトランプ大統領(当時)がパリ協定からの離脱を宣言しました。それを受けて、すぐさまアメリカの企業や自治体、学術機関などの非国家アクターが「We Are Still In」というネットワークを立ち上げ、政府がいなくともパリ協定の目標達成を目指して行動すると宣言したのです。
これは「たとえ大統領が離脱しても、我々はパリ協定にとどまる(We Are Still In)」という強い意思表示であり、非国家アクターの力と存在感を世界に示すものでした。
そこにインスピレーションをうけ、日本でも非国家アクターのプラットフォームを作ろうと、2018年にWWFを含む数団体が共同で「気候変動イニシアティブ(JCI)」を立ち上げたのです。
環境や人の役にたつ仕事がしたい
――非国家アクターによる連携は、まさにこの数年で大きなうねりを見せている、最先端の温暖化対策の動きですね。そんなJCIに出会うまでの田中さんは、どのようなキャリアを積まれてWWFジャパンに入局されたのですか?
最初は福岡県の化学を専門とする技術職員として、県内の環境を守る仕事をしていました。大学で化学を専攻していたので、「人にも環境にも役立つ仕事で、化学の知識も生かせる!」と考えたのが、この仕事を選んだ理由です。
そのなかで経産省に2年間出向する機会があり、地域を出て国全体を見る仕事に携わることができました。
そこでは、リサイクルビジネスを実践する日本企業の海外事業展開を支援する仕事を担当していたので、必然的に海外の環境問題を知ることになったのです。
視野が福岡県内から全国、そして海外まで広がり、「まだまだできることがあるかも」と考え始めました。そこで、出向期間を終えると同時に一念発起して自治体の仕事を辞め、日本科学未来館で「科学コミュニケーター」として働きはじめました。
そこで学んだのが「科学コミュニケーション」です。日進月歩で進むさまざまな科学技術や研究を一般の方にわかりやすく伝え、それらを私たちはどう使いたいのか、また持続可能な社会を実現する科学技術とはどうあるべきかを考えてもらい、研究者にフィードバックする仕事でした。いわば、研究者と一般市民の橋渡し役です。その仕事で、いろいろな業種の方と関わる経験ができたことも、今のJCIでの活動に繋がっていると思います。

日本科学未来館がアジア太平洋10の国と地域の科学館と連携し、2015年から2017年にかけて実施した映像制作ワークショップ「Picture Happiness onEarth」の成果発表イベントの様子。
そこでさらに視野も広がり、科学コミュニケーターの任期が終わるタイミングで、WWFジャパンのスタッフ募集を知ったのです。
「多様なセクターの方を束ねてつなぎ合わせ、日本の気候変動対策を盛り上げていく」というJCIの取り組みと、それを仕事とするWWFスタッフの応募要項をみて「これまでの経験を全部活かせるかもしれない!」と、ピンときて応募しました。
――環境や科学といったキーワード、それから「人にも環境にも役立つ仕事!」という点は共通しているものの、職種としてはさまざまな内容を経験されてきたのですね。結果として、公務員から違う道を行くと決めた決断は間違いじゃなかった、と。
よく聞かれる質問ですが、後悔はしていないですね。
自治体を辞める決断をするまでは、科学コミュニケーターが任期制だったこともあり、その次の仕事が見つからなかったらどうしよう?とすごく悩んで、悩み過ぎて熱が出たくらいでしたが(笑)。でもやっぱりこのまま福岡に戻ったら絶対後悔すると思ったので、最後は不安を振り切って決めました。
今は、気候変動対策に変化と動きが出ている過渡期で、世界や社会のシステムも大きく変わろうとしています。
そのうねりに、自分がWWFのスタッフとして関われていることはすごくやりがいを感じるし、面白いし、ハッピーなことだと思いますね。前の職種ではできなかったことに携われている実感があります。

2019年に開催された気候変動アクションサミットにてモデレーターとして登壇
多様な非国家アクターが声をあげる社会に向けて
――大きく動き、非常に注目されている活動でもあるわけですが、田中さんとして、これまでJCIの活動に携わるなかで、印象的だったことはありますか?
2021年4月に、JCIに参加する企業や自治体などのメンバーが共同で声明を提出する活動を行ないました。
日本政府に対し、日本の温室効果ガス排出削減目標を少なくとも45%以上にすること、また電力における再生可能エネルギーの導入目標を40~50%にすることを求める声明です。
これに291のメンバーが名前を連ねて声をあげてくれたのは、成果としてとても印象に残っています。
この声明に答えるかのように、その後「日本の温室効果ガスの排出削減目標を46%に引き上げ、さらに50%の高みを目指す」と発表されました。少なくともJCIの声は政府に届いていると実感しています。
――参加している非国家アクターのメンバーの方々が声をあげてもいい、政府にしっかりとモノを言ってもいいと気づいて、その影響力を発揮できるようになったという点は大事ですね。
はい、企業や自治体などのメンバーには、JCIに参加することで、政府に対して働きかけるアドボカシー活動の意義や、その具体的な手順について知っていただく機会を提供できているのではないかと思っています。
また、このようなアドボカシー活動を行なうことに対するハードルも少しずつ下がってきているのではないかと感じています。
特に日本では、個々の企業や自治体が国の掲げる政策に対して公に声をあげる文化はないので、JCIの活動がそういう文化が浸透していくひとつのきっかけになればいいなと思っていますね。
——JCIのような非国家アクターの集まりがあげる主張や声が、世の中を変えていくだけの力をもっているのですね。
はい、企業や自治体など社会のあらゆる主体が自らの認識や行動を変える、必要な声を上げる、それが社会の変容に繋がっていきます。それを後押しするJCIの活動は、気候変動対策を推進し脱炭素社会を実現する上で、今後ますます重要な役割を果たせる可能性を持っていると思います。

2021年10月に行われた気候変動サミット2021の様子
変化しながら進化するために
――一方で、今の取り組みの中で課題だと感じている部分はありますか?JCIの活動は順調に拡大しているように感じますが、今後にむけた展望の中で、気にしなくてはならない点などはあるのでしょうか。
2018年の立ち上げ当初、JCIには105の企業や団体が参加していました。
そこから急激に参加数が伸び、4年目の2022年には約700団体が加盟しています。
そうなると、やはり活動にも年々新しい進化が求められるようになる。
加えて今、気候変動対策は国内外の動きが速いので、その時流にあわせて動いていかないといけません。
変化をキープしつつ進化すること。そのためには、常に一歩先をみて新しいことを考えていく必要があります。
――なるほど、国際的にも地球温暖化対策が進む中では、企業などの非国家アクターに求められる取り組みも、当然変わってくるわけですね。より野心的で、効果が期待できる温室効果ガスの排出削減への取り組みが必要になってくる。そういう中で今後、田中さんとして、目指している将来像や具体的な目標はありますか?
JCIには現在約700団体が加盟していますが、その中でも企業や自治体などのメンバーが、より主体的にリーダーシップを発揮して活動に参加できる仕組みが作れるとよいと思っています。
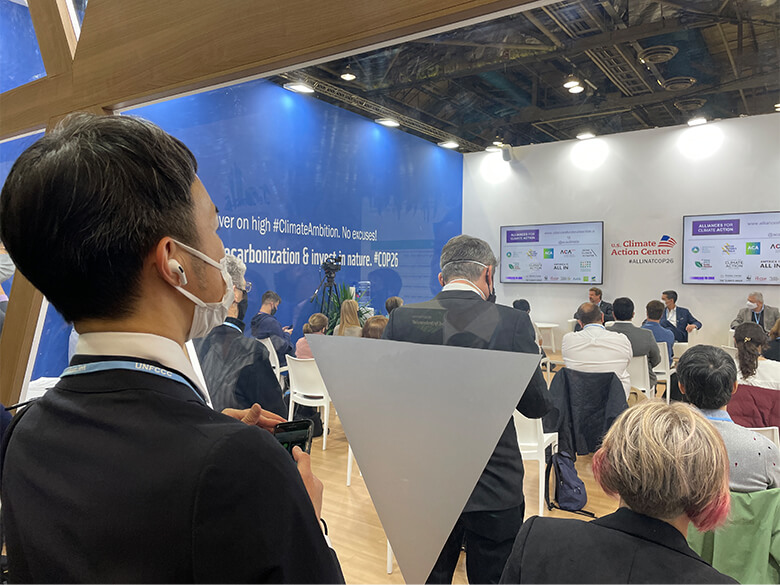
2021年に開催されたCOP26での非国家アクターのイベントの様子。ブースが満席のため担当者なのに中に入れず、イベントの前半はガラス越しにイベントを見ながら、音声はオンライン配信で聞きました。
アメリカの団体「We Are Still In」では、すでに先行してこれを実施していて、より主体的にリーダーシップをとるメンバーで構成される「リーダーズサークル」と呼ばれるグループが置かれています。サークルのメンバーは各セクターを代表する発信役となり、より顔の見える活動ができる仕組みです。また、バイデン政権のもとアメリカのパリ協定復帰後には、「We Are Still In」は「America Is All In」へと進化しました。日本でも、JCIメンバーの主張を引っ張っていけるような、そうしたリーダーを生み出し、進化していきたい。
また、長期的には、JCIに求められる役割も時代と共に変わっていくと考えられます。
例えば、「2030年温室効果ガスの排出量半減、2050年排出量ゼロ」という大目標を達成する目途がつくと、次の目標や必要なアクションが新たにでてくる。
JCIもこれまでの知見や活動の手段を活かしつつ、新たな目標にむけて進化していかなければなりません。
そのためには、さまざまな選択肢があると思います。どの選択が最適か見極めるために常に情報を収集し、時代の波についていかなければならないと思っています。

あらゆるアクターをつなぎ、ともに気候変動対策を前進させる「場づくり」
――最後に、田中さんの活動に対する想いをきかせてください。
JCIの活動を4年間やるなかで、加速する世の中の変化とあわせて、JCIの活動も進化して変わっていかないといけないと感じています。
実際、もう変化は見えています。例えば、現在、WWFジャパンのウェブサイトで自治体の先進的な脱炭素施策事例を発信する担当もしているのですが、そのリサーチを通じて、自治体のカーボンニュートラルに向けた目標の引き上げや対策の具体化などが、ますます加速していることを感じています。
JCIの活動だけでなく、企業や自治体など非国家アクター自身の動きもまた加速する今、この状況を上手に後押しする活動を絶えず生み出していくこと。それがWWFの役割だと考えています。
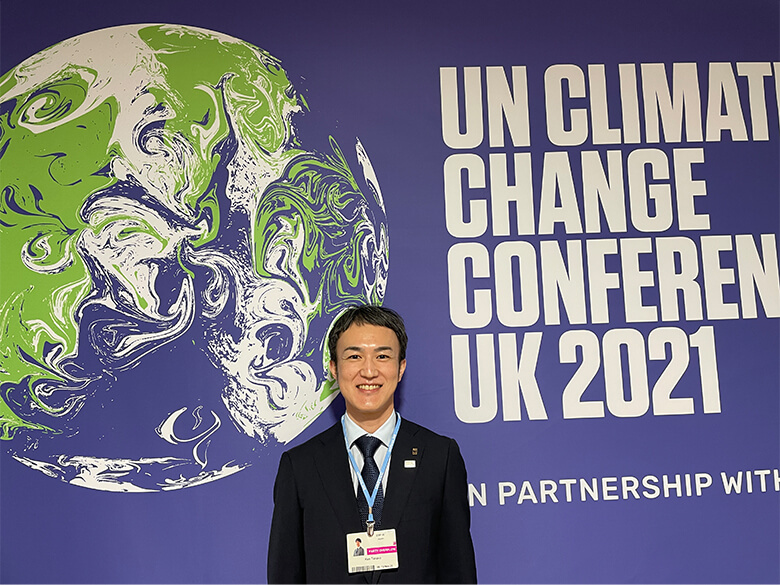
2021年にイギリス・グラスゴーで開催されたCOP26に参加したときの様子
ですからJCIの活動も、スクラムを組んで「みなさん、一緒に前に進めていきましょう!」という気持ちで取り組んでいます。
かくいう私も「これで大丈夫かな?」「これで皆さんがちゃんと参加してくれるのかな?」と試行錯誤しながらこれまでの活動をやってきましたし、これからもそうやっていくと思います。
それは、企業や自治体をはじめ、ありとあらゆる枠を超えて多種多様なアクターが結集し、気候変動対策のために行動を起こせるこの「場づくり」こそが、これからの気候変動対策を加速させるカギであり、未来の脱炭素社会を実現するタネになると考えているからです。
――地球温暖化の脅威のない未来を担うのは、まさにこうした、あらゆる枠を超えた人のつながりという訳ですね!そのつながりがもっと大きく、強くなっていくように、これからの取り組みに期待しています。
WWFで働いてみませんか?
スタッフ一同、強い気持ちと、実力と、高い志をお持ちの皆さんと共に、ご一緒に働けることを願っています。






















