- 標準和名
- ヒラメ
- 標準的な大きさ
- 80cm
「左ヒラメに右カレイ」と言われるように、左図のように目が上側、口が下側になるよう横向きに並べたとき、左を向くのがヒラメ、右を向くのがカレイですが、例外もあります。生まれてすぐは、他の魚と同じように左右対称ですが、やがて片方の目が反対側へ移動し、良く見る姿へと変わります。また海底の状況に合わせて体の色や模様を変えることができるため、砂や泥に紛れて身を隠し餌を待ち伏せするのにとても適しています。互いに姿かたちは似ていますが、餌や生態は異なり、味や食感が違います。
天然
養殖






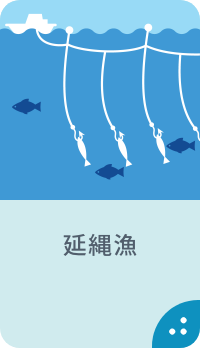
適切な資源管理と環境配慮が重要
一方、オヒョウやカラスガレイなどの輸入魚は、管理が強化され資源が回復しつつありますが、漁業による環境影響が懸念されるなどまだ予断を許さない状況です。