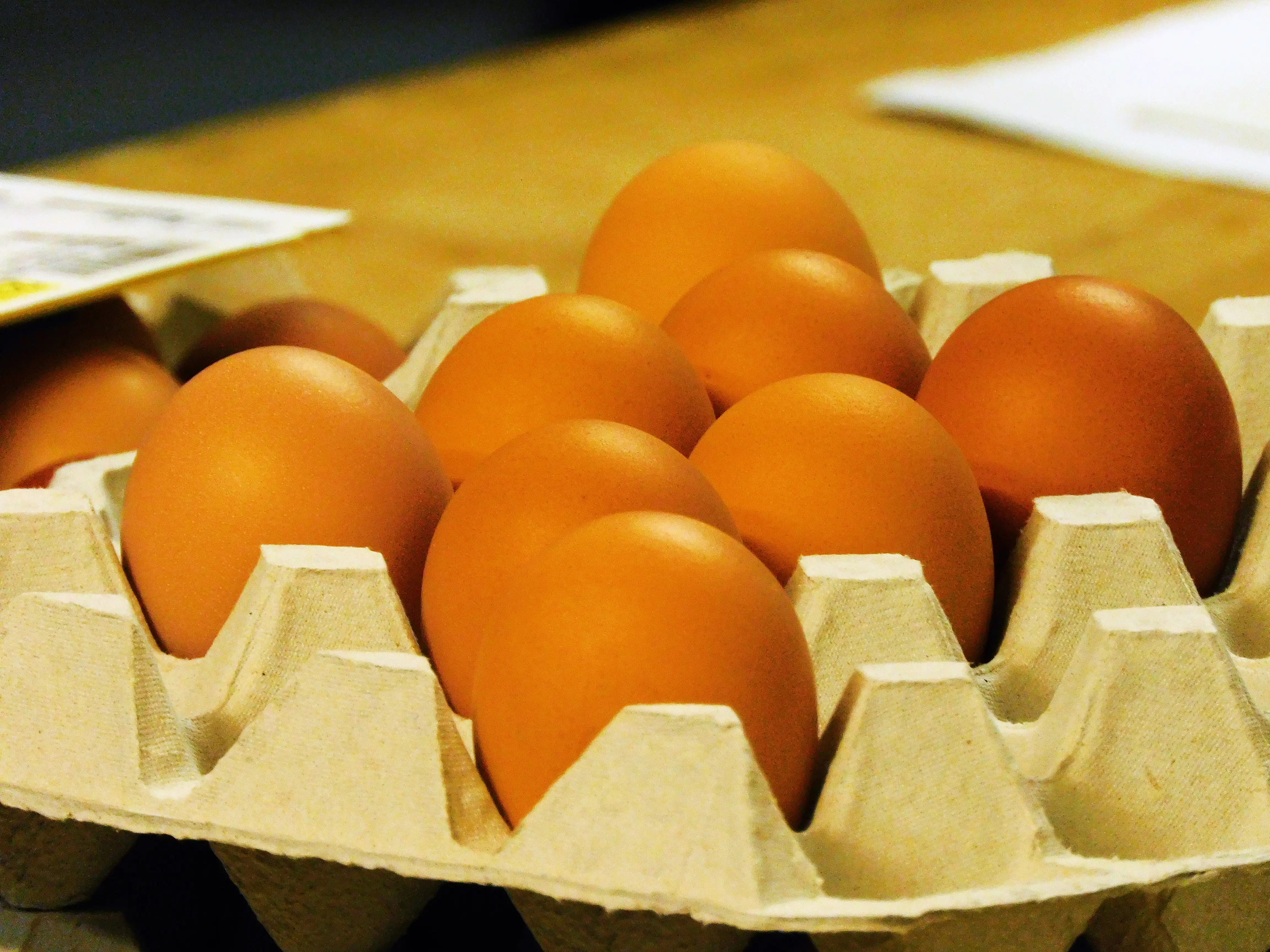トラの森から夏の日本へ
2019/05/28
大きさはスズメくらいでしょうか。
双眼鏡で捉えたのは、さして目立った模様もない、地味な、でも黒い大きな目が印象的な、一羽の小鳥でした。
おそらくは、コサメビタキと思われるこの鳥。
日本では毎年、夏の山地の森に渡ってきて巣をつくり、鳴きかわす声を聞かせてくれる、なじみの深い「夏鳥」です。
しかしこの時、私がこの鳥を見たのは2月の初旬。
場所も、日本ではなく、東南アジアはタイの森でした。


タイのクイブリ国立公園で2月初めに見たコサメビタキと思われる鳥。まだ少し若い個体かもしれません。他にも、東南アジアで越冬し、初夏に日本へ渡ってくる鳥は少なくありません。
日本ではまだまだ冬の寒さが厳しい時期でしたが、タイは気温が30度前後という暑さで、他にも、熱帯ならではの、たくさんの鳥を見ることができました。
その中で出会った、このコサメビタキ、そしてツバメのような鳥たちは、いずれも、春になると、越冬地である東南アジアを旅立ち、はるかアジアの北部へとやってくる渡り鳥です。

タイのクイブリ国立公園。WWFタイが長年、野生生物保護のためのパトロールなどを推進してきた重要なフィールドの一つです。
トラもいればゾウもいる。
そんなインドシナ半島、メコンの森から日本の山林へ。
毎年、13センチほどの小さな身体で、数千キロの旅路をはるばる飛んでくる命の持つ力に、あらためて気づかされるとともに、何ともいえない畏敬の念を感じた一瞬でした。
渡り鳥にとって、冬を過ごす越冬地は、巣をつくる夏の繁殖地の自然と同じように、大切な生息環境です。
日本の森も、インドシナの森も、共に守らなければ、このコサメビタキのような渡り鳥たちの未来を守ることもできません。

クイブリ国立公園の北に位置する、ケーン・クラチャン国立公園でのトラの調査。この取り組みには、日本からの支援も役立てられています。


天然ゴム(右)と、パーム油を採るためのアブラヤシ(左)の農園。東南アジアでは、この2つの作物の農園の拡大が、自然の森を脅かす大きな要因になっている。
東南アジアと日本の自然が、渡り鳥の結ぶ、一つの自然であることを忘れないようにしながら、現地のWWFの仲間たちとも一緒に、インドシナの森とそこに生きる野生生物の保全を目指してゆきたいと思います。