地域に寄り添う治水対策をめざして
2021/09/21
今年の夏も、各地で豪雨災害が発生してしまいました。被害を受けられた方々に心からお見舞い申し上げるとともに、一日でも早く日常を取り戻されることを願うばかりです。
8月の豪雨で、特に多くの浸水被害が出た福岡県と佐賀県は、WWFジャパンが「水田の生物多様性と農業の共生プロジェクト」を行なっている場所でもあります。

九州北西部の水田地帯は、豊かな淡水生態系が残る貴重な場所でもある
活動にご協力いただいている農業者の方々に安否をおたずねしたところ、1階の胸の高さまで浸水した地域もあることがわかりました。田んぼが水に浸かったという地域はさらに広く、その時に稲がどのくらいまで成長していたかによって、収穫が難しくなってしまうおそれもあるそうです。
手塩にかけて育ててきた作物が全滅するかもしれないというあまりにも厳しい状況に、言葉を失ってしまいます。

黄金色に実る稲穂。今年も無事に実りの秋を迎えられるよう願うばかりです(写真は2018年撮影)
ここ数年、九州では毎年のように、豪雨被害が出続けています。WWFとしても何かできることはないかと考え、2020年11月、九州大学および長崎大学の協力を得て、水田地帯における防災・減災と、生物多様性保全の両立をめざす共同研究を開始しました。
地球温暖化の影響も指摘される中、水害の発生がこれからも続く可能性は、残念ながら否定できません。だからこそ、地域に寄り添った、より多角的な水害対策が、これからますます必要になってくるのではないかと思っています。

九州大学との共同研究では、伝統的な石積みが川の勢いを抑える効果を持つことなどが明らかに
WWFが共同研究を行なっている九州大学流域システム工学研究室では、「河川というフィールドに主軸を置き、社会問題を解決するための実践的な科学研究をとおして、人々や自然の生きものを幸せにし、より明るく豊かな社会と未来を築き上げる」ことをめざしています。
降り続く雨を止めるすべはありませんし、水害の発生をゼロにできるような特効薬もありません。それでも、ひとつひとつ、実践的な知見を積み上げていくことによって、人の暮らしの安全を守り、なおかつ、地域の歴史や景観、生物の多様性を守っていく一助となれたら…と願っています。
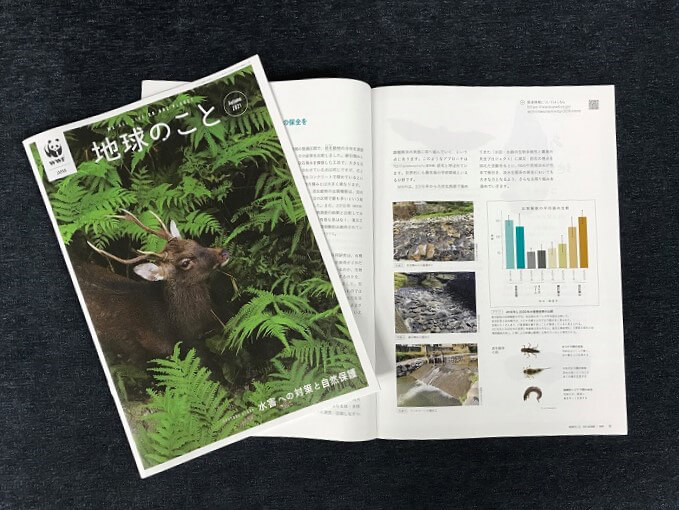
九州大学との共同研究については、WWF会報 『地球のこと』2021年秋号で特集しています。会員の皆さまには、9月15日前後にお届けしています。ぜひご覧ください



























