シリーズ:気候危機の解決に向けて、私にできることは?「家でも外でも、食べ残しをしない工夫を」編
2020/09/23
都道府県を選択すると、その地域に起こりうる今世紀末の気候危機を見ることができる「未来47景」キャンペーン。大切な地元にも温暖化の影響が及びうることを知って、食い止めるための行動を呼びかけるとともに、特設サイトでは、個人にできる12のアクションをご紹介しています。
でも、「気候変動ってとっつきにくい、実感がない」「個人の行動で何が変わるの?」と感じている人も多いはず。そこでこのシリーズでは、12の選択肢からピックアップしたアクションについて、WWFインターン歴1か月の大学生・エナさんが、気候変動・エネルギーグループの専門家に聞いた行動のヒントをご紹介します!
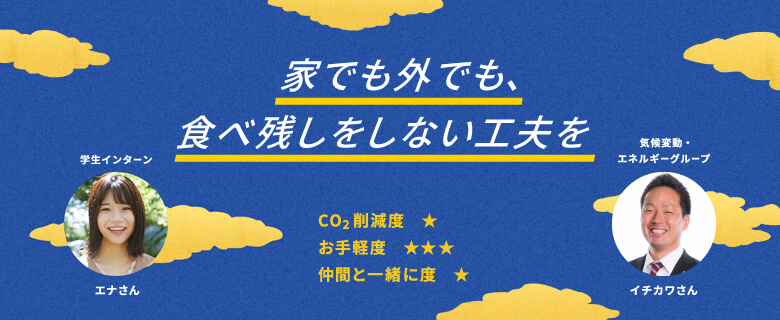
エナ:イチカワさん、今日もよろしくお願いします!さっそくですが、食べ残しが気候危機につながっている・・んですね?
イチカワ:食品ロスとCO2排出の関係がピンとこない方もいるかもしれませんね。

食料の生産から廃棄の過程で排出される温室効果ガスは、世界の排出量全体の約2~4割ともいわれています*1。そして、世界で生産される食料の約3割が、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられています*2。一方では、世界人口の1割強が飢えに苦しんでいることを考えると、とても不均衡な状態です*3。
エナ:驚きの数字です・・!
イチカワ:また、世界で進む森林破壊の約8割が、農業に由来します*4。野生生物のすみかを奪うことにもなりますし、木はCO2を吸収し固定してくれていますから、森が伐採されれば、温暖化も進んでしまいますね。

さらに、食料を廃棄すれば、その食料を作ったり、輸送するために使われたエネルギーも捨てることになり、ムダなCO2が排出されていたことになってしまいます。
エナ:「もったいない」という言葉に重みを感じます。日本の食品ロスのうち、家庭からの廃棄はどのくらいなんでしょうか?
イチカワ:食品ロス全体に占める家庭からの廃棄は45%、約半分を占めます*5。私たちの生活に工夫の余地がありそうですね!エナさんだったら、どんな工夫をしますか?
エナ:まず、かしこく買いものをすることでしょうか。冷蔵庫の中身を把握して、必要なものを、必要な量だけ。レストランでも食べきれる量を意識して、時には「少なめ」をリクエストしたり、カフェでは使い捨て容器ではなくマイカップやマグカップをお願いしたりします。
イチカワ:できることがいろいろありますね。買いものでいえば、加工食品の製造には多くの資源が使われるので、生鮮品を買うこともポイントです。また、輸送には多くのエネルギーを必要とするため、地元産で露地栽培の野菜を選ぶなどの心がけも、スマートショッピングに有効です*6。
エナ:レジ袋有料化で、エコバッグを持参する人が増えました。
イチカワ:加えて、パッケージが過剰な商品を避ける、野菜や果物など包装されていないものが選べる場合は選ぶ、量り売りを利用するといったことで、さらに使い捨てプラスチックの利用を減らしていきましょう。日本は1人当たりの容器包装プラスチックごみの発生量が世界第2位*7です。

エナ:全然嬉しくない第2位ですね(悲)
イチカワ:また、一見、日本では廃棄されるプラスチックの有効利用率が84%と、進んでいるとされていますが、全体の58%は、「サーマルリサイクル」という方法に頼っています*7。この方法は、リサイクルとはいっても、廃プラスチックを燃やすことで、CO2を排出しているので、やはり、まずは使い捨てプラスチックの利用を「減らす」ことが大切です。
エナ:「リサイクル」というだけでは安心できないんですね…。冒頭の、世界の1割の人が飢えに苦しんでいるというのも、考えさせられます。
イチカワ:そうですね。食事もままならない人々が大勢いるなか、誰の口にも入らず廃棄された食品のCO2のせいで、そうした貧しい人達に気候変動の影響がおよぶという矛盾はやるせないですね。

エナ:食品ロスをめぐるさまざまな課題の一端を知ることができました。
イチカワ:「心がけよう」という気持ちが大きな意味を持ちます。消費者庁が、食品ロス削減に大切だと思うことは何か調査したところ、「もったいないの意識づけ」が1位に挙がったそうですよ*8。
エナ:今日からさっそく心がけたいです!
「未来47景」キャンペーンサイトでは、みなさんの意思表明をお待ちしています。地元の未来の気候危機を知ったあとは、取り組みたいアクションを選んで「実行する」ボタンのクリックをお願いいたします!

次回は「国会や地元の議員、選挙の候補者に、SNSで温暖化政策を尋ねてみる」編。公開するとSNSでお知らせしますので、WWF公式Twitter/Facebookをフォローしてくださいね!
シリーズ一覧
*1 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SRCCL-Chapter-5.pdf
*2 https://www.saveonethird.org/energy-emissions
*3 https://www.wwf.or.jp/staffblog/news/4142.html *4 http://www.fao.org/news/story/en/item/1103556/icode/
*5 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/4.html
*6 https://www.wwf.or.jp/activities/data/20191025_wildlife01.pdf
*7 https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html
*8 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/pdf/pamphlet_181029_0005.pdf

























