シリーズ:気候危機の解決に向けて、私にできることは?「地域の自治体に『2050年CO2排出ゼロ宣言』の宣言予定や具体的な対策を聞く」編
2020/10/14
都道府県を選択すると、その地域に起こりうる今世紀末の気候危機を見ることができる「未来47景」キャンペーン。大切な地元にも温暖化の影響が及びうることを知って、食い止めるための行動を呼びかけるとともに、特設サイトでは、個人にできる12のアクションをご紹介しています。
でも、「気候変動ってとっつきにくい、実感がない」「個人の行動で何が変わるの?」と感じている人も多いはず。そこでこのシリーズでは、12の選択肢からピックアップしたアクションについて、WWFインターン歴2か月の大学生・エナさんが、気候変動・エネルギーグループの専門家に聞いた行動のヒントをご紹介します!
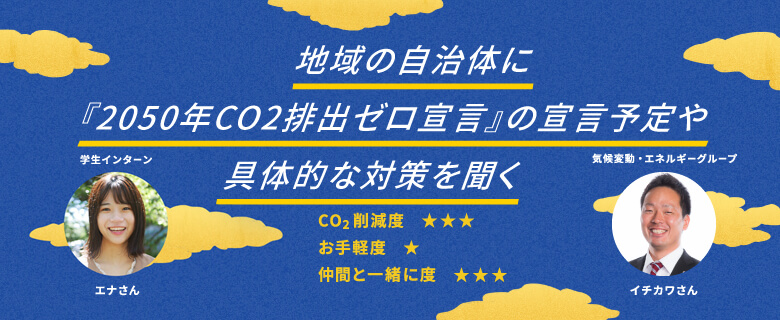
エナ:イチカワさん、今日も難易度高めですが、よろしくお願いします!さっそくですが、そもそも今日のお題である、自治体の「2050年CO2排出ゼロ宣言」がなんのことかわかりません・・・!

イチカワ:まず、国際社会では、気候変動の影響を抑制する目安として、産業革命以降の温度上昇を2℃ないし1.5℃未満にすることが目標となっています。この1.5℃未満を達成するため、2050年までにCO2排出ゼロを達成することが、社会的通念となりつつあることは、前回お話ししましたね。
エナ:はい、覚えています!
イチカワ:それを受けて、世界各地の国や地域、さらには多くの企業で、2050年までに自身の排出ゼロを宣言する流れができつつあります。日本でも、2020年10月1日現在、157の自治体が宣言をしています。
「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明している自治体の一覧(画像をクリックすると環境省のサイトに遷移します)出典:環境省ウェブサイト https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
宣言した自治体に住む人の数は、日本の総人口の半数以上を超えていますので、ご自身の出身地や居住地の自治体があるか、見てみてくださいね。なければ、自治体の担当課に問い合わせ、宣言を促してみましょう。まず、地元の自治体について知ることが、このアクションの第一歩です。
エナ::157も!こんなに多くの自治体が前向きに取り組もうとしているなんて。希望を感じます。ただ・・「2050年CO2排出ゼロ」って、ものすごいことをさらっと言っていませんか!?実際のところ、可能なんでしょうか?
イチカワ:わずかあと30年しかありませんので、野心的な目標ではありますが、決して夢物語ではありません。日本は、排出削減の鍵となる再生可能エネルギー資源に恵まれています。WWFジャパンが試算した報告書では、国内の再エネ資源を活用することで、2050年までに脱炭素を実現できることも分かっています。

WWFジャパンが2017年2月に発表した「脱炭素社会に向けた長期シナリオ」。省エネと、段階的な再エネへの切り替えによって、CO2排出ゼロが可能であることを示しています。
エナ:日本の豊かな自然を活かして達成できるなら、素晴らしいですね!自治体による具体的なCO2削減の取り組みは、例えばどのようなものがあるんでしょうか?
イチカワ:自治体がおもに担う役割は、自治体内の企業や家庭が排出削減できるような具体策を設けることです。
排出削減の要は、無駄なエネルギーを削減して、CO2排出の少ないエネルギーに置き換えること。そのため、省エネ機器や再生可能エネルギーの導入への助成や補助がよく行なわれます。

進んだ自治体では、排出量を規制するルールを定めたり、近年では、自治体自身が再生可能エネルギーを扱う会社(新電力)を立ち上げたりすることもあります。
宣言をした自治体が表明している主要な取り組みは、こちらから見ることができます(環境省のサイトへ遷移します)。
エナ:とくに積極的に取り組んでいる自治体はあるんでしょうか?
イチカワ:東京都や埼玉県、京都市、横浜市や富山市など多数あります。例えば東京都は、排出量取引制度を採り入れ、2000年比で、すでにエネルギー消費量を24%減少させることに成功しています*1。

また富山市では、路面電車(LRT)を整備することで、まばらに広がるコミュニティを、近郊に集約化して、コンパクトで車に過度に依存しないクリーンな街づくりに取り組んだり、水が豊かな地勢を活かして、小水力などの再生可能エネルギーの導入を積極的に進めています*2。
エナ:なるほど!となると、住まいの自治体に対して具体的な対策を促し、市民の声を推進力につなげることが、このアクションのポイントですね!どのように自治体に働きかけをしたらいいんでしょうか?
イチカワ:自治体の担当課にメールや電話で、具体的な気候変動対策を聞いたり、意見を送ってみましょう。自身が住んでいる地域ですから、家族や知人を介して、一緒に取り組める仲間を広げやすいのではないでしょうか。近年顕著に関心が高い、熱中症対策や防災と結びつけると、共感してくれる人が増えやすいと思います。

また、自治体で政策を決める際には、役所のウェブサイトで“パブリックコメント(パブコメ)”と呼ばれる、市民からの意見を吸い上げるプロセスがあります。その際には、地元のNPOや市民団体が、パブコメへの意見を公表し署名を集めていることもありますので、そこに署名賛同することもできますし、それを参考に自身でパブコメを出してみるのもよいですね。
エナ:ふだん、生活の中で自治体の取り組みを実感する機会があまりないのですが、対策が進んで実感できたら素敵だなと思います。イチカワさん、ありがとうございました!
「未来47景」キャンペーンサイトでは、みなさんの意思表明をお待ちしています。地元の未来の気候危機を知ったあとは、取り組みたいアクションを選んで「実行する」ボタンのクリックをお願いいたします!

WWF公式
Twitter/Facebookをフォローしてくださいね!
シリーズ一覧
*1 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/zenpan/emissions_tokyo.files/2018sokuhou.pdf
*2 https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/9930/1/dai2ji_kankyoumiraitoshikeikaku_gaiyou.pdf


























