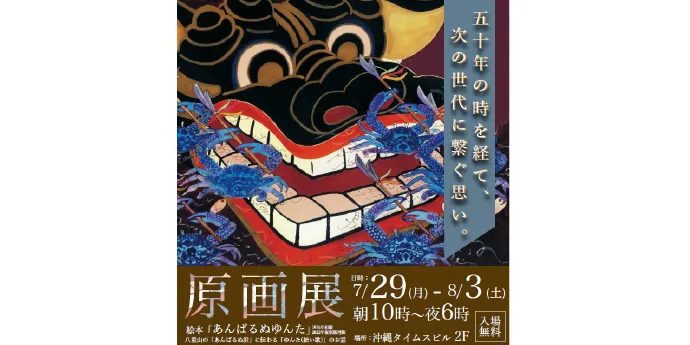(参加受付中)淡水魚の鑑賞と保全を考える日本魚類学会シンポジウム
2023/05/18
初夏の日差しが降り注いだ5月の休日、関東平野の谷津へホトケドジョウの顔を拝みに行ってきました。久しぶりにその鷹揚な「仏顔」を見て、癒されパワーをもらいました。

ホトケドジョウ。絶滅危惧IB類(環境省)
『増補改訂版 日本の淡水魚』(細谷和海 編・監修、山と渓谷社)によれば、日本産の淡水魚の種数は約500種超。その「日本の風土に適応し独自の進化を遂げた」多様性は、日本の水辺の自然の豊かさを表しています。
一方で、ホトケドジョウを含め、日本の淡水魚は、かつては普通に見られた種も次々と絶滅危惧種に指定され、国内でもっとも絶滅の危機にさらされている生物相の一つとなっています。開発による生息地の消失や外来種の影響に加え、鑑賞魚としてインターネット等で行われている営利目的の取引は、この生物多様性に対する直接的な脅威となっています。

種の保存法に基づく特定第二種国内希少野生動物種に指定されているカワバタモロコ。手前の個体がオスで、向こう側の個体がメス。特定第二種国内希少野生動植物種については、販売目的の捕獲等が法律で禁止されている。

カワバタモロコの絵 ©nature works
違法・過剰な流通・取引から野生の種をまもりながら、自然体験や環境教育の一環として生物との触れ合いも大切にすること。日本の生物多様性を保全する上で非常に重要なこのテーマについて、6月3日、日本魚類学会が市民向けシンポジウムを開催します。
※シンポジウムの情報
日本魚類学会 市民公開講座
「観賞魚としての日本産淡水魚の流通・飼育の現状と課題」
詳細・参加申込については、下記よりご確認ください:
https://www.fish-isj.jp/event/sympo.html
シンポジウムには、日頃よりWWFジャパンの活動に貴重なご指導・ご協力を頂いている魚類学の研究者の方々も登壇されます。
私も早速申し込みました。日本産の淡水魚が置かれている厳しい状況や、野生生物と人との関わりについて、学び、考える機会にしたいと思います。
ご関心のある方は、ぜひ上記の日本魚類学会ホームページをご覧頂き、ご参加頂ければと思います。
(野生生物グループ 小田倫子)