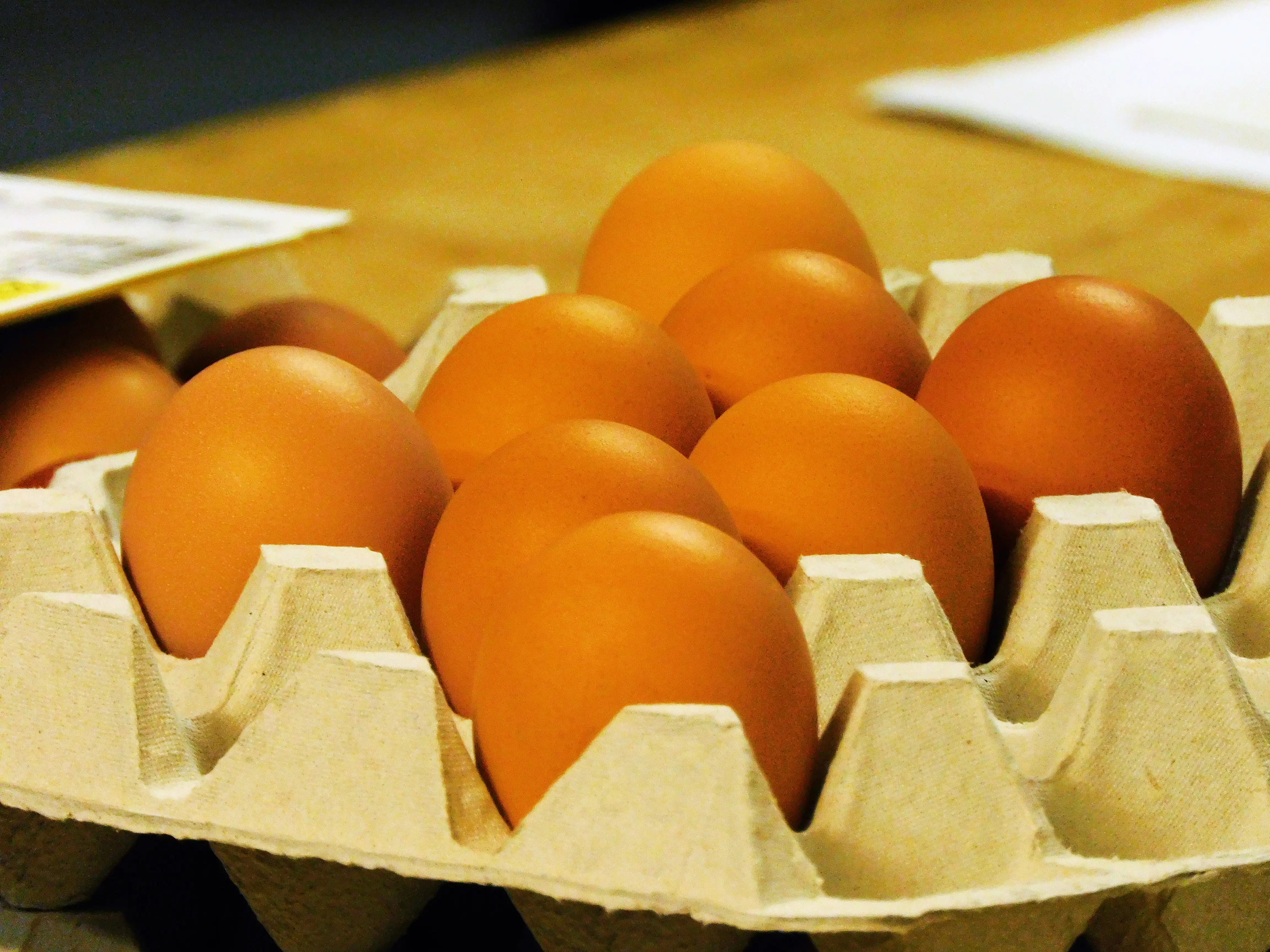かささぎの渡せる橋におく霜の… 七夕によせて
2022/07/07
「かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞ更けにける」
百人一首に収録されているこの有名な歌。
「霜」とあるので冬の歌かと思いきや、これは本日7月7日の七夕の歌だそうです。
七夕の日は年に一度、織姫と彦星が天の川を渡って会うとされる日。
その折、川を渡る橋をかけるのが、「かささぎ」という鳥です。
これはカラスの一種で、白と黒の身体に、光沢のある羽を持つきれいな鳥で、日本では北九州一帯にのみ分布しています。
もっともこの鳥は、文禄・慶長の役の折に朝鮮半島から大名が日本に持ち帰ったとか、渡ってきた個体が定着したなどといわれ、昔から日本にいたわけではなかった模様。
上の和歌を詠んだ大伴家持などは奈良時代の方なので、本物の鳥の姿は見たことが無かったに違いありません。
ともあれ東京などで暮らしていると、カササギはなかなか姿を見ることができないため、九州の水田プロジェクトのフィールドに出向いた折に目にしたりすると、非常にテンションが上がります。
ですが先日、別の場所で、久方ぶりにこの鳥を見た時はビックリさせられました。
場所は、ユキヒョウの保護プロジェクトの現場であるインドはラダック州、西ヒマラヤの標高4,000mの高地。

西ヒマラヤで出会ったカササギたち。谷を吹き上げる風に乗って遊んでいました。
やはりカラスというべきか、人のすむ集落の周りをすみかとしているようでしたが、それでもこんな場所でお目にかかれるとは!
日本では平地でくらす鳥の、意外かつ逞しい一面を見ることができました。
そんなカササギたちが活躍する、本日7月7日の七夕の日。
願わくば今宵の雲が晴れ、天の川に橋がかかりますように。

西ヒマラヤのプロジェクト現場。この標高4,000mの高地にユキヒョウやヒグマ、ウリアルなどが生息しています。画面中ほどの緑のある場所が人の集落。奥の雪をいただく山嶺は、7,000mを超えます。