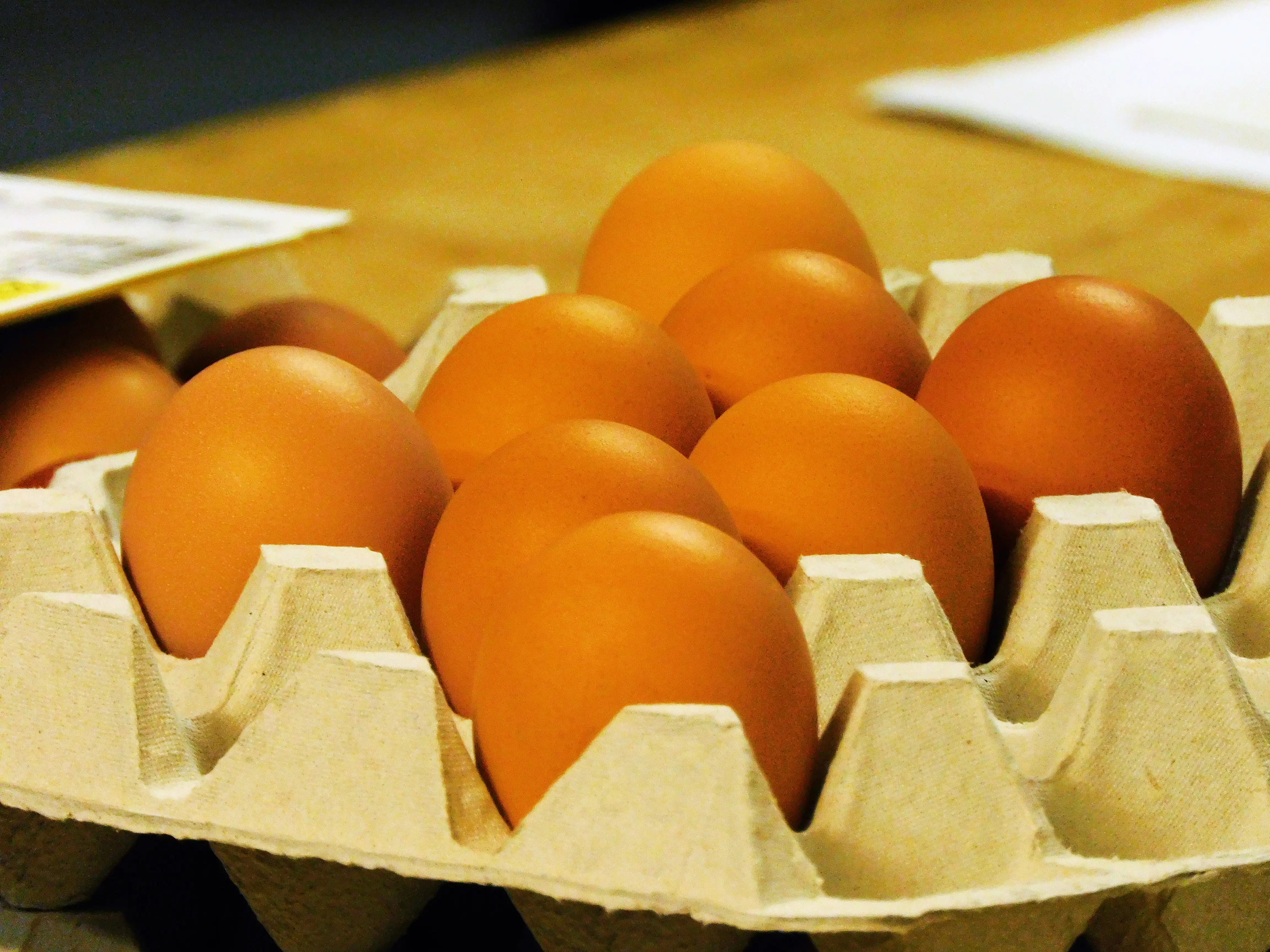減災・防災の観点から求められる生物多様性
2023/07/07
先日、損害保険料率算出機構が、全国一律だった保険加入者向け水害補償の保険料の料率を、地域の災害発生のリスクの高さに応じて5段階に変更する、という報道がありました。
これは簡単にいえば、洪水などの起こりやすい、水害のリスクの高い地域ほど、支払う保険料が高くなる、ということです。
最近の気候変動(地球温暖化)による異常気象は、日本をはじめ世界の各地で、多くの被害をもたらしていますが、その影響が、普段の暮らしにも直接的にかかわっていることを、あらためて実感させる報道でした。
水害は、予測の難しい災害です。
ここはそれほど雨も降っていないし大丈夫、と思っていても、川の上流で大雨が降ったりすれば、やはり災害に見舞われることになります。
川の流れがつなぐ「流域」という視点で考えなければ、そのリスクを正しく理解し、対応することは難しいのです。
逆に、この流域という観点でリスクを低減させることも可能です。
たとえば、上流域で水を蓄えてくれる豊かな森を守ったり、中流で水田や湿地などを一時的に遊水池(あふれた水を逃がす場所)として活用することで、流域全体を水害から守ることができます。
最近、NbS(Nature based Solutions:自然に根ざした解決策)という考え方が、防災の観点からも全国的に注目されていますが、これはまさに、こうした自然の力を、防災や減災の助けにしよう、という試みです。

今も現役で活躍する九州の伝統的な石造りの堰。石畳の段差には水の流速を落とす効果があります。その地域の歴史や文化の中で取り組まれてきた減災や防災には、現代のNbSが学ぶべき、多くの知恵が秘められています。
堤防やダムによる水の管理は、確かに有効な手段の一つではありますが、現代の水害は、もはやそれだけでは防ぐことが難しくなっています。
流域の自然と共に、人自身の暮らしを守っていく。そうしたこれからの環境保全の取り組みを、しっかり進めていかねばと思います。
アメリカのニューヨーク市では、流域全体のコミュニティで水源を守る取り組みを行なっています。大都市ニューヨークで使われる水の約90%は、同州北部のキャッツキル山地が水源。市では、このキャッツキル山地の自然保護を通じた水源と流域の保全に、大きな投資を行なっています。