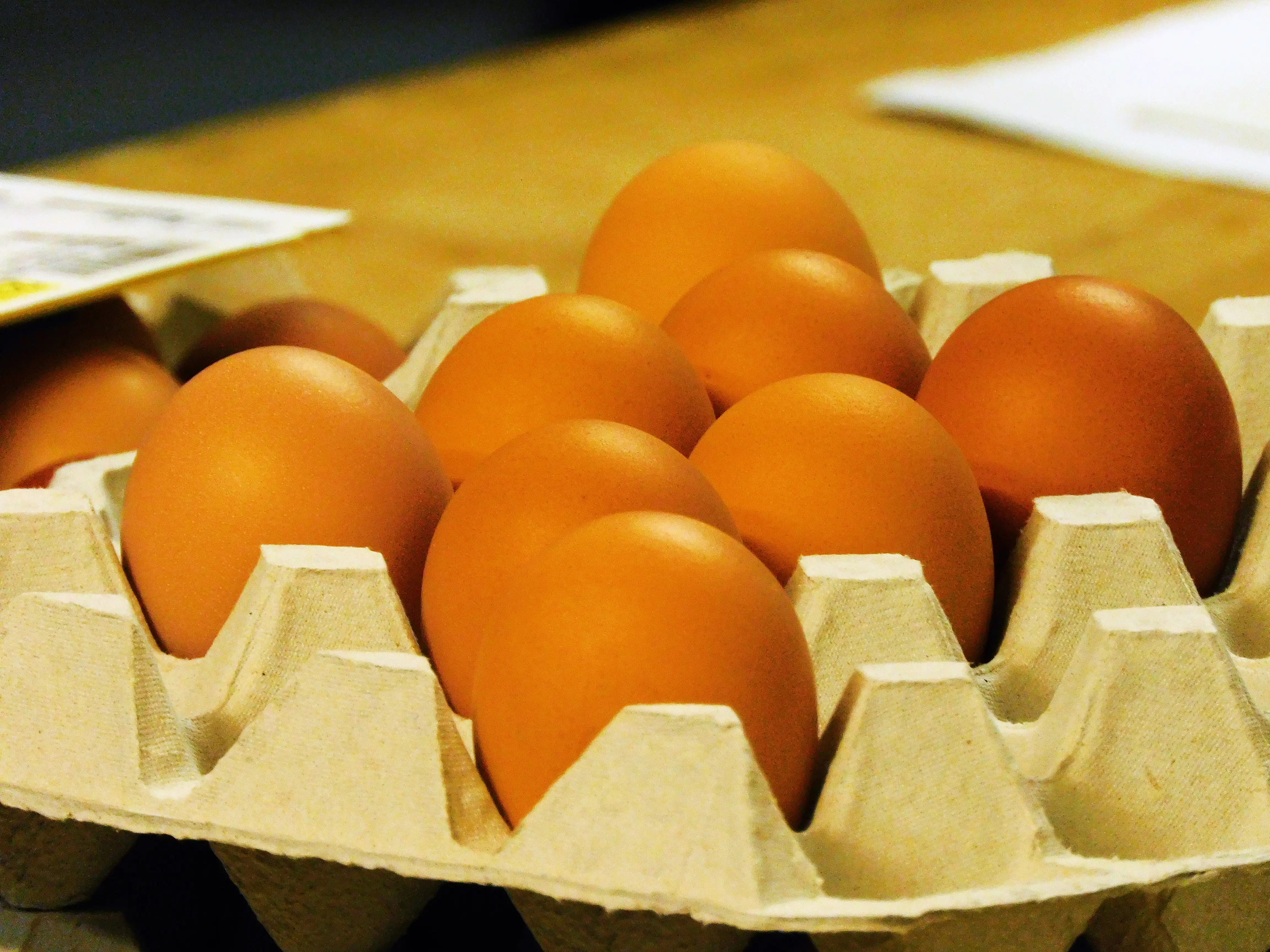サギとウシは仲がよい?
2019/10/24
穏やかな日差しの下、のんびりと草を食むウシと、その周りにたたずむサギたち。
なんとも心の和む、よい風景です。
この写真を撮影したのは、私たちが現在WWFタイの仲間たちと共に、絶滅寸前のインドシナトラの調査・保全に取り組んでいる、タイのケーンクラチャン国立公園。

タイ最大の自然保護区ケーンクラチャン国立公園。この山並みの向こうはミャンマーです。
隣国ミャンマーとの国境に位置するこの山岳地帯の国立公園は、自動車で20分も走れば、深い森の世界になりますが、公園入口にある管理棟やロッジの周りでは、このように家畜のウシがお食事をしている姿が見られます。
このウシとサギが一緒にいることには、実は理由があります。
ウシが草を食べながら移動すると、隠れていた虫やトカゲなどの小動物が驚いて飛び出す。サギたちはそれを食べてやろうと、ウシの周りをついて歩き回る、というわけです。

ウシの周りにいるのはアマサギ。英名はCattle Eagletで、文字通り「ウシのサギ」です。
こんな景色は、実は日本の田んぼでも見られます。
今ではさすがに田んぼを耕すのにウシは使いませんから、トラクターなどにお役は変わっています。が、サギがこのトラクターの後ろや周りをついて歩くのは全く同じ理由。
時には数種のサギが、何羽も群がっていることもあります。
実際、田んぼや、その周辺をめぐる水路は、小さな生きものたちの宝庫。
鳥が集まってくることにも、確かな理由があるのです。

WWFジャパンの保全フィールドがある九州の水田にて。イネの根元にアマガエルがいました。他にも数種のカエルが見られます。
今、世界的にも貴重な自然の一つである日本の水田が、その豊かさを失いつつあります。
そうした環境に生きる、メダカのような身近だった野生生物たちも、少なからず絶滅危惧種となってしまいました。
未来にのこしたい景観、自然の一つとして、私たちは現在、日本の水田環境を保全するプロジェクトを推進しています
支援キャンペーンも行なっていますので、ぜひご協力をお願いいたします。