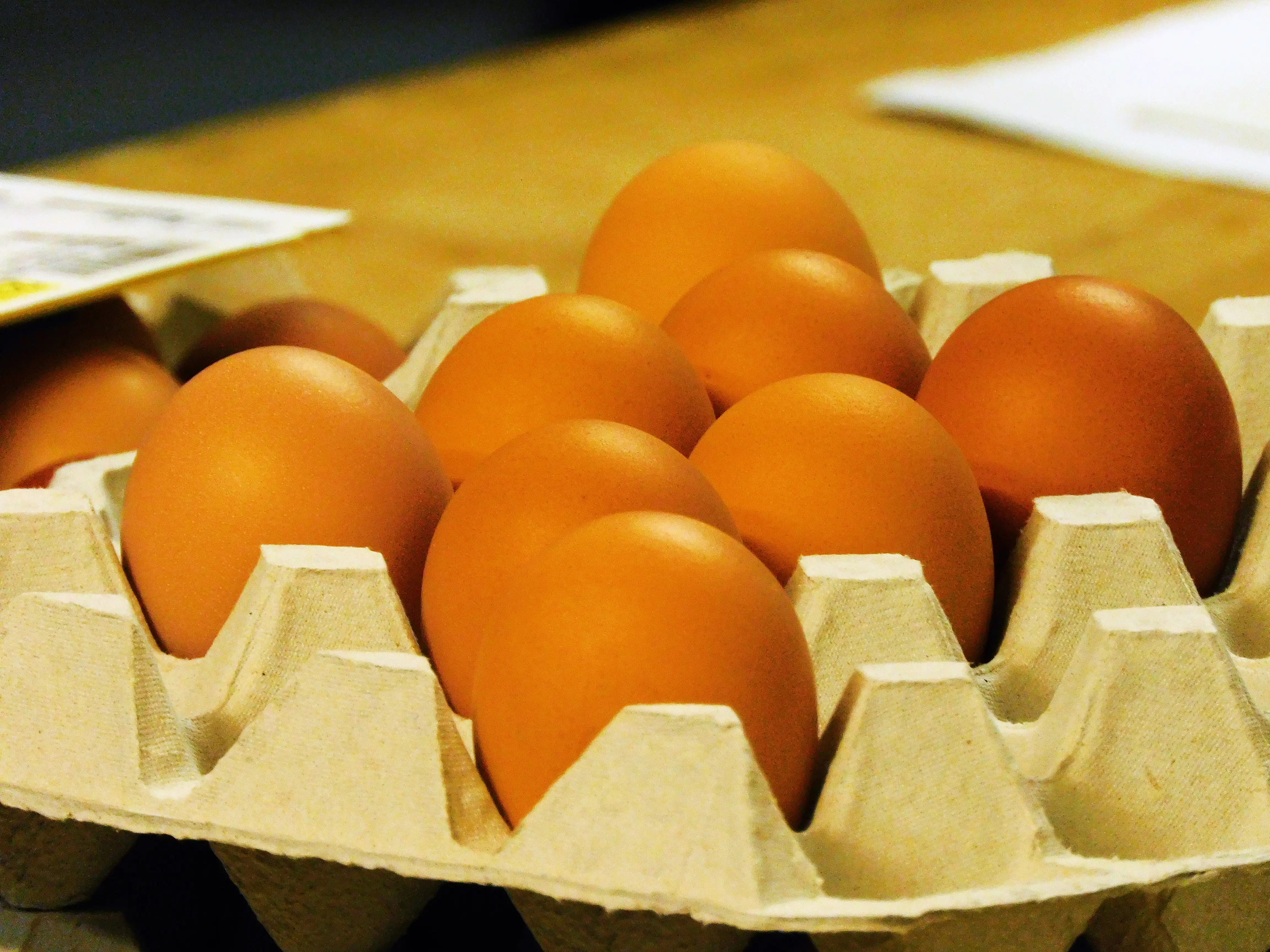ユキヒョウのすむ標高4,000mの山でトカゲに遭遇!
2023/08/14
「世界の屋根」といわれるヒマラヤ山脈。
ここで私たちが展開している、ユキヒョウの保全プロジェクトの現場、西ヒマラヤはラダック地方のフィールドを訪れた時、驚くべき動物に出会いました。
トカゲです。

遭遇したヒマラヤアガマ(Paralaudakia himalayana)と思われるトカゲ。同行していたWWFインドのスタッフいわく、こうした高地にも数種のトカゲが生息しているそうです。ちなみに、同じ爬虫類でも、ヘビはいないとのことでした。
もちろん、本命の野生のユキヒョウにでも出会っていれば、もっと驚いたに違いありません。
ですが、このトカゲを目にしたのは、富士山の山頂よりも高い、標高4,000m近い高地。
氷雪に覆われる冬場はもとより、私たちがここを訪れた夏でも、明け方は息が白くなるほど寒くなる場所です。
そんな場所で変温動物、つまり太陽の熱が無ければ体温が得られない爬虫類の一種であるトカゲに出会えようとは!
予想もしていなかった分、この驚きは本当に大きなものでした。
ですが、あらためて周りを見てみて、なるほど、と納得しました。
トカゲがいた場所の周辺には、多少の差はあれ、必ず植物が生えています。
そして、そこにはバッタをはじめ、トカゲの獲物となるであろう、さまざまな虫たちがたくさん集まっていました。

トカゲのいた場所の周辺で見られたバッタと植物。チョウやハチも見られました。
また、散在する大小の岩々も、日中の陽が高い時間帯は、しっかりと温かくなっています。
きっと冬眠の期間は長く、寒さへの耐性もある程度は必要なのでしょうが、厳しくともトカゲが生きられるぎりぎりの条件はそろっているようでした。
しかし、こうした自然環境のバランスが、気候変動によって少しでも変わってしまったら?
ヒマラヤの厳しい環境に適応してきた、限られた野生の生きものたちは、たちまち絶滅の縁に追いやられることになります。
ユキヒョウ然り、トカゲたち然り。
この地ならではの自然と生きもののつながりを守っていくために、これからも日本からの支援を続けていきたいと思います。

トカゲのいた岩の上にあったユキヒョウのフン(手前)。奥に見える山々の標高は6,000mを超えます。