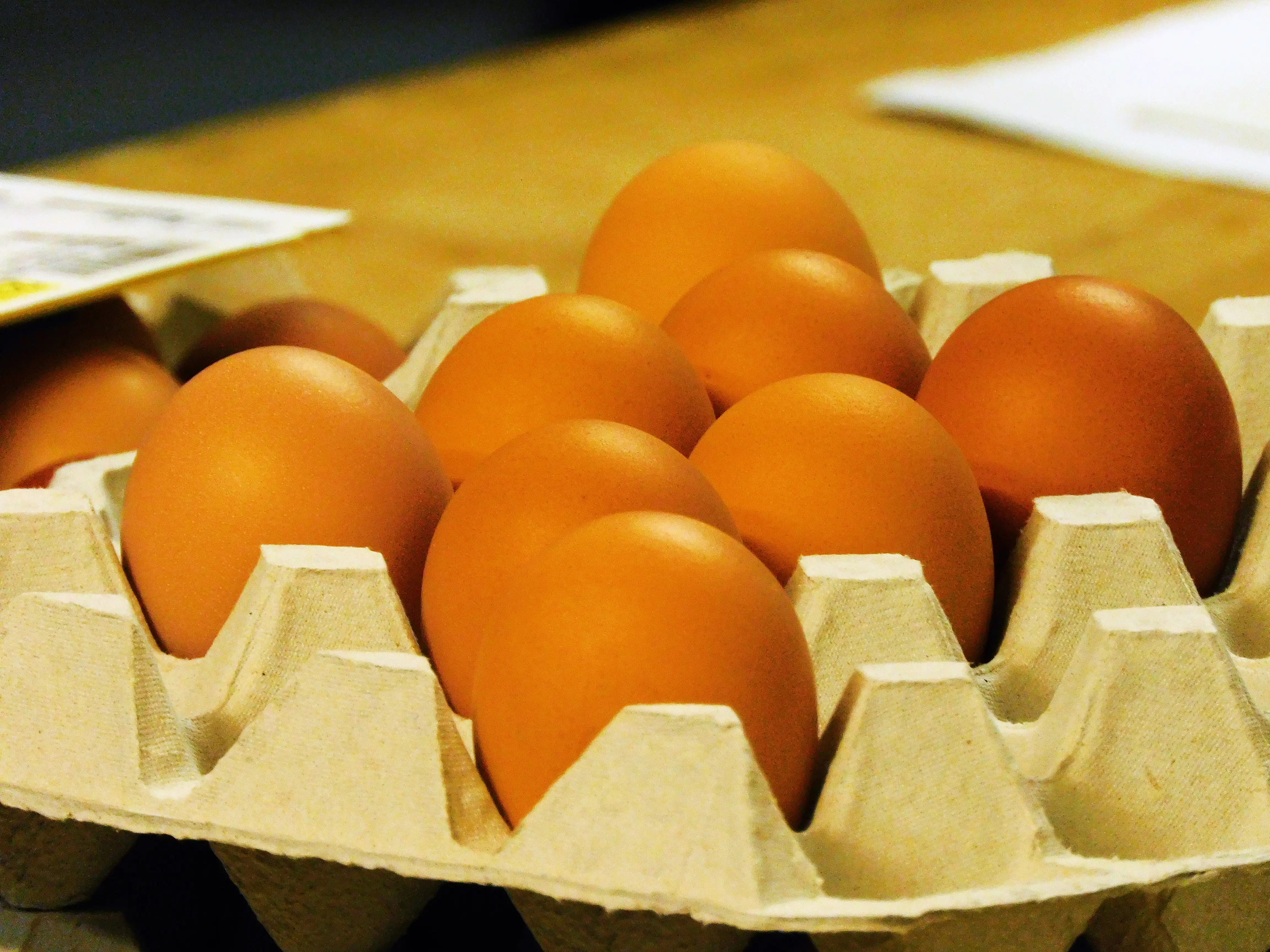10月23日は「世界ユキヒョウの日」です
2023/10/23
10月23日は、絶滅のおそれのあるユキヒョウの保全を考える「世界ユキヒョウの日」です。2013年10月23日に、キルギスのビシュケクで「世界ユキヒョウ保護フォーラム」が開催されたことを受け制定されました。
中央アジアとヒマラヤの標高3,000~6,000mの高地を中心に生息するユキヒョウは、いまだに多くの謎に包まれている野生動物です。
現状で調査が行われているのは、ユキヒョウの全生息域の23%未満。しかも、科学的に十分な信頼のおける個体数調査が行われている地域は、3%未満にすぎません。

しかし、そうした状況の中で、私たちWWFは各国の政府や地域社会と協力しながら、調査と人とユキヒョウの共存に向けた取り組みを行なってきました。
この夏には、ブータンでの調査により、同国内のユキヒョウの個体数が39.5%回復傾向にあることが明らかになったほか、中国やパキスタンでも、新たにAIなどを活用したユキヒョウによる家畜被害への取り組みが行なわれています。
またネパールでも、山間部の伝統的なコミュニティに残るユキヒョウについての知見を調査・記録し、地域との協力のもと、国立公園の統合的な保全管理戦略を策定。カメラトラップを用いた調査で、90頭を記録しました。

私たちWWFジャパンも、WWFインドによる西ヒマラヤでの野生動物の調査・保全活動を支援し、ユキヒョウと人が共存できる未来を目指した活動に取り組んでいます。
気候変動や放牧地の拡大、家畜を襲う害獣としての報復など、ユキヒョウを取り巻く危機は今も尽きることがありません。
10月23日の「世界ユキヒョウの日」に、その保全の輪を広げていくため、ぜひこれらの問題にご関心をお持ちいただき、SNS等での発信にご協力をいただきますよう、お願いいたします。