レッドリストに見る「成果」と「課題」
2018/11/16
広報の大倉です。
11月14日、IUCN(国際自然保護連合)は、「レッドリスト」(絶滅のおそれのある世界の野生生物のリスト)を更新しました。
目立つのは、マウンテンゴリラの危機の度合いが改善したことです。「CR(近絶滅種)」から「EN(絶滅危惧種)」へと1段階危機のランクが下がりました。
絶滅の危機の3段階のうち上から2番目のため、決して保護の手をゆるめることはできませんが、前向きな気持ちになる話題です。

マウンテンゴリラの親子
今年5月、密猟パトロールの強化と違法なわなの撤去に努めた結果、マウンテンゴリラが1,000頭を超える水準に回復していることが明らかになりました。レッドリストはそれを反映しています。

ゴリラよりも小さな動物をねらうわなだが、ゴリラもかかってしまうため撤去。ヴィルンガ国立公園(コンゴ民主共和国)にて。
このように、保護活動の成果が現れ、危機のランクが改善する例が見られるようになってきたのが、最近のレッドリストの特徴です。ジャイアントパンダも2年前に危機のランクが1段階下がりました。

ジャイアントパンダ
かつては生息環境の悪化に歯止めがかからず、ひたすら危機のランクを上げる例が多かったのですが、徐々に改善に向かう事例が出てきています。
ただ、今回の発表では、絶滅のおそれのある生き物は合計26,840種となり、前回より643種増えて過去最多を記録。全体としては、危機が進行していることに変わりはありません。
たとえば、アフリカ、マラウィ湖の調査した458種の魚のうち9%が絶滅の危機にあると判断されるなど、人間の影響は依然として大きなものがあります。
これは過剰漁獲によるものですが、一方で、マラウィの人々の3分の1が食を同湖に依存しているなど、問題解決には多くの課題を抱えています。

マラウィ湖畔の風景
成果を励みとしつつも、困難な課題に向き合い、自然保護活動にいっそう力を注いでいかなくてはと思います。
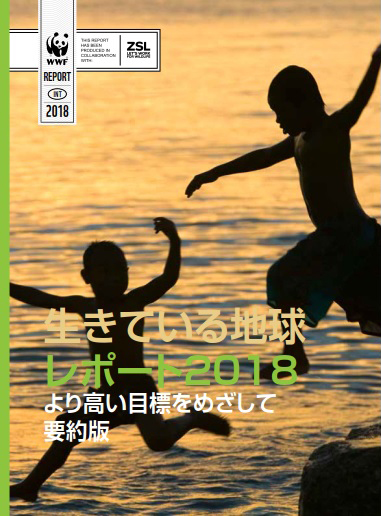
2018年10月30日に公表された『生きている地球レポート2018』は、1970年以降、脊椎動物の個体群のサイズが60%も減少するなどの生物多様性の危機を伝えています。





















