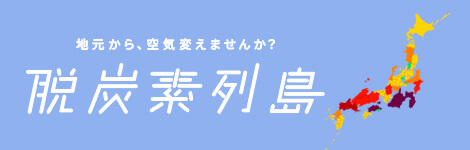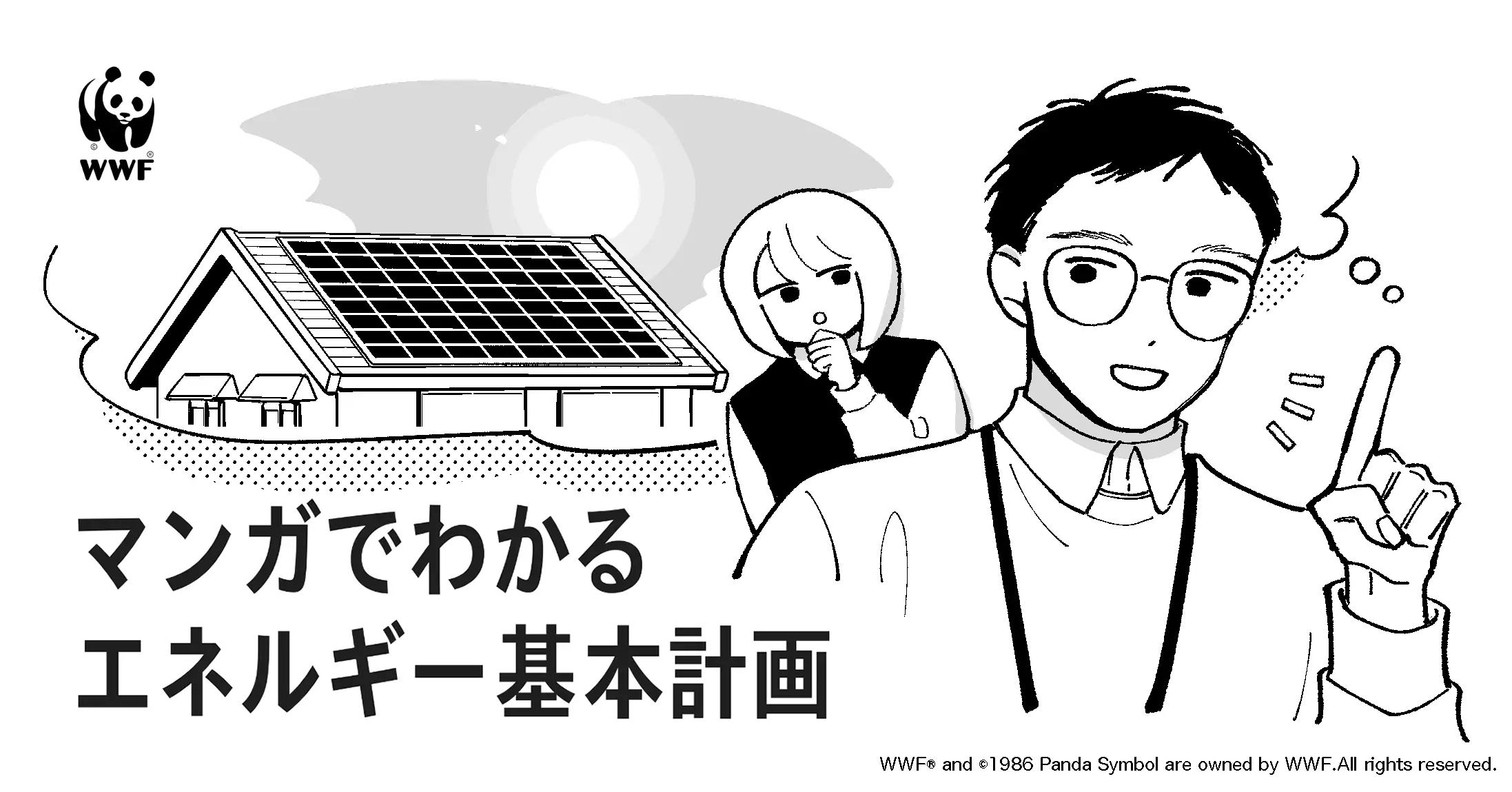WWF声明「岸田首相の省庁横断でのカーボンプライシング検討は、 GXリーグなどの自主的な制度のみに留めてはならない」
2022/01/21
2022年1月18日、岸田文雄首相は「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会を開催し、その中でカーボンプライシングについても方向性を見出すように経済産業大臣・環境大臣に指示がなされた。WWFジャパンは、岸田首相主導の検討指示項目の中にカーボンプライシングが含まれたこと自体は歓迎するが、それが脱炭素へと寄与するキャップ&トレード型排出量制度を中心としたポリシーミックスへとつながることを求める。
これまで菅前政権・岸田政権の下で成長に資するカーボンプライシングについて議論がなされつつも、2021年12月の与党税制改正大綱ではカーボンプライシングには全く触れられず、同月の環境省審議会でも検討に留まった。経済産業省では「GXリーグ」の基本構想について検討が進んでいるが、これは自主的取組が中核を占めるに過ぎない。日本の出遅れはすでに日本産業にとって危機的なところまで来ている。日本にとって必至の産業構造の転換や労働力の公正な移行、ライフスタイルの変革などが促される政策がないままでは、日本の産業は脱炭素経済の中でさらに競争力を失っていきかねない。
首相主導で多くの省庁の大臣が関わる今回の検討では、実効力のあるカーボンプライシングを導入することを決定する必要がある。エネルギー需要側の転換を促しながら脱炭素型の経済成長のドライバーとして、一定規模以上の企業に対するキャップ&トレード型の排出量取引制度や、実効力のある水準の炭素税など日本に適した制度設計に早期に着手できるように、具体的な工程表をもって示すべきである。
特に今回の検討に当たって肝に銘じるべきは以下の2点である。
①「一部のやる気のある企業のみの自主的な取り組みを促す仕組み」などでお茶をにごすことなく、脱炭素化へ向けた経済全体の底上げを図る制度にするべきである。GXリーグの導入のみでは日本全体の脱炭素化を進めるには不十分である。
②カーボンプライシングはエネルギー需要側の取り組みをインセンティブをつけて促す制度であるため、関係する多様なステークホルダーの意見を取り入れるべきである。従来のように重厚長大産業を中心とする産業団体の声のみを優先するのではなく、脱炭素化の経済成長の主要な担い手である産業、たとえばIT産業や小売、食品、建築などの産業界、金融セクター、および将来を担う若者世代を含む市民社会や海外の有識者など多様な意見を取り入れる議論プロセスにするべきである。
そもそも日本がカーボンプライシングの早期導入を図るべき理由を以下3点述べる。
1. 目標達成に向けた政策的担保の欠如:自主取組から政府主導の政策への移行が必須
パリ協定や日本が掲げる目標の達成を、現在及び検討中の施策では担保できる見込みがたっていない。COP26を経て、国際社会の目標は事実上世界の平均気温の上昇を1.5度に抑えることへと移行した。中でも重要なのは、2030年に向けて一層の取組みの深化であり、各国が提出するNDCは今後も継続的に目標の引上げが求められていく。主要国ではキャップ&トレード型の排出量取引制度や二酸化炭素排出量に比例する形での炭素税といったカーボンプライシングの導入が既に進んでおり、政府主導で排出削減を強化していく土台があるのだ。
一方、日本の施策では自主行動計画やイノベーションなど産業界の自主的取組に大半を委ねており、目標を達成できるか否か、仮にできたとして今後8年で46%削減する時間軸に沿うかははなはだ心もとない。地球温暖化対策のための税はあるが、税率がトン当たり289円と著しく低く、炭素削減へのインセンティブ付与に寄与していない。既存エネルギー諸税をもって日本にもカーボンプライシングがあると強弁する向きもあるが、これらは炭素比例でないため、そもそもカーボンプライシングとしての効力がない。
経済産業省で現在検討が進む「GXリーグ」の下でも、制度への参加、目標の設定、超過削減分の取引等はあくまで自主的になされるものとされており、政策不在の状況は変わらない。今回の検討において、GXリーグなどの自主的取り組みの導入のみで留めるならば、それは既存路線の延長であり、日本産業の今後の成長にはつながらない。
カーボンプライシングではないが、建築物省エネ法改正案の検討先送りの流れが出てきていることも、目標達成に向けた政策的担保の欠如を憂慮させる要因となる。
2. 制度の不在による日本企業の国際競争力の毀損:投資の予見可能性が必須
日本において明示的なカーボンプライスがないことは、日本企業の国際競争力を結果として削ぐ。各国・地域で明示的かつ段階的に引き上げられていく炭素価格が存在する中、国内・域内における競争の公平性等の観点から、炭素国境調整措置の導入が欧州ではすでに予定されており、アメリカや中国などにおいても検討されている。自主的取組に大きく依存する施策に留まり、明示的なカーボンプライスが存在しない日本では、当該措置の対象となっていくおそれがある。
加えて、現在の日本の施策では、2050年までにカーボンニュートラルを達成する上で炭素価格がどのように推移するか企業は把握できない。炭素価格の目途が立たないと新たに導入する脱炭素技術の投資回収の予想ができず、企業の迅速かつ円滑なトランジションを実現することができない。
カーボンプライシングがあれば、企業は排出量をコストと捉え、炭素価格の上昇ペースと上昇幅を把握することで、脱炭素技術への投資計画の立案が容易になる。すなわち、炭素税の下では政府によって税率の段階的な引上げが示されることで、また排出量取引制度の下では排出総量の段階的な引き下げ、もしくはオークション制度によるオークション価格の段階的引上げを示すことで、それぞれ炭素価格の上昇ペース・上昇幅を確認できる。それを基礎として、企業による脱炭素技術への投資が促進される。これらは脱炭素社会と親和性が高いデジタルトランスフォーメーションに向けた投資を促す効果も期待し得る。
日本産業が脱炭素化へ向けた移行において長期的な投資計画を立て、日本産業が今後も国際競争力を持ち続けられるためにこそ、政策の後押しを一刻も早く用意するべきではないか。
3.財政的措置に対する原資の欠如:脱炭素化を促進する財政基盤としても有効
脱炭素化には、長期的かつ巨額の投資が必要であることは言うまでもない。今後2050年に向けた長期にわたっての財政的な支出が必要であるが、まずは2030年までに温室効果ガス排出量の半減を目指す中で、コロナ禍からグリーンリカバリーを果たすためにも大規模な財政出動が必要である。現状の施策はこうした費用に対する予算をどこから確保するか明らかではない。日本の厳しい財政状況に鑑みると、将来世代に負担を残さないためには赤字国債の発行にも限界がある。
カーボンプライシングは社会全体での費用面において効率的にカーボンニュートラルを達成できる。また副次的な効果として炭素税からは一定期間にわたる税収が得られ、例えばピーク時に年間約6兆円の税収を見込む試算もある 。税率アップによる経済的な影響は、税収を企業の省エネ投資や技術開発補助に回すなどの税制中立の設計により緩和することができる。もちろん本来の制度趣旨は経済的インセンティブに基づくカーボンニュートラルへの移行の促進であり、目標達成に近づくにつれて減少し最終的にゼロとなる点で、これらの税収は恒久的なものではない。しかし、その活用でカーボンニュートラルに向けた更なる取組みの加速が可能となる。このようにカーボンプライシングは、財政面・費用面でも強力な政策ツールとなる。
「GXリーグ」基本構想をはじめ現在及び検討中の施策は、2050年までにカーボンニュートラルの達成、2030年までに温室効果ガスの排出量の半減という目標の達成に応えるものではない。今回の首相直下の省庁横断でのカーボンプライシングを含めた脱炭素化へ向けた施策の検討において、キャップ&トレード型の排出量取引制度をはじめとしたカーボンプライシングが早期に導入されることを求め、WWFジャパンとしても引き続き議論を注視する。