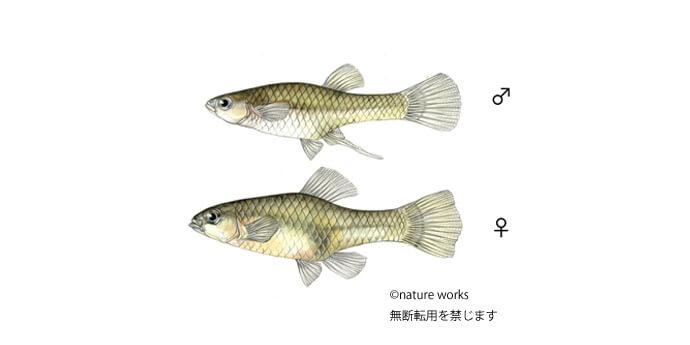何が問題? 水産物の「産地偽装」
2022/02/02
2月1日、「熊本産アサリに外国産混入していた可能性」がある、というニュースが報道されました。
これは農水省が行なった、売られている国産アサリのDNA分析を行なった結果、明らかになったもので、調査によれば「熊本産」の商品31点のうち30点に外国産のものが混ざっている可能性があった、とのことです。
また、報道によれば、熊本県で報告されたアサリの漁獲量と同県産の表示で販売されているアサリの量を比較すると、後者の方が圧倒的に多い、という実情も明らかになっており、今後の捜査と法的対応の行方が注目されています。
こうした水産物の産地偽装は、以前から繰り返し行なわれてきました。
ロシアから日本へのカニの輸入量が、輸出量の記録を上回っていたり、養殖で使われるウナギの稚魚の産地がどこなのか、全く追跡ができなかったり。
今も解決されていない問題は多々ありますが、こうした「出所の分からない」水産物の流通が、産地偽装につながっていることは間違いないでしょう。
産地偽装は違法行為にあたるケースが多いため、それだけを取っても、当然許されることではありませんが、何よりもその大きな問題は、どこで、誰が、どれだけその魚や貝を獲ったのか、それが分からない、つまり「トレーサビリティ」が確保できていない、ということです。
これができなければ、乱獲や違法な漁業、また就労者に対する搾取など、さまざまな問題が、漁業の現場で生じても、把握することも改善することもできません。
トレーサビリティの確立は、水産資源を守る一番の重要な要素であり、それを脅かす産地偽装は、ちょっと地名を書き換えた、くらいでは収まりのつかない、深刻な問題なのです。
天然の水産資源は、全て海の野生生物。その過剰な漁獲が今、海の生物多様性を危機に追いやっています。
環境保全という観点からも、看過できないこの産地偽装。
漁業資源の保全、管理、また人権への配慮から、国際的にも水産物のトレーサビリティの確立を求める動きが強まる中、私たちも、日本での法的な対応の強化を求める政策の提言に、引き続き力を入れていきたいと思います。