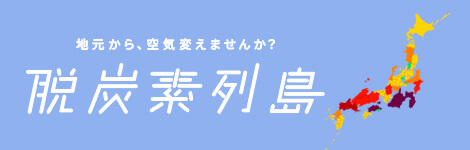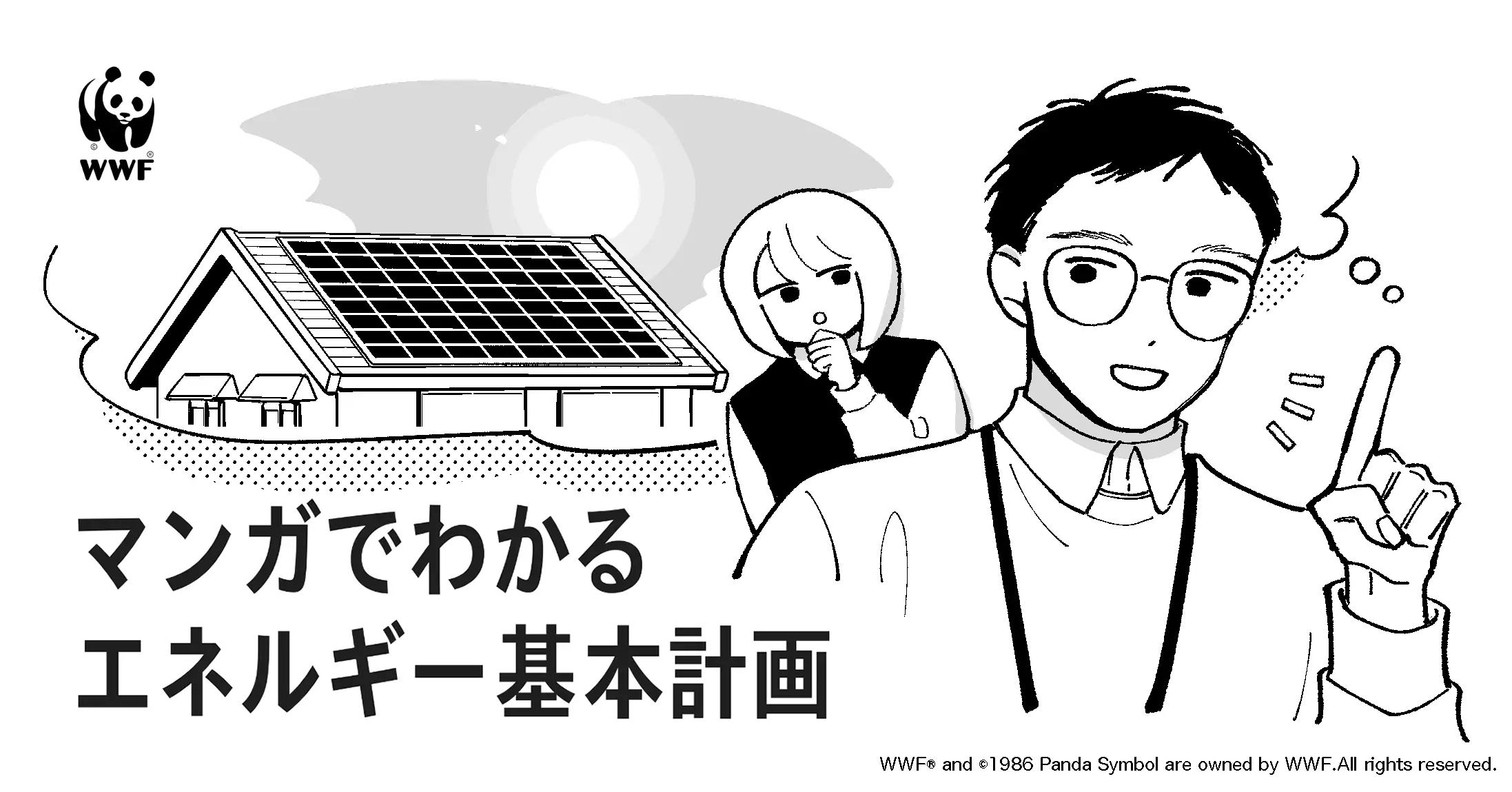WWFエネルギーシナリオシンポジウム~2030年46%削減はどのようにして実現可能か~を開催
2021/10/26
- この記事のポイント
- WWFジャパンが「2030年にCO2排出量約50%削減」を可能とする社会像を描いた「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」。2021年5月28日、このシナリオの実現に必要な費用(コスト)について発表するオンラインセミナー「WWFエネルギーシナリオシンポジウム~2030年46%削減はどのようにして実現可能か~」を開催しました。このセミナーには、2050年脱炭素を目指す企業の関係者を中心に、約300名の方に視聴いただきました。内容の解説と当日資料をご案内いたします。
シンポジウムの目的
2021年4月22日、当時の菅義偉総理は「2030年温室効果ガス削減目標46%、さらに50%の高みを目指す」と表明しました。
9年後の2030年に46%以上の削減を実現するためには、産業界の取り組みが最も重要です。
その実現には、どのような取り組みと、どれくらいの費用(コスト)が必要となるのでしょうか?
WWFジャパンは、2020年12月に発表した「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」で、2030年にCO2排出量約50%削減を可能とする社会像を示しました。
そして、2021年5月28日、新たにそのシナリオの実現に必要な費用を算定した「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ<費用算定編>」を発表するシンポジウムを開催。
このシンポジウムでは、シナリオの概要をお伝えするとともに、建設、鉄鋼、再エネの各業界から先進的な企業団体をお招きし、脱炭素化に向けたビジョンと実践についてご紹介いただきました。
当時の各登壇者の発表の要旨と資料、および講演の動画をご紹介いたします。
プログラム
司会 WWFジャパン顧問 前田智子
1)開会挨拶:WWFジャパン 池原庸介
2)シナリオ解説:株式会社システム技術研究所 所長 槌屋治紀様
2030年宣言:WWFジャパン 小西雅子
3)パネルディスカッション 第1部「WWFエネルギーシナリオを読み解く」
ファシリテーター: WWFジャパン 田中 健
パネリスト:(株)戸田建設 樋口正一郎様 /(株)東京製鐵 奈良暢明様 /(一社)日本風力発電協会 上田悦紀様
4)パネルディスカッション 第2部「各社ビジョンと事例のご紹介」
ファシリテーター: WWFジャパン 小西雅子
パネリスト:(株)戸田建設 樋口正一郎様 /(株)東京製鐵 奈良暢明様 /(一社)日本風力発電協会 上田悦紀様
閉会挨拶:WWFジャパン会長 末吉竹二郎

WWFジャパン 池原庸介

WWFジャパン 田中 健

WWFジャパン会長 末吉竹二郎
各講演の概要
脱炭素社会に向けた 2050 年ゼロシナリオ
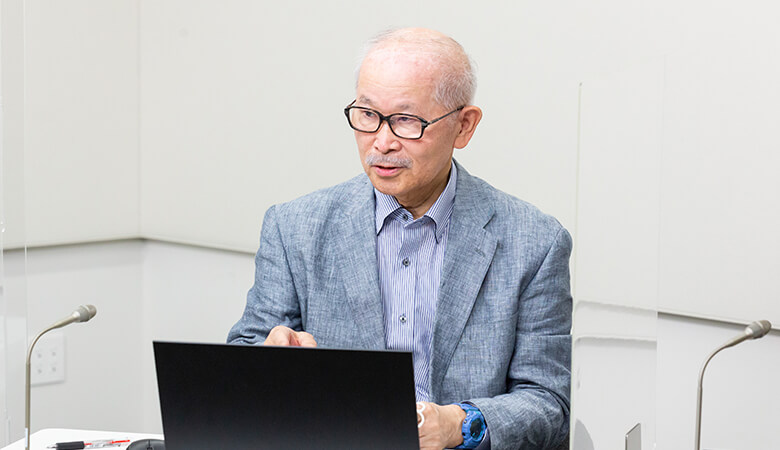
システム技術研究所 所長 槌屋治紀
今回、100%自然エネルギーを実現するシナリオと、その費用を算定いたしましたので、その内容をご説明したいと思います。
2030年には、日本では人口減少により活動量が減少し、エネルギーの効率化が進むことにより、エネルギー需要は2015年比で21.5%削減することが可能です。
また、最もCO2排出量の多い石炭火力を2030年までに全廃しても、既設のガス火力の稼働率を向上させれば補うことができるため、火力発電所を新設する必要はありません。
原子力発電は30年以上経過したものは稼働せず、新設しなければ、2030年で3基322万kWのみになり、2038年以降に全廃されます。
これによって、電力の約50%を太陽光や風力などの自然エネルギーでまかなうようになります。
このエネルギーミックスによって、エネルギー起源のCO2は2013年比で約50%削減が可能になります。
2050年には、人口減少やエネルギー効率の向上にともない、エネルギー需要は2015年の約半分に減少。
電力・熱・燃料のエネルギー需要のすべてを自然エネルギー100%でまかなうようになります。
変動の大きい太陽光発電や風力発電による余剰電力は、揚水発電所の揚水やバッテリーの充電、電解水素の生産、EVの充電などに利用し、シフト可能なエネルギー需要に対応することで需給を調整するようになります。
こうして生産された水素は、鉄鋼業のほか、船舶や航空機などの運輸部門で利用されるようになるでしょう。
こうした取り組みを通じて、すべてのエネルギー用途に自然エネルギーを供給し、エネルギー起源のCO2も、温室効果ガスもゼロにすることが可能です。
こうした未来に向けたWWFの「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」を実現するためには、2020年から2050年までの30年間に、省エネルギーに81兆円、自然エネルギーに163兆円、電力関係に9兆円で、合計253兆円、年間8.5兆円の投資が必要になります。
これに対して、運転費用は省エネルギーでマイナス56兆円、自然エネルギーでプラス25兆円、電力関係にプラス9兆円で、合計マイナス22兆円になりました。
また、同じ時期のGDPは平均750兆円であり、このコストは対GDP比で1.1%に相当します。
こうして考えると、2020年からの30年間の自然エネルギーの設備投資は、全体として見れば回収が可能で、有効な投資と言えます。
結論として、2030年までには石炭火力を廃止し、CO2排出は50%に削減が可能。2050年には、国土面積の1~2%は使用しますが、100%自然エネルギーの供給は可能。その費用はGDPの1.1%ほどの負担と試算いたしました。
発表資料 株式会社システム技術研究所 槌屋治紀様
脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ〈費用算定編〉
最も重要な2030年エネミックス:WWFからの提言

WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー)小西雅子
日本が脱炭素社会に向かっていく上で、今、一番重要な「2030年のエネルギーの在り方」について、WWFの提案を紹介いたします。
日本が2050年脱炭素を達成するために、2030年46%削減は必達の目標です。
世界全体で2050年までにカーボンニュートラルを実現するためには、2010年比で45%減が必要ですが、先進国である日本は1%高い46%減、さらには50%の高みをめざしています。
46%削減を達成するためには、年率3.38%の削減が必要ですが、WWFシナリオはこの「2030年目標の実現が可能」であることを示しました。
WWFシナリオは、まず省エネルギーの最大限の推進によって最終エネルギー需要を削減したうえで、自然エネルギーの割合を引き上げることによって、2030年までにCO2排出量を53.3%(温室効果ガス排出量を49.4%削減(2013年比))が実現できることを示しました。
そして、エネルギー効率の改善は現状の技術とその延長線上で可能であること、さらに最も大きな課題である石炭火力を2030年までに全廃し、自然エネルギーの割合を高めることが現状の電力インフラの範囲内で可能であることを示したことに最大の特徴があります。
政府の長期エネルギー需給見通しとWWFの提言の違いは、電力に占める自然エネルギーの割合を、政府が22~24%としているのに対し、WWFは約50%とし、石炭火力の割合では政府が26%であるのに対してWWFは0にしている点にあります。
(なお、2021年8月に発表された第6次エネルギー基本計画において政府案は電源に対する自然エネ比率を36~38%に引き上げ、石炭火力を19%に改定。)
それを補うのがガス火力。現状35~50%のガス火力の稼働率を60~70%に高めることによってカバーします。
果たしてそれが可能なのでしょうか。WWFはアメダス2000のデータを使って365日1時間ごとの自然エネルギーの発電量を予想するダイナミックシュミレーションを行ない、石炭火力を2030年までに廃止しても電力需給に問題はないことを確認しました。
また、変動の大きな再エネからの余剰電力を活用してグリーン水素をつくり、脱炭素化が難しい燃料や熱需要に充てることによってエネルギー全体を脱炭素化していくことにWWFシナリオの特徴があります。
その実現に必要なコストは、2020年から2030年までの10年間で合計61兆円です。
これに対して、運転費用は省エネルギーがマイナス21兆円、自然エネルギーがマイナス15兆円となることから、合計でマイナス36兆円になることがわかりました。
つまり、省エネルギーの導入が有効であり、自然エネルギーの投資には時間がかかりますが、全体では2035年から正味でマイナス(便益)に転じます。
一方、電力価格は自然エネルギーが増加するにつれて燃料費が不要になるため、2030年までに微増するものの、その後は一貫して減少していきます。
すなわち、自然エネルギーを中心とする社会には将来的な価格優位性があることが示されました。
脱炭素をめざす産業界には、グローバルスタンダードで客観的なイニシアチブであるSBTi など、独立した機関の提言も参考にして、将来の方向性を検討していただきたいと思います。
発表資料 WWFジャパン 小西雅子
パネルディスカッション第1部 WWFエネルギーシナリオを読み解く
このセッションでは、WWFシナリオについて、建設、鉄鋼、再エネ業界の登壇者3名から、それぞれの業界に関連した質問をいただき、シナリオ分析を行なった槌屋氏が回答する形式で、シナリオへの理解を深めました。
戸田建設株式会社の樋口正一郎価値創造推進室副室長からは、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の建設コストについて、東京製鐵株式会社の奈良暢明取締役総務部長からは、2030年以降の電力料金が安くなる理由について、日本風力発電協会の上田悦紀国際部長からは、再生可能エネルギーの費用対効果について、それぞれご質問をいただきました。

左から東京製鐵株式会社の奈良暢明取締役総務部長、日本風力発電協会の上田悦紀国際部長、システム技術研究所 所長 槌屋治紀、WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー)小西雅子
第2部 各社ビジョンと事例のご紹介

このセッションでは、建設、鉄鋼、再エネの各業界において、早くから脱炭素の取り組みを経営に取り入れてきた各社が、その実例を発表。
ファシリテーターの小西がそれぞれの発表に対する質問を通して、各社の取り組みへの理解を深めました。
また、この活発な議論を通して、ZEBの建設には自然エネルギー由来の電力で生産された電炉材が利用される事例、また洋上風力発電の費用の大部分は風車の建設や送電線の敷設などへの投資である事例などを通して、各業界が連携しながら脱炭素を目指す重要性が確認されました。
脱炭素社会を実現する建設業界の挑戦 ~気候変動への対応でレジリエントな企業へ

戸田建設株式会社 価値創造推進室副室長 樋口正一郎
戸田建設は1994年に「戸田地球環境憲章」を策定して以来、環境への取り組みを推進してきました。
2016年からは国際的なイニシアチブであるSBTi、CDP、RE100に参加。
2020年にはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく分析を行ない、脱炭素社会を目指すことが当社の利益増に寄与することを確認しました。
2050年に脱炭素を達成に向けたロードマップを策定し、再エネ電力への切り替えを行っていますが、脱炭素を実現するには、重機などの燃料を軽油から、再エネ電力や水素へ転換することが求められます。
建設業としてZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やZEB(カーボンマイナス建築物)の研究開発に取り組んでおり、2030年には新築建物のすべてがZEBになる予定です。
ESG経営を推進するため、2016年に取締役および執行役員へのインセンティブプランとして業務連動型株式付与制度を導入しました。
2019年からは、CO2削減目標の達成度を加え、気候変動の実情に応じて変動させています。
発表資料 戸田建設株式会社 樋口正一郎様
脱炭素社会を実現する製鉄業界の挑戦

東京製鐵株式会社 取締役総務部長 奈良暢明
鉄鋼業からのCO2排出量は1億5,800万tと産業界の中で最大であり、日本全体の13.3%を占めています(2018年度)。
しかし、1tの鉄を生産するために排出されるCO2は、高炉製鋼法が2tであるのに対し、電炉製鋼法では0.5tにすぎません。
また、先進国では、製鉄の歴史に比例して鉄鋼の蓄積量が高くなっており、日本もおよそ14億tの鉄鋼を国内蓄積する、世界有数の鉄の資源国となっています。
そのため、この蓄積された膨大な鉄を電炉で再生することで、脱炭素化の達成に寄与することができます。
そのうえ、電炉の電力を再生可能エネルギーに変換すれば、さらにCO2排出量を削減することができます。東京製鐵では工場の屋根に設置した太陽光発電の電力を生産プロセスで使用しています。さらに、2018年度からは春や秋の日中に需要を上回る太陽光発電の電力を使って電炉を稼働させており、電炉を電力需給の調整弁にすることで再エネの拡大に貢献しています。
発表資料 株式会社東京製鐵 奈良暢明様
脱炭素社会を実現する再エネ業界の挑戦~日本の風力発電の現状と将来像

日本風力発電協会 国際部長 上田悦紀
世界の風車は2020年末に陸上・洋上を合わせて約34万台まで増加し、設備容量は7億3,400万kWに達しました。今や世界の電力の約8%は風力発電によってまかなわれています。
しかし、世界の風力発電に占める日本の割合は非常に小さく、新規で51.6万kW、累積で444万kWという導入実績は、いずれも世界全体の0.6%にすぎません。
国内の年間電力需要に占める割合も1%に満たず、第5次エネルギー基本計画に基づく2030年のミックスでも1.7%、陸上・洋上の合計で1,000万kWに据え置かれていました。
2020年10月のゼロ・カーボン宣言で、この状況が一変しました。
同年7月に「洋上風力発電の産業競争力強化に向けた官民協議会」が開催され、同12月に発表された「洋上風力産業ビジョン」では、洋上風力に対して2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000~4,500万kWの導入目標(認定ベース)が示されました。
日本風力発電協会は、2050年カーボンニュートラルの実現をめざし、意欲的で明確な中長期導入目標の設定を提言しています。
洋上風力の主力電源化をめざして、インフラ(送電網、基地港、国内サプライヤー)を整備し、規制を緩和すれば、2030年代の洋上風力の発電コストを8~9円/kWhまで低減することは可能であり、建設・保守・機器製造・観光などを通して日本の経済と雇用にも貢献することができます。
発表資料 一般社団法人日本風力発電協会 上田悦紀様
イベント概要:WWFジャパン エネルギーシナリオ シンポジウム~2030年46%削減はどのように実現可能か~
日時:2021年05月28日(金) 13:30 ~ 16:00
場所:オンライン開催
主催:WWFジャパン