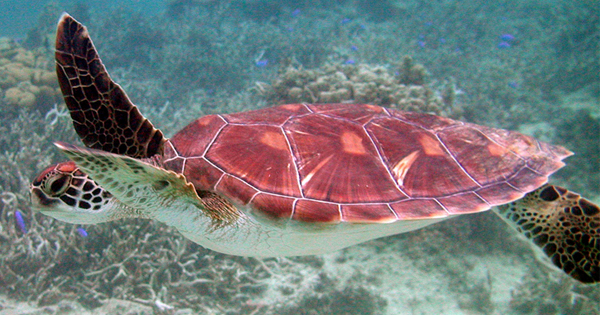クマノミとイソギンチャクの共生
2020/08/06
こんにちは。沖縄の石垣島サンゴ礁保護研究センターの西田です。
鮮やかなオレンジの身体に白い帯。
イソギンチャクの中に隠れている魚といえば、そう、クマノミです。
映画で有名な「ニモ」もその1種で、正式名はカクレクマノミ。
センジュイソギンチャクやハタゴイソギンチャクにすんでいることが多く、ここ、石垣島の海でも
イソギンチャクに隠れたり顔を出したりする人気者です。
石垣島近海にはカクレクマノミを含めて6種類のクマノミが生息しており、個体によって模様も色も大きさも違います。
種類ごとにすむソギンチャクが決まっていると言われ、さらにそれぞれ個体にも、お気に入りのイソギンチャクがある模様。
実際、クマノミの写真や映像を見ると、色々な種類のイソギンチャクと一緒に写っています。

石垣島で見られるクマノミたち。(左上)クマノミ、(右上)カクレクマノミ、(左下)トウアカクマノミ、(右下)ハマクマノミ。それぞれ違う色、形のイソギンチャクと共生しています。
このクマノミとイソギンチャクは、生きもの同士が「共生」の関係にある、とても分かり例として知られています。
「共生」とは、2種類以上の生きものが一緒に生活し、お互いに利益を得ている関係のこと。
たとえば、イソギンチャクの触手には毒があり、触れた生きものはマヒして食べられてしまいますが、クマノミは触手に触れても耐性があるので大丈夫。
そこで、クマノミはイソギンチャクに外敵から守ってもらいながら、近くを泳ぐことで新鮮な海水をイソギンチャクに送り、元気にしてあげています。
まさに、たくさんの生物が暮らしているさまざまな生態系が形づくられているサンゴ礁ならではの「共生」のありかたといえるでしょう。

ハナビラクマノミとセジロクマノミ。ハナビラクマノミは長い触手、セジロクマノミは短い触手のイソギンチャクと共生していることが多いです。
この石垣島のサンゴ礁の海では、クマノミと共生しているイソギンチャクがとてもきれいな色で大きく広がっています。
また、クマノミたちもお気に入りのイソギンチャクで安全に暮らしています。
そんな豊かな南西諸島の海の、美しい自然が残される未来を目指して、これからも活動を続けていきます。