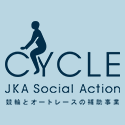横浜で第3回学校教員向けESD講座を開催
2019/07/02
2016年から、横浜市で毎年開催しているESD講座(持続可能な開発のための教育)。
今年は6月8日(土)に実施し、小中高校から28名の先生方の参加を得ました。
地球温暖化などの環境問題に関する資料を提供し、さらに、模擬体験的に学びを深めるアクティビティを9本ご紹介。
今回、新たに教材に加えたのは、最近、大きな関心を集める「プラスチックごみ問題」に関する話題。

教材とアクティビティの道具類(左)グループワークで議論して、答えを見つけます(右)
プラスチックは、利便性が高く、コストも安価とあって、簡単には手放せない側面があります。
ロールプレイ活動では、班ごとにストロー、レジ袋、ペットボトルの廃止に賛成、反対の立場に分かれて議論を展開。身近な問題だけあって、制限時間をオーバーするほど議論が白熱しました。
2050年の地球を想像する活動もあり、環境を守るため、「少し不便になった地球を受け入れたい」という声が聞かれました。これからは価値観の転換をともなうライフスタイルの変化が求められていきそうです。

2050年の地球をイメージするアクティビティ「ウェビング」(左)。「ウェビング」は班ごとに多様な意見が出て盛り上がりました。
アンケートでは、「活動があり、聞くだけの時間が少なかったのは参加している側からすると楽しい内容だった」、「授業に役立つアクティビティが多く、ありがたかった。学校に帰って、子どもたちに還元できたらと思う」といった感想が見られました。
満足度の評価は5点満点で平均4.7点。好評のうちに終了しました。
9月以降、希望する学校は香港の学校と環境に関するメッセージ交換をおこない、国際交流にチャレンジ!
出前授業で学校現場に足を運ぶと、SDGs(持続可能な開発目標)のアイコンを校内に張り出し、意識を高めている様子に刺激を受けることがあります。

こうした動きを助けながら、WWFジャパンでは、引き続き横浜市内でのESD推進に貢献してゆきます。
※このイベントは、競輪の補助を受けて開催されました。