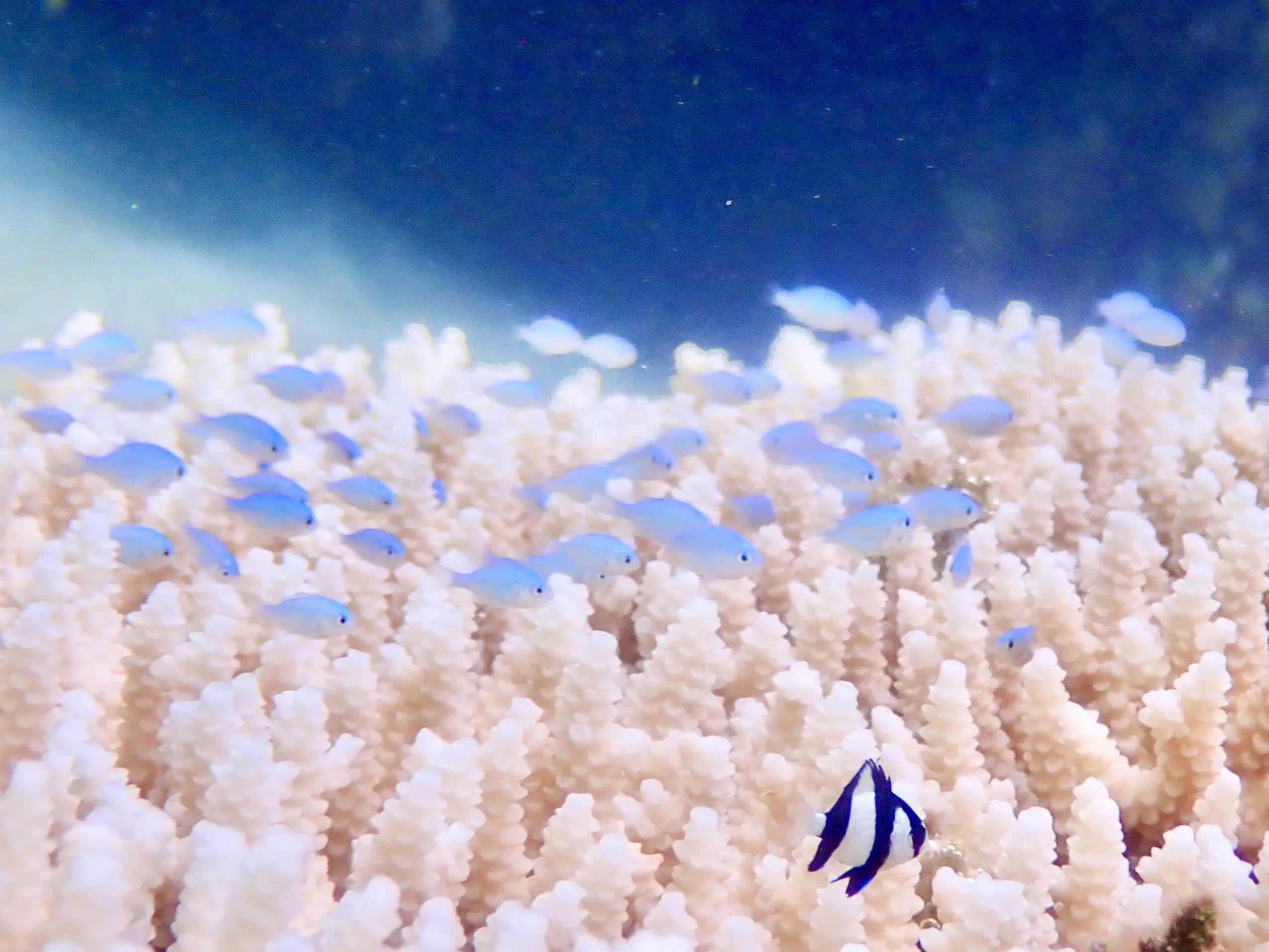【WWF声明】石炭火発の廃止時期明示に足並みを揃えられなかったG7首脳宣言、その要因である日本政府に抗議し、国内議論の前進を要請する
2024/06/18
2024年6月15日、イタリアのプーリアで開催されたG7首脳サミットは首脳宣言を採択した。WWFジャパンは、2030年までの石炭火発の段階的廃止をG7各国の首脳が決断できず、4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケと同じ表現に留まり、抜け道を残したことに抗議する。
首脳レベルでも石炭火発を廃止する年限として2030年代前半という具体的な時期が合意されたことは、最低限のラインに踏みとどまったと言える。しかし、廃止時期の遅さや抜け道の許容も変わっていない点で妥当でなく、2030年までの段階的廃止を明示するべきであった。中でも日本は廃止時期の明示に反対するなど足を引っ張る側に回ったことに抗議する。
IPCC第6次評価報告書によれば、既存の火力発電所等からのCO2排出量ですらパリ協定の掲げる1.5度目標の達成に向けて許容されるCO2排出量を超えるとされ、火力発電所を使い続ける余地はない。そして、1.5度目標に整合的なIEAネットゼロシナリオでは、OECD諸国等の先進国経済では石炭火発を2030年までに廃止することが必要とされている。また、2024年11月のCOP29の主要テーマとなる資金でも、今回の首脳宣言では特段新しい宣言は無く、モメンタムの形成には不十分だった。共同声明で示されたアフリカ諸国でのクリーンエネルギー普及に向けたイニシアティブの立ち上げも重要だが、緩和や適応、「損失と損害」での資金の充実に資する追加的かつ定量的なコミットメントも必要だった。
こうした点で不十分さの残る今回の首脳宣言ではあるが、議論をリードする側では無かった日本には参酌すべき点も多い。特に次の3点で国内政策の改善を図るべきである。
(1)次期NDCの議論では2035年GHG削減目標で2019年比60%減をどの程度上回れるかに力点を置くこと
今世紀末までに世界の平均気温上昇を1.5度に抑えるには、温室効果ガス排出量を世界全体で2019年比2030年43%、2035年60%削減が必要とされる。これは、2023年3月にIPCCが示して以来、G7広島サミット首脳宣言やCOP28合意文書で重ねて確認されてきた。今回の首脳宣言でも不変の目標として言及される中、排出削減の責任と能力を有する先進国として、日本がこの水準を下回る目標を掲げることはもはや国際的に許容されない。
2024年6月末から始まる次期NDCの議論では、どのようにすれば2035年GHG削減目標で2019年比60%減を最大限上回れるかに焦点を合わせるべきである。例えば、WWFジャパンが2024年5月に公開した「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ2024版」(以下、WWFシナリオ2024)では、2035年にGHG排出量を2019年比62.7%(2013年比67.9%)にできることが示されている。こうした広く社会に存在するNGOや独立系シンクタンクの分析も勘案して検討が進められる必要がある。
(2)第7次エネルギー基本計画では、まずは2030年までに国内での再エネ3倍を盛り込み、石炭火発の段階的廃止計画を明示すること
COP28では1.5度目標の達成に向けて、2030年までに世界全体で再エネ設備容量を2019年の3倍にすることやエネルギー効率の改善率を2倍にすること、化石燃料からの転換を加速させていくことなどが合意された。今回の首脳宣言では、当該合意を歓迎した上で、その実現に向けて国内政策を展開する意思が示されている。それに合致するように、日本も国内での取組みを強化する必要があるところ、折しも現在議論中の第7次エネルギー基本計画にはCOP28での合意を確実に反映させなければならない。
WWFシナリオ2024は、2030年までに再生可能エネルギー設備容量を2019年の3倍以上にできると示す。その理由として、太陽光や風力の設備利用率の向上が望めることや、導入ポテンシャルが十分にあることなどが挙げられる。加えて国内の石炭火発については、太陽光と風力で年間を通じて十分な発電量を確保できるほか、既設ガス火力の稼働率を上げて補完可能なため、2030年までに廃止しても電力供給に問題は生じない。
2030年までに国内で再エネを3倍にして省エネを最大限進めること、同時に石炭火発を廃止していくこと、さらにG7首脳宣言で繰り返し約束されている「2035年までに電力部門の完全又は大宗の脱炭素化を達成する」ことを第7次エネルギー基本計画に盛り込んでこそ、COP28の合意、そして今回のG7首脳宣言に応えたと言える。
(3)国内の資金を再エネ・省エネ技術に振り向けるために、十分な炭素価格を伴うカーボンプライシングを早期に導入するべき
パリ協定の下では、GHG排出が少なく、かつ気候変動にレジリエントな発展に整合する資金の流れが求められる。今回のG7首脳宣言も、非効率な化石燃料補助金の廃止や、環境十全性の高い炭素市場、カーボンプライシングの重要性を再確認した。
日本国内での資金の流れを大きく変えて、温暖化対策を加速させるのに特に重要になるのがカーボンプライシングである。省エネの強力なドライバーとなるだけではなく、再エネの導入にも大きく貢献する。例えば、太陽光発電協会の試算では、カーボンプライシングの実施によって太陽光発電の導入ポテンシャルの多くが顕在化することが示されている。
その制度設計では、十分な炭素価格を形成できるものにしなければならない。IEAは2050年ネットゼロの実現には、先進国経済で2030年に140ドル(約21,000円:1ドル150円の場合)が必要と試算する。他方、日本のカーボンプライシングを基礎づけるGX推進法では、炭素価格に上限を設け、この水準の実現は不透明である。IEAの示すタイムラインでの炭素価格を形成できるように、導入時期を可能な限り前倒ししつつ、単価上限が制約になる場合にはそれを撤廃するべきである。
以上3点の改善が図られてこそ、日本国内の脱炭素化が大きく進展し、データセンターや半導体工場といった日本経済の今後の推進役として期待される産業の立地に有利な環境も整う。今回のG7首脳宣言で改めて示された方向性を見誤ることなく、次期NDCや第7次エネルギー基本計画の議論が進み、温暖化対策が実施されていくことをWWFジャパンは期待する。