東京と九州の高校生をつなぐ、水田プロジェクトスタディツアーを開催!
2019/11/22
氾濫原の自然と「田んぼ」の環境
現在、日本では淡水魚類の42%が絶滅の危機にさらされています。
その多くが生息している環境が、「水田」そしてその周辺をめぐる水路といった、人の手が入ったウェットランド(湿地環境)です。
過去の約半世紀の間に、コンクリートなどを使った水田や水路の近代化と改修が進み、生物の生息に適した環境が、広く失われてきたことが原因です。
そもそも、田んぼに生息する水生生物の多くは、かつては自然の氾濫原にすんでいたと考えられています。
氾濫原とは、河川の周りにある草地や河川敷、湖沼などを含む自然環境で、冬季にはほとんど水がないが、夏季には降雨により川の水位が大きく上がり、湿地帯になるような場所を指します。
こうした場所に生きる日本の魚や水生昆虫などは、冬は川の深い場所に潜み、夏は広く移動しながら、冠水する植物の間で産卵するなど、変化に富む環境に適応し、進化してきました。
やがて、稲作が広く行なわれるようになると、氾濫原の自然は水田に作り替えられましたが、昔ながらの水田では、季節に応じた水位の調整が継続されてきたため、生きものたちも人や農業と共生するかたちで、生き延びてきました。
メダカやドジョウといった里山の身近な魚たちは、その代表ともいえる生きものです。
現代にあっても、この生きものたちが生きる上で、水田の自然の豊かさ、多様性が欠かせません。

有明海沿岸の水田地帯にある豊かな水路
しかし、近年は水路などをコンクリートで固め、水路(クリーク)と田んぼを直接つながずに、ポンプを使って水を入れるなどの近代化が進んだため、生きものたちにとって移動や繁殖がしにくい、生きづらい環境が広がってきました。
今ではすっかり希少になり、絶滅が心配される水生生物も少なくありません。

有明海に流入する河川にのみ分布するアリアケスジシマドジョウ。生息環境である植物の多い水田周辺の水路などが改修され、絶滅の危機にある。
かつての氾濫原の自然が失われ、それに代わる環境として命をつないできた水田の消失は、その危機をさらに大きなものにするおそれがあります。

水田の生きものだけではなく、農業と一緒に両輪で応援していくことが大切。
農業に忍び寄る高齢化・後継者問題
この問題を解決するためには、生きものの生息環境である「水田」を、そこで営まれる農業と共に保全していく、という取り組みが欠かせません。
そしてその中には、現代の日本の農業が抱える問題にも通じた課題が含まれています。
たとえば、農業者の高齢化・後継者問題です。
WWFジャパンが現在保全に取り組んでいる、九州の水田地帯でも、農業者の方々の中では、60代が若手農業者と呼ばれている現状があります。
また九州の農業高校では、卒業後の進路として水田農業に従事する生徒は一学年の数%にとどまっているとのこと。
自然と共生した農業が継続されなければ、氾濫原に代わる、日本の水田・水路の景観を未来に引き継いでいくことはできません。
その保全活動に取り組むWWFにとって、次世代の農業を志す若者が増え、かつその農業が生物多様性と両立する形で発展していくことは、とても大切な課題です。
高校生たちにとっての「水田」
そこでWWFジャパンでは、特に貴重な淡水魚が多く分布する九州の水田地帯をフィールドとして、高校生に生物多様性と農業の共生について考えてもらうイベントをこれまで数回開催してきました。
その中でわかってきたのは、特に地元の高校生にとって、水田や水田の生きものは、近いようで、なかなか触れ合う機会がない場所だということ。
生まれてから十数年田んぼの近くで過ごしていても、田んぼに入る機会はなかなかない、ということでした。
また水田の生物多様性が劣化していることを伝えると、近くに住んでいるのに、知らない間に減っているなんて!と驚きの声も聞かれました。
その一方、同じく未来を担う中高生でも、大都市圏の学校の生徒たちの場合は、全く状況が違いました。
そもそも、身近な場所に田んぼのような環境が無く、生きものが大好きで高い関心を持っていても、実際に足を運び、触れ合える機会がなかなか無かったためです。
こうした中高生の間からは、「自費で九州に行きたい」「WWFが保全に取り組む水田に行ってみたい」との声も上がるほどでした。
東京・愛知から九州へ!実現した高校生「水田」ツアー
この声に応え、何より日本の水田の未来を考えてもらう機会として、WWFジャパンでは高校の先生と協力し、高校生が参加する「水田スタディーツアー」を2019年8月31日、9月1日に開催しました。
このツアーには、佐賀県、福岡県、熊本県、愛知県、東京都の普通科中学校・高校・農業高校の、生物部やボランティア部、SDGsゼミなどに所属する多様なバックグラウンドを持つ生徒43人が参加。
現場の水田を見、学生同士の交流を通じて、農業をめぐるさまざまな立場と課題、そしてその保全と将来について考える機会となりました。
たとえば、生物多様性と農業と共に守るためには、水田の生きものを守りつつ、農業が継続できる手段を確立せねばなりません。
つまり、そうした「生きものと共生した水田」で生産されたお米やその加工品が、流通・消費によって社会で知られ、広がっていくということが求められます。
こうした課題について、生産の場である九州と、消費・流通の場である東京で、何ができるのか。学生の皆さんに水田の生きものたちについて学びながら、考えていただきました。
プロジェクトサイトの生きものと、それを守る価値
2日間にわたるこのイベントはまず、生態学の専門家である佐賀大学の徳田誠先生からWWFプロジェクトサイトの一つである、佐賀平野の生きものについて、現状と課題、また生きものを守る価値などについてお話頂きました。
「自然を守ることを経済価値に変換すると…」といったお話もあり、参加者からは「今まで自然を守ることについて、経済的な側面を考えたことがなかった」といった声も聞かれました。
ここでは、自然を守ることとはどんなことなのか、や、自然を守る意義や価値について、参加者全員で理解を深める時間となりました。

徳田先生の講演に耳を傾ける高校生たち
生きものの場と生産の場である水田、その場の両方の現場の声をきく
徳田先生の講演の後は、農業と生物多様性の両立を目指す取り組みの現場、佐賀市東与賀にある水田へ。
ここは、江戸時代から有明海の干潟を干拓して造成してきた農地で、佐賀県でも屈指の水田地帯が広がっています。
干拓地の堤防の向こう側に広がる干潟と、こうした水田は、水路や河川を通じてつながった一つの自然。
海から水田水路に遡上してくる魚もおり、干潟に飛来する渡り鳥の中にも、水田の環境も利用して生きるものが少なくありません。
そこで佐賀県では、自然と農業を共存させる取り組みとして「シギの恩返し米プロジェクト」を推進してきました。
この日は、このプロジェクトの推進協議会の吉村信行会長より、生徒の皆さんに取組みのご説明頂きました。
さらに、佐賀県を中心に自然観察会を開催しているネイチャー佐賀の増田英治事務局長にクリーク網の歴史・文化について、徳田先生からも再度、東与賀地区の生物多様性の現状と課題をご説明いただきました。
ここでは、参加者から「田んぼをしながら生きものを守るプロジェクトに参加したきっかけ」「プロジェクトを進める上でどんな苦労があったのか」など多くの質問があがり、水田・水路の生物多様性と農業を両立することの大変さや苦労、お米の生産だけではなく、流通・消費の大切さを理解することが出来ました。

現場で佐賀大学徳田先生が水路の生きものを実際に採集してくださいました。その説明を受ける東京の学生たちは目を輝かせていました。

施設内でシギの恩返し米プロジェクトの説明を受けました。隣接する干潟でも、干潟に飛来する渡り鳥についてもレクチャーを受けました。

現場でネイチャー佐賀の増田さんからクリークの成り立ちについて学びました。また現在使われている水田の水システムとかつてのシステムの違いなどもクイズを交えて教えて頂きました。

現場で説明を受けたあとに、合同質問タイムを設けました。現場を見たからこそ、直接お会いするからこそ実感できるご苦労や生きものの大切さを実感することが出来ました。
お米をとりまく現状を理解するワークショップ
水田の現場で、農業者や行政の方たちにも話を聞いた後、参加者の生徒の皆さんは、さらに理解を深めるためのワークショップに参加しました。
このワークショップは、お米の生産・流通・消費に関わる4つの立場に立つ人たちの「価値観」を理解するためのものです。
先に述べた通り、生物多様性と農業と共に守るためには、現場である水田で生産されるお米が、生きものに配慮された形で生産され、流通し、それを消費者が購入することが理想です。
しかし残念ながら、現状そうはなっていません。
その理由は何か。理想を実現するためにはどうしたらよいのか。
関わる人たちの「価値観」を軸に、理解を深める時間を過ごしました。

現場で1日頑張ったあとに実施されたワークショップ。疲れた顔も見せず、白熱した議論が進められました。
参加者がワークショップでなりきるのは、次の4つの立場です。
- 農業者
- 行政
- 企業
- 消費者
学生の皆さんは4つのグループに分かれ、それぞれが担当するステークホルダーの価値観はどんなものかをロールカードから読み取り、米作りや水田水路の生きものに対する意見を述べて、考え、議論します。
たとえば、各グループの参加者は、「生物多様性を守る水田作り」を提案する架空の町長に対して、意見書を作ります。
そして、自分たちの立場で考えたが価値観に基づき、提案に賛成か反対か、賛成ならばどんなことが貢献できるか、反対ならばどうしたら賛成できるか、を想像し議論するのです。
こうした取り組みを行ない、最後に各グループからその意見書の内容を発表しました。

ロールプレイで議論した内容を代表者が参加者に発表。このときは、農業高校の方が発表下さいました。
参加者の生徒の皆さんには、こうした各ステークホルダーの価値観の違いや、相反する部分、類似している部分などを認識してもらい、「生物多様性と農業の共生」の難しさ、ステークホルダー同士の関係の複雑さに対する理解を深めていただきました。
実際に自分たちで出来ることは?
2日目の翌日は、本来の高校生として「生物多様性と農業の共生」のために、実際に何が出来るのか。考えてもらうためのワークを行ないました。
農業のような大きな社会的営みを、自分事としてとらえ、何ができるかを考えるのは、大人でも難しいことです。
そこでまずは学校ごとに分かれてもらい「ステークホルダー・マッピング」という手法で、前日になりきった4つのステークホルダーと、自分たちの間にあるつながりを見つける作業からスタートしました。
これを通じて学生の皆さんからは「自分たちなら現地で生きもの調査ができる!」「テレビ局に田んぼの重要性を伝えてもらうよう、お願いをしたらいいのではないか」「SNSで発信したらいいのではないか」といった前向きな発想から、「こうしてみると自分たちにできることは何もない気がする」といった正直なコメントまで、多種多様な考えが出てきました。

各学校でまとまって議論しあってもらいました。ときおり盛り上がりながら、しっかりとお題に沿って議論して下さいました。

各校で考えたステークホルダー・マッピング。関係している方の名前を付箋に書いて、誰と誰がつながっているのか、ペンでつなげて整理していきます。

各校でまとめたステークホルダー・マッピングを参加者全員で共有。安倍総理や農林水産省などといった声も飛び出しました。
そして、それぞれの学校での議論の後、各校が作ったステークホルダー・マップを発表し、気づかなかったつながりを確認したり、自分たちにどのような影響力があるのかを振り返ったりしました。
二日間にわたるこのワークショップは、参加者である中高生たちが、生きものの保全と農業について理解を深め、自分事としてこの取り組みにどう関われるかを考えるきっかけとなりました。
イベント後の自主的な活動も!!
今回、イベントに参加してくれた中高生たちの姿は、佐賀、福岡、熊本の水田の自然を守る未来への大事な一歩となる期待を感じさせてくれるものでした。
そして嬉しいことに、参加した高校生がイベント後、自主的にいくつもの活動を始めてくださったのです。
福岡の農業高校では、ステークホルダー・マッピングで整理した方々に、直接インタビューを実施。
さらにイベントで学んだことを整理し、学校の保護者や高校職員に活動を知ってもらうための活動報告も行なったそうです。
東京の中学生たちも、自校の文化祭の出し物として、今回のイベントで学んだことを発表。WWFの取り組みを支援する募金活動も展開してくれました。
また、学校内の取組みである研究の課題として、本プロジェクトを取り上げてくださっている生徒さんが、WWFのオフィスに改めて取材に来てくれる一幕もありました。
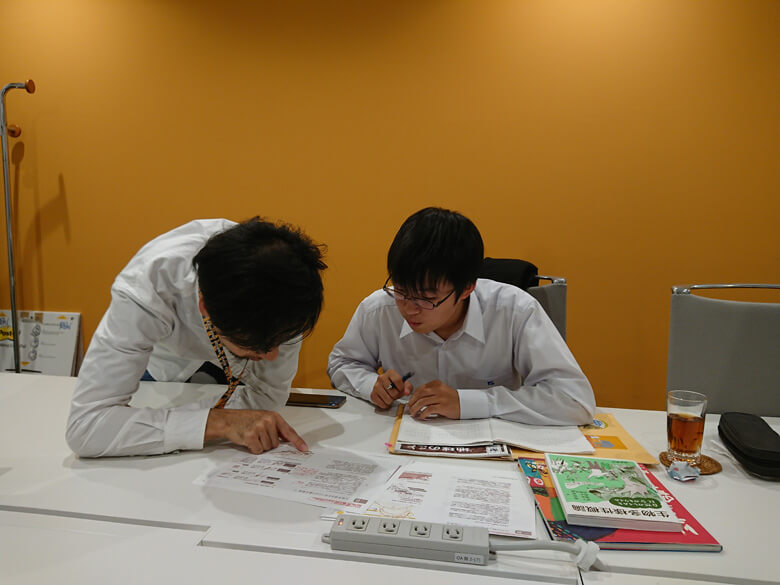
取材に来てくれた海城中学校の生徒さん。するどい質問に担当スタッフが回答に悩むシーンも。

現在展開中のキャンペーンも応援してくださっています。
中学生や高校生の皆さんの若い力は、プロジェクトを推進するうえでも大きな力になります。
WWFジャパンは引き続き、地域の行政や農業者、企業、そして中高生や学校関係者の方々と協力しながら、水田に生きる日本固有の希少な生きものの保全を進めていきます。
イベント概要「WWF水田スタディーツアー」
| 日時 | 2019年8月31日、9月1日 |
|---|---|
| 場所 | 佐賀県立宇宙科学館ゆめぎんが、佐賀市東与賀地域、佐賀県立青年会館 |
| 参加者所属校 | 海城中学高等学校、熊本県立熊本高校ボランティア同好会、福岡県立糸島農業高校、福岡県立八女農業高校、佐賀県立佐賀西高校サイエンス部、私立明星学園(高等学校)、名古屋市立菊里高等学校、国立大学法人九州大学、私立帝京科学大学 |
| 講師 | 国立大学法人佐賀大学 徳田誠准教授、ネイチャー佐賀 増田英治、シギの恩返し米プロジェクト推進協議会 吉村信行 |
※本活動は、公益財団法人JKAの競輪補助事業です。























