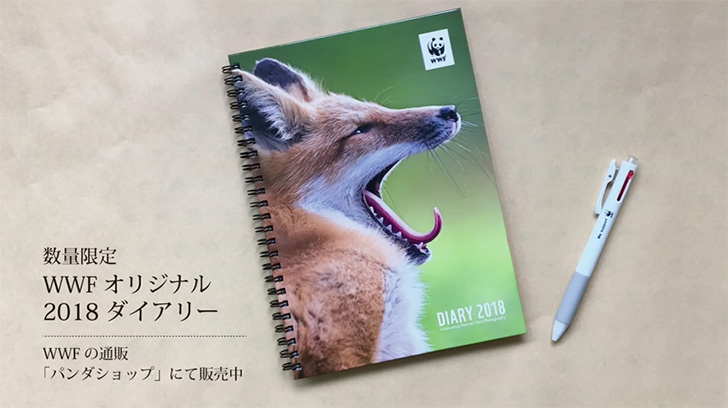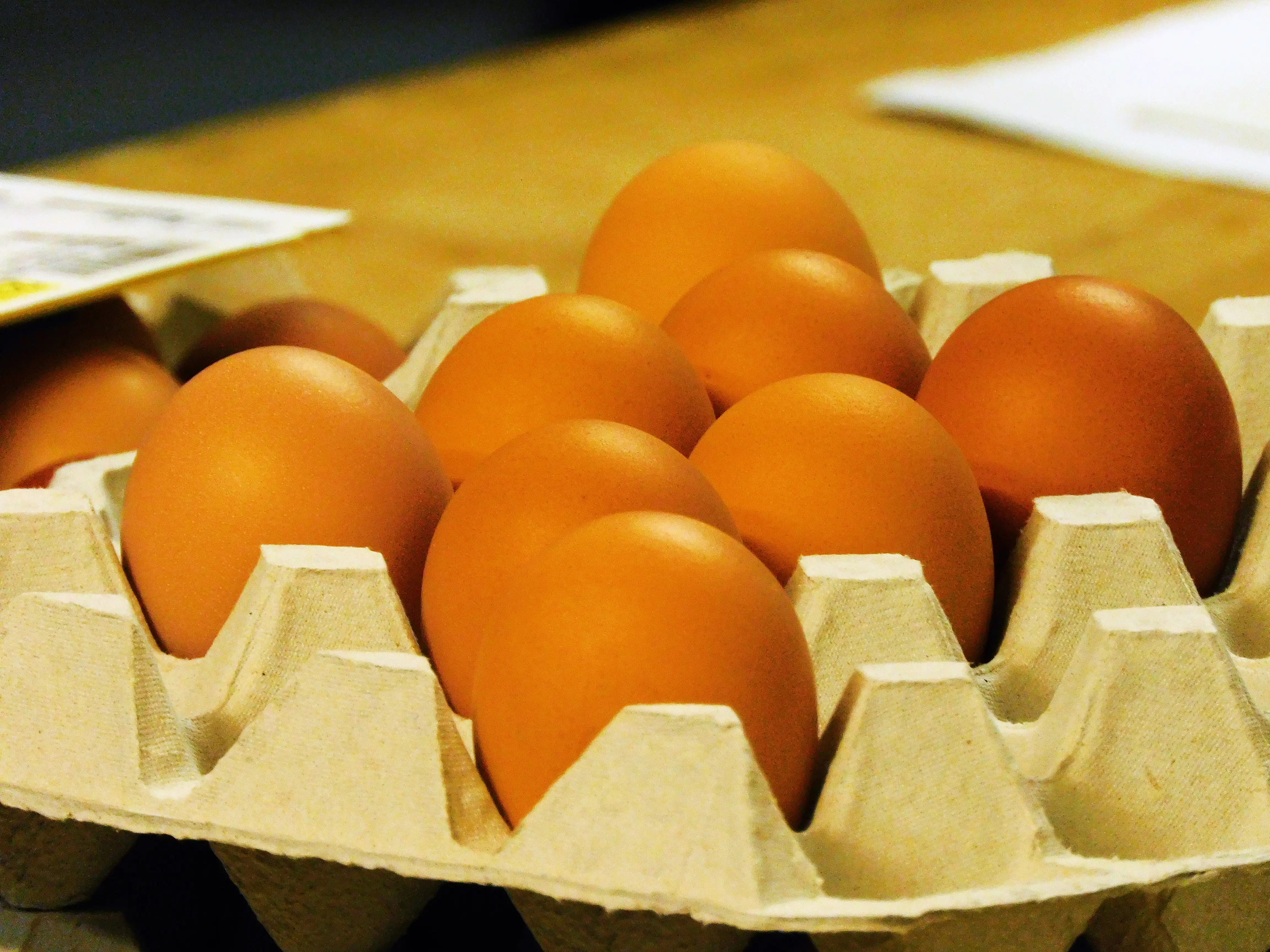野生ヒツジの王様、アルガリの話(動画あり)
2017/12/23
※2023年6月26日をもって、WWFロシア(Vsemirnyi Fond Prirody)はWWFネットワークから離脱しました。
ヒツジ、という言葉に、どんな印象を持たれるでしょうか?
飼ったことのある人は、その結構な臭いや、ビックリするほどの大きな声などを最初に思い浮かべるかもしれませんが、一般には「子羊のような...」という形容もあるとおり、か弱い動物、というイメージが、強いのではないかと思います。
ですが、頭から尾までが2m、肩の高さ1.2m、体重180キロのヒツジとなると、とてもカワイイなどとは言っておられません。
そんなヒツジの調査を行なった、という情報が先日ロシアから届きました。

調査を行なったのは、アルガリの中でも最も大きな亜種のアルタイアルガリ。ねじれた見事な角は、伸ばすと1.5m、一番太い部分の周囲は50cmにもなります。
ヒツジの名はアルガリ。アルタイ山脈を中心に、中央アジアに広く分布する世界最大のヒツジで、もちろん野生の種です。
ロシア国内に拠点を置くWWFアルタイ・サヤン・プログラムでは、このアルガリの調査を長年にわたり手掛けてきました。
ロシアとモンゴル両国の国際協力と、専門家の協力の下、厳しいフィールドでの調査の中で、個体数の推定手法をはじめ、さまざまな調査方法を確立し、精度の高い生息データを測定。

調査地は標高の高い険しい山岳地帯。ここにすむアルガリは、9mもの崖を飛び降りることがあるといいます。
もちろん、数を推定するだけではなく、移動範囲やそのルート、死亡した個体の死因や、密猟の現状なども調べ、保全に役立てます。
今年の結果は、大雪の影響で一部生息地に変化が見られるものの、ロシア側で確認された1,236頭の個体をはじめ深刻な減少は認められず、数は2013年以降安定しているとのこと。
それでも、角や肉を狙った密猟は今も続いており、取り締まり活動は今後も継続がもとめられています。

同じ環境に生きるユキヒョウ。アルガリはその獲物となる重要な草食動物の一種です。アルガリの保全は、ユキヒョウを守ることにもつながります。
世界屈指の広がる大山脈で動物を調べ、守るのは大変な仕事ですが、志を同じくする人たちが国境を越えて協力できるのは、すばらしいことです。
また新しいニュースが届くのを楽しみに待ちたいと思います。(広報担当 三間)

厳しいフィールドでの調査。こうした調査活動の結果もあり、ロシアでは2010年に、WWFの支援でサイルゲムスキー国立公園が設立されました。アルタイのアルガリの80%がここに生息しています。モンゴル側の保護区とも今後つなげられる予定です。
★まるで写真集! 限定販売のWWFオリジナル・ダイアリー2018(パンダショップのサイトへ)