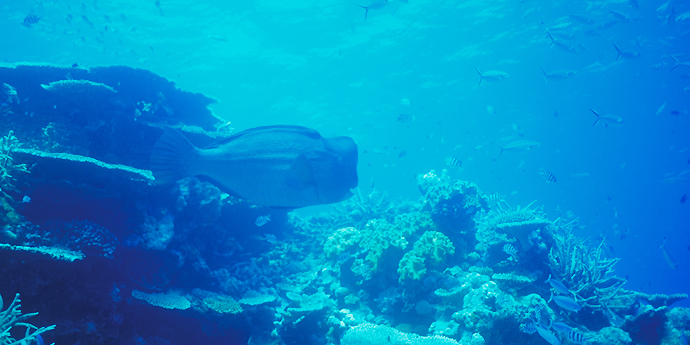二次的な自然にすむ魚たちを守るために
2015/12/18
草刈です。
来週月曜日、環境省が「淡水魚保全のための検討会(第4回)」を開催します。
これは、二次的な自然を主な生息環境とする、日本の淡水魚を保全するための提言をまとめるための会合です。
「二次的な自然」とは、水田や雑木林のような、人の手が入ることで維持されている景観のことです。
こうした自然は通常、人が全く手を付けない原生の自然(一次的な自然)よりも、豊かさが劣っていると思われがちですが、必ずしもそうではありません。
たとえば、木や枝が定期的に伐られている雑木林などは、林床にも光が届くため、さまざまな草花が育ちますし、フクロウのような猛禽も、林の中の開けた場所で狩をします。
これらを「里山生態系」などと呼んだりしますが、いわゆる「身近な動物」たちの多くは、この二次的な自然の住民なのです。


淡水魚も同様で、フナやメダカのような知られた魚は、水田やそこに続く水路、ため池のような場所によく生息しています。
もちろん、周りを全部コンクリートで固めてしまったりすると動物たちも生きられませんから、やはり人の側には、自然と共存するための努力と責任が求められるわけです。
今回行なわれる検討会も、そうした視点に立った取り組みを推進することを、一つの目的としています。
議題となっているのは、「二次的自然を主な生息環境とする純淡水魚保全のための提言」の作成について。
水田などを生息場所の一部としている淡水魚全体を対象とした保全の指針と、必要な取り組みを示そう、というものです。
その対象には、目下「京都スタジアム(仮称)」の建設計画によって危機に瀕している、日本の固有種アユモドキも対象に含まれています。
検討会でどのような提言案が提示されるのか。アユモドキの保全にも、どのような貢献が期待できるのかを含め、注目したいと思います。

水田を含めた二次的な水辺の自然は、国際的な湿地保全のための条約「ラムサール条約」でも、保全すべき重要な湿地(ウェットランド)のタイプの一つとして、規定されており、原生の自然とは異なった豊かさを持っていることが認められています。そうした自然に生きる、ツルやトキ、コウノトリなども、元々は日本人にとって身近な動物です。

アユモドキ。世界と京都と岡山の2か所にしか生息していません