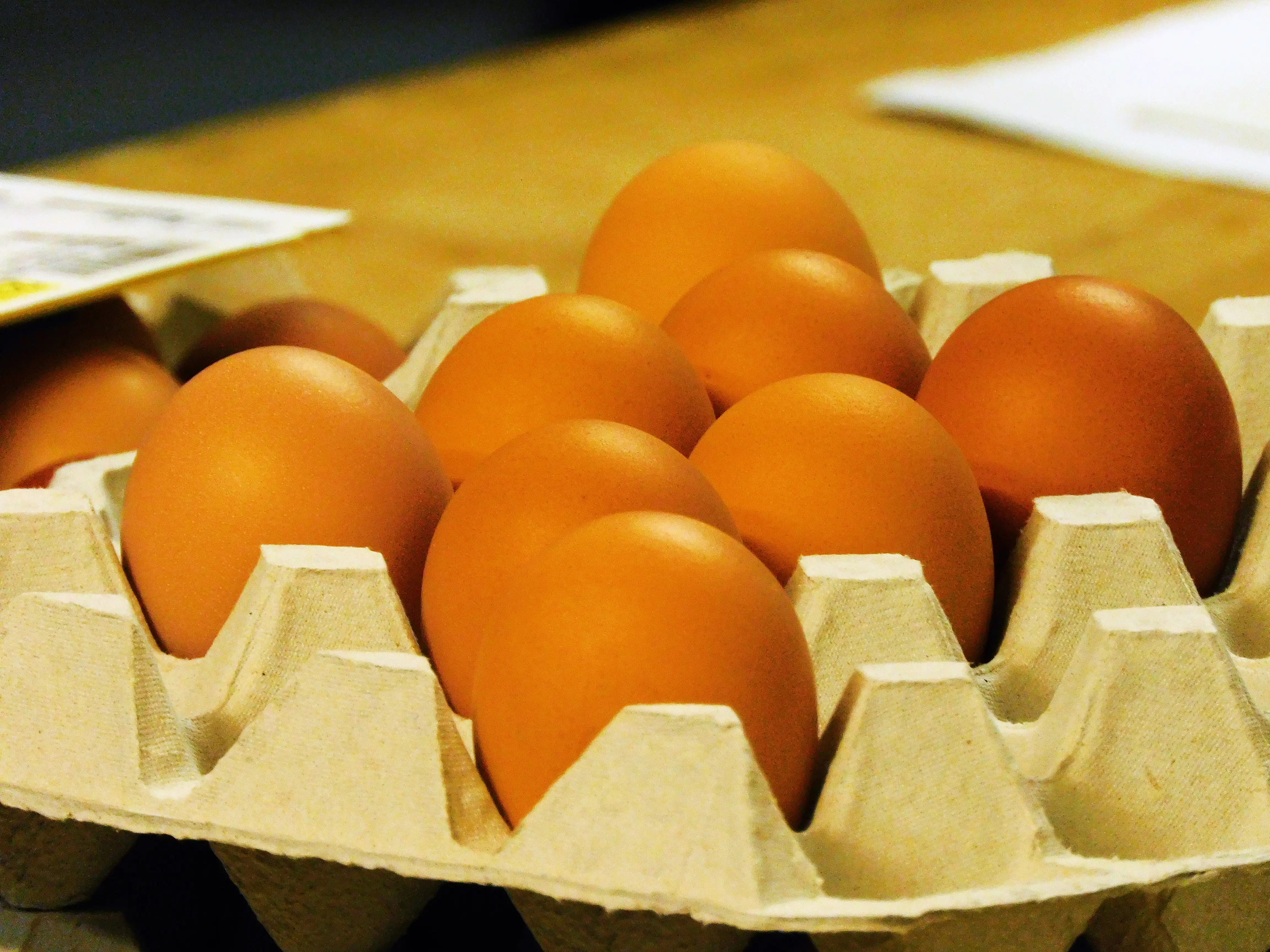中国の沿岸部で広がる「緑の砂漠」
2016/11/21
急速な経済の拡大を続ける中国。
各地では大規模な開発で貴重な自然が失われている、と聞けば、誰でも「そうだろうなあ」と思われるかもしれません。
ですが、そんなありがちな印象の一方で、先日ちょっと驚くような「自然破壊」の話を聞きました。
中国沿岸の干潟や湿地帯で、「緑の砂漠」が広がっている、というのです。
原因は、Spartina alternifloraという北米から持ち込まれたイネ科の植物。

手前の細い草がSpartina alterniflora。奥は在来種のアシ
塩分の多い土にしっかり根を張り、茎が柔らかくて風や波にも強いこの草は最初、堤防などの土を固定するため、人の手で植えらました。
これが在来種のアシなどを駆逐しながら生育地を拡大。
1985年に2.6平方キロだったその面積を、2011年には4,000平方キロまで広げたのです。
このため、アシ原など本来の湿地に生息していた野鳥などの野生動物は、すみかを喪失。
一見緑の、しかし生きものの息吹が絶えてしまった「砂漠」が出現した、というわけです。

アシの間を泳ぎ回るカンムリカイツブリ。つがいかな?と思ったら、親子のようでした。崇明東灘鳥類国家級自然保護区にて
これを教えてくれたのは、長江の河口にある崇明島で、シギやチドリなどの渡り鳥の保全に取り組むWWF中国のスタッフでした。
東アジア屈指の渡り鳥の飛来地、崇明島でも、この外来植物の繁茂は、自然保護の大きな課題。
広さ240平方キロの崇明東灘鳥類国家級自然保護区では、全域の7割以上にはびこっていたこの草を、3年がかりで95%取り除く活動が行なわれている、という大変な話も聞きました。

広大な崇明東灘鳥類国家級自然保護区。地平線まで、見渡す限りアシ原が広がっていました。ここでの外来植物の駆除は、莫大な労力を必要とします
大規模な埋め立てや工場建設などの開発ばかりが、自然を壊すわけではありません。
生態系にここまで大きな影響を及ぼす外来生物。
野外に生物を放つ、という行為が引き起こすこの問題は、日本でも深刻化が指摘されています。
人の身勝手が、どのように自然を変えてしまうのか、忘れないようにしなくてはと思います。(広報担当 三間)

崇明島のフィールドを案内してくれたWWF中国の張亦黙さん(写真右)。ここには年間20万羽以上のシギやチドリなどの渡り鳥が飛来するそうです。