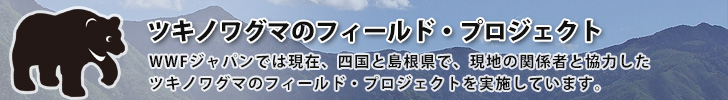日本のクマについて
2009/09/14

日本にはヒグマとツキノワグマという、2種のクマが生息しています。いずれも、国内で最大の陸にすむ野生動物です。しかし、このクマたちはしばしば、人里へ現れて人間と軋轢(あつれき)の問題を起こすことが知られています。野生のクマと、いかに接し、共に生きてゆくのか。これらは国内の自然保護と、日本の社会に根ざした問題でもあります。
日本の森をめぐって
森の中で突然クマに出くわしたらどうしますか?
人間もびっくりするでしょうが、クマはもっとびっくりするでしょう。大きくて強そうなクマですが、本来は慎重で臆病な生きもの。山の奥でひっそりと暮らしています。
一方、近年では数年ごとに、たくさんのクマが人里へ下りてきて問題になっています。そこで暮らす人々との衝突が起きているのです。
クマと人間との軋轢(あつれき)を減らすにはどうすればいいのか?
クマが「森の主」として、日本の森林に住み続けるためにはどうすればいいのか?ご一緒に考えていきましょう。
日本に生息する2種のクマ
世界には8種類のクマがいます。日本国内には北海道に生息するヒグマと、本州以南に生息するツキノワグマの2種類のクマがいます。
環境省の調査によると、北海道の約55%の地域はヒグマが、本州の約45%の地域にはツキノワグマが生息しています。
クマによる被害
人里に降りてきたクマは、農作物や家畜の飼料などを食害します。また、人工林のスギやヒノキの木の皮をはいでしまう被害も出ています。山の中に入っていった人がクマに遭遇、あるいは人里に下りてきたクマが人と遭遇し、人身事故に発展することもあります。
クマの保護管理
クマは昔から狩猟の対象になってきました。過剰な捕獲の結果、生息数が減少した地域もあります。未だに生息数が多い地域、あるいは生息数が回復している地域では、人間との軋轢が問題になっています。
クマの「保護」と「管理」。日本ではどのように行なわれているのでしょう。
クマの大量出没
毎年ある程度の頻度でクマは人里へ出没しますが、著しく出没の多い年があります。特に近年は顕著で、2004・2006年・2010年に起こっています。この大量出没の結果、クマによる農業被害や人身被害が多発し、その防止のため多くのクマが捕獲されました。

ヒグマのくらす北海道知床の森

ツキノワグマ

森深い東北の山。ツキノワグマの主要な生息地の一つ

クマ注意の看板(秋田県)
ツキノワグマの調査
クマとの共存を目指して
日本の山林や中山間地域を取り巻く状況は変化しています。その結果、増えてきたクマと人との衝突。クマとの軋轢(あつれき)は、私たちの社会問題でもあるのです。
人間とクマの距離を適度に保ち、共生していくためにはどうすればいいのでしょうか。
■ツキノワグマのフィールド・プロジェクト
WWFジャパンでは現在、四国と島根県で、現地の関係者と協力したツキノワグマのフィールド・プロジェクトを実施しています。
■シリーズ:クマの保護管理を考える
日本人はクマとどう付き合うべきなのか? このシリーズでは、全国各地の保護管理の最前線を取材し、クマとヒトの未来について考えます。
■クマ関連のスタッフブログ
関連情報
監修
このサイトの制作に際して、日本クマネットワーク/茨城県自然博物館、山崎晃司氏に監修いただきました。
出典・参考資料
このサイトの制作に際して、主な参考にした書籍、資料は以下のとおりです。
- 坪田敏男・山崎晃司編(2011)日本のクマ-ヒグマとツキノワグマの生物学,東京大学出版
- 天野哲也・増田隆一・間野勉編(2006)ヒグマ学入門-自然史・文化・現代社会,北海道大学出版
- 大井徹(2009)ツキノワグマ‐クマと森の生態学,東海大学出版
- 河合雅雄・林良博編著(2009)動物たちの反乱-増えすぎるシカ、人里へ出るクマ,PHPサイエンス・ワールド新書
- 環境省(2010)特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)
- 環境省(2007)クマ類出没対応マニュアル
- 独立行政法人森林総合研究所(2010)ツキノワグマ出没予測マニュアル
- 独立行政法人森林総合研究所(2010)ツキノワグマ大量出没の原因を探り、出没を予測する
- 日本クマネットワーク(2011)人身事故情報のとりまとめに関する報告書
- 日本クマネットワーク(2010)クマの保全と生物多様性
- 間野勉・大井徹・横山真弓・高柳敦(2008)日本におけるクマ類の個体群管理の状況と課題,哺乳類科学
- 小池伸介・正木隆(2008)本州以南の食肉目3種による木本果実利用の文献調査,日本森林学会誌
- 坂庭浩之・姉崎智子・田中義朗・黒川奈都子(2009)群馬県内で錯誤捕獲されたツキノワグマ、ニホンカモシカの解剖所見について,群馬県立自然史博物館研究報告
- 竹内正彦(2004)食肉目研究における法的手続き,哺乳類科学
- Fumi Kitamura and Naoki Ohnishi (2011) Characteristics of Asian black bears stripping bark from coniferous trees, Acta Theriologica
- 環境省発表資料・統計
- 農林水産省発表資料・統計
- 林野庁発表資料・統計