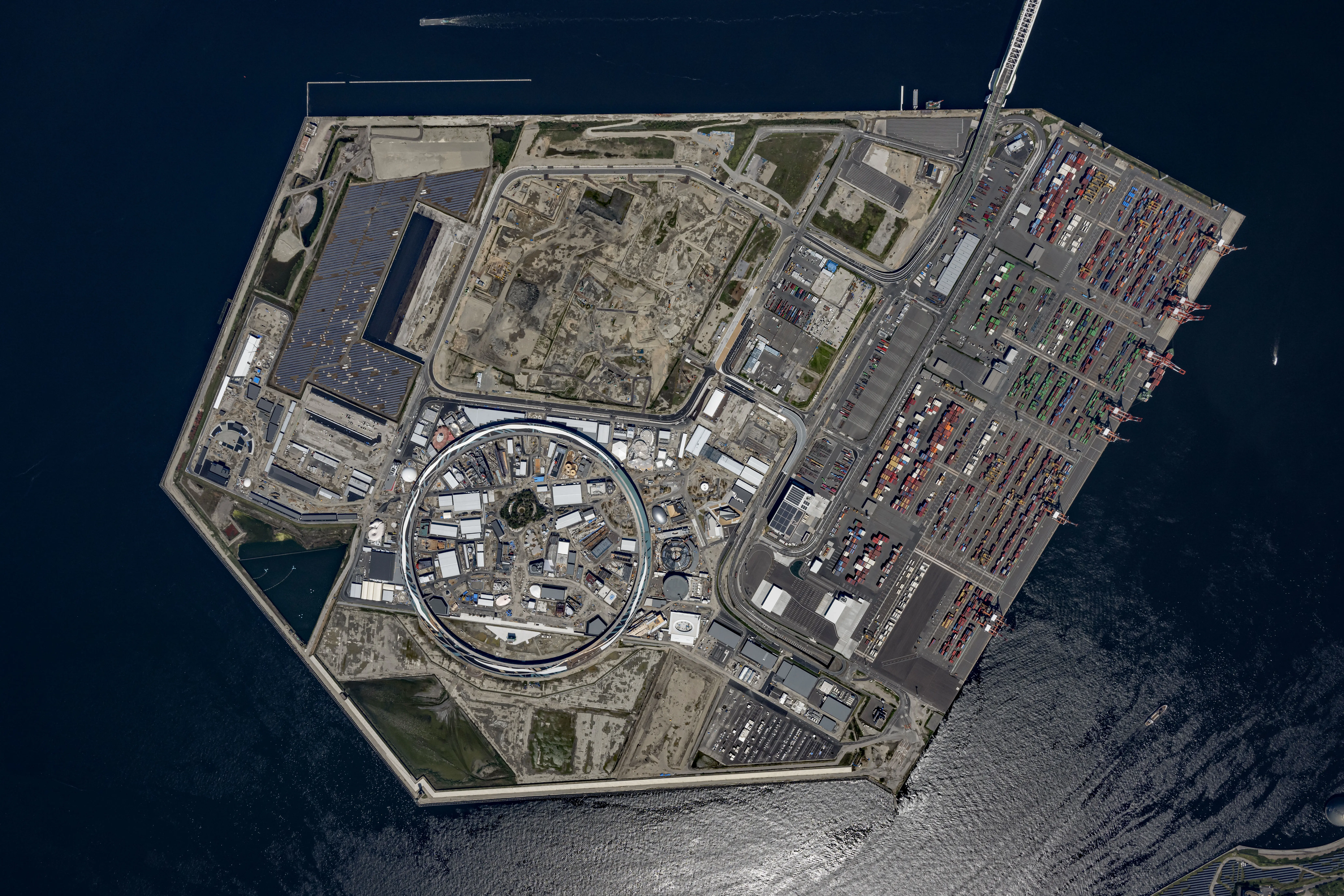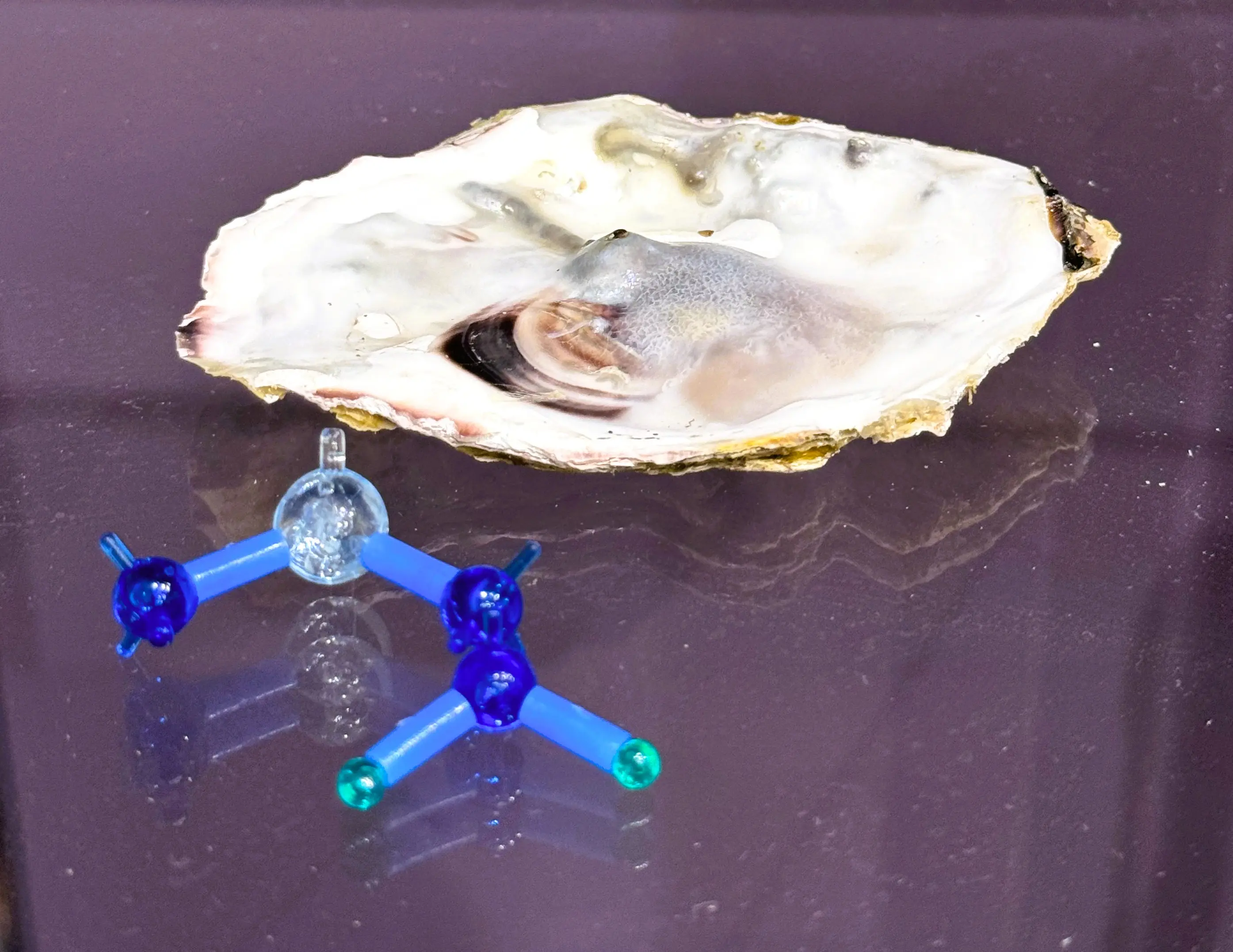「エネルギー・環境に関する選択肢」に対するパブリックコメント
2012/08/11
原発比率だけに着目すればゼロシナリオ。しかし、3つの選択肢全て気候変動対策の観点からは不充分。省エネ対策の強化、自然エネの普及強化、化石燃料構成の低炭素化を更に進めて、気候変動目標を引き上げるべき。
1:気候変動に関する温室効果ガス排出量削減目標について
最低限15%削減を維持し、可能な限り25%維持
3つの選択肢の2020年温室効果ガス排出量目標の幅は、1990年比7〜11%削減であり、吸収源やオフセットを考慮したとしても、現行の目標(1990年比25%削減)から大幅に下がることになる。以下で述べる省エネルギー対策の強化、自然エネルギー水準の強化、化石燃料構成比の改善をそれぞれ実施することで、温暖化対策の目標を維持することは可能なはずであり、少なくとも、真水での15%以上削減は維持し、可能な限り既存の25%削減目標を維持する選択肢を提示するべきである。
国際的に「野心の水準の引き上げ」が議論されている流れを踏まえるべき
国連気候変動交渉では、先のドイツ・ボンの会議において、今後、各国の温室効果ガス排出量削減に関する「野心の水準の引き上げ」について議論していくことが合意された。世界全体で野心の水準を引き上げていくためには、日本のようにこれまでの温暖化に責任を持つ国が、率先して目標の引き上げに貢献していくことが本来必要である。そのような状況下で、日本が目標を大幅に引き下げることが、他国の動向に対して与える負の影響は看過されるべきではない。日本は、ただでさえ、京都議定書の第2約束期間参加の拒否や、途上国支援のための長期資金に関する消極的姿勢によって、途上国が積極的になる要因を殺いでいる。この上に、さらに目標を大幅に引き下げるということになれば、2015年へ向けた将来枠組み交渉の中で、日本の影響力の更なる低下は避けられない。
2:省エネルギー
最終エネルギー消費で30%程度の削減(2010年比)を想定する選択肢を
政政府選択肢では、省エネルギーの水準について、複数のケースから選択できるようになっていない。現状の選択肢で想定されている省エネルギー対策よりも、さらに深堀をするような選択肢があるべきである。具体的には、最終エネルギー消費の、30%程度の削減を想定する選択肢が存在するべきである。
政府選択肢では、発電電力量に関する省エネが2010年比10%削減で固定され、他のエネルギーも含んだ最終エネルギー消費量の削減比率についても、原発ゼロシナリオの追加対策後以外はほぼ横並びの約20%減となっている。
また、議論が電力に過度に集中し過ぎている。東日本大震災および原発事故を受けて、議論の焦点が電力や原発比率に当たることは、ある程度はやむを得ない。しかし、省エネルギーは本来、電力だけでなく、熱や燃料も含めたエネルギー全体についての議論である。日本全体のエネルギー構造を見た時、一次エネルギー供給に占める電力の割合は約44%、最終エネルギー消費に占める割合は約24%である(2010年実績)。コジェネレーションの活用に典型的に見られるように、違うエネルギー(電気と熱)を組み合わせることで効率がアップするケースもある。電力への過剰な議論の集中によって、一般市民がこの選択肢を見た時に、省エネルギーの可能性についても不当に低い評価を下しかねない。
特に産業部門と業務部門での省エネルギー対策想定の強化が必要
以下の図 1と図 2は、今回の政府選択肢それぞれにおける部門毎の省エネルギー比率とWWFジャパンが発表した「脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案」の比率を比較したものである(2020年時点、2030年時点)。
図 1:2020年の省エネルギー比較
(出所)政府選択肢については、国家戦略室(2012年)「シナリオ詳細データ」より作成。
図 2:2030年の省エネルギー比較
出所)政府選択肢については、国家戦略室(2012年)「シナリオ詳細データ」より作成。
これらの図が示すように、2030年断面でみた場合、WWFジャパンのシナリオと政府の諸シナリオとでは、産業部門についての差が一番大きく、ついで業務部門の差が大きい。ただし、業務部門については、環境省のシナリオを除いた他の政府シナリオとWWFのシナリオを比べると、その差は産業部門よりも大きくなる。
産業部門については、より大きな省エネルギーを想定するべき
産業部門については、政府シナリオの通りであるとすれば、2020年時点では現状(震災前)のエネルギー消費水準そのままということを意味する。産業部門での差は、端的に言えば、素材系業種における省エネ改善努力の想定が低いことに起因する。
産業部門について、さらに詳しく見てみる。表 1は、WWFジャパンと政府シナリオについて、産業部門の中での業種ごとの省エネルギー想定の差を示したものである。ここでは、「選択肢」そのものの業種別データがないため、選択肢の背景として経産省・基本問題委員会で行われた計算の数字とWWFシナリオとの比較をした。ここでの計算は、政府公表データが限られているため、あくまで暫定的なものである。しかし、そうであるにしても、WWFシナリオとの差は大きい。
- ※1)素材系4業種については環境省も想定は同じである。
- ※2)政府が公表している数字では、省エネ量は公表されているが、業種ごと(例:鉄鋼、窯業土石...)の基準年(2010年)でのエネルギー消費量は公開されていない。これが、公式統計(総合エネルギー統計)の業種ごと数字そのままと同じであるのか、それとも、独自の計算が業種ごとにされているかの区別もない。WWFはエネルギー経済研究所の『エネルギー・経済統計要覧』の区分を使用しているため、ここで示した結果は、概ね合っているとはいえるが、厳密かどうかの確認はできない。
WWFシナリオでは、(現在から約40年後の)2050年までに、多くの素材系業種において効率が30%改善することを想定している。約40年間での効率改善30%(年平均で約0.75%)決して極端な数字ではない。これによって、2030年時点でのエネルギー消費量は、2010年と比較して、概ね2〜3割減ることが想定されている。
これに対し、政府の想定では、2030年までのエネルギー消費量はいずれの業種でも1割程度の減少しか見込んでいない。これでは明らかに不充分である。
| 2030年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 原油換算万kl |
省エネ量 原油換算万kl |
エネ消費量削減率 2010年比 |
|||
| 実績 | 基本問題 委員会 | WWF | 基本問題 委員会 | WWF | |
|
鉄鋼 |
4,212 |
336 |
1,489 |
-8% |
-35% |
|
窯業土石 |
976 |
67 |
340 |
-7% |
-35% |
|
パルプ・紙 |
814 |
58 |
45 |
-7% |
-6% |
|
化学工業 |
5,455 |
95 |
1,294 |
-2% |
-24% |
|
その他全ての産業(転換以外) |
5,488 |
824 |
998 |
-15% |
-18% |
(出所)基本問題委員会の想定については:三菱総合研究所(2012)「省エネルギー対策に関するテクニカルレポート」(経済産業省・基本問題委員会第22回会合資料 2012年5月14日)
業務部門は、せめて環境省の高位ケースの省エネを想定するべき
業務部門については、WWFシナリオと政府選択肢との差は大きいが、環境省の「高位」対策ケースでの省エネ水準とはそれほど大きな差はない。したがって、最低でも環境省シナリオで想定されている水準まで、省エネルギーを強化することが必要である。
つまり、産業・業務での省エネルギー対策強化を徹底すれば、たとえWWFシナリオと同水準とならなくても、最終エネルギー消費で3割程度の削減を達成することは十分可能である。さらに、これらの部門以外でも省エネのポテンシャルは大きくある。たとえば、発電過程そのものでの効率の改善(エネルギー転換部門)も、本来であれば深堀が可能なはずである。
3:再生可能エネルギー比率について
再生可能エネルギー電力比率を50~60%まで引き上げる選択肢を
いずれの選択肢シナリオにおいても、再生可能エネルギーの比率が25~35%に留まっており不十分である。50~60%まで比率を高める選択肢も設けるべきである。
そもそも、日本の再生可能エネルギーが現状9%程度(大水力を除くと1%)に留まっているのは、各地域の電力会社が送配電網を分割・独占していることが大きく影響している。ドイツやスペインのように、一つの送配電網として連系することができれば、再生可能エネルギーを大きく普及させられることが実証済みである。
日本においても、全国で需給バランスをとれる系統の広域運用を可能とする電力システム改革を行い、地域間連系線や地域内送電網の強化を速やかに進め、再生可能エネルギーの優先給電を徹底することによって、早期に25~35%まで再生可能エネルギーを導入していくことが可能となる。
さらに透明性と公平性を確保した系統運用が可能となるように、所有権分離の発送電分離を旨とした改革を強力に進めていくことによって再生可能エネルギーの比率を25~35%よりさらに高めることも十分可能である。したがって、選択肢においては、原発の比率の低下とともに化石燃料の比率を高めるのではなく、電力システムの改革を前提とした、より高い再生可能エネルギー電力比率を選べるようにすべきである。
WWFジャパンのエネルギーシナリオ(※)では、2050年までに日本のエネルギー需要(電力に加え燃料・熱利用も含む)を100%再生可能エネルギーで賄うことが可能であることを示している。
発電電力に占める再生可能エネルギーの割合も、2010年の約10%から2030年には63%まで高めることが可能である。その大前提となっているのが、意欲的な省エネの推進である。本シナリオでは、現時点で想定できる省エネ技術を積み上げていくことにより、2030年時点で最終エネルギー消費を34%削減できることを示している。
このように、エネルギー使用の無駄を無くし、消費エネルギーの総量(分母)を減らせば、再生可能エネルギーの数値割合も自ずと高まる。対して、今回提示された選択肢シナリオでは、いずれも省エネ部分の検討が不十分であるがゆえに、再生可能エネルギーの数値割合も相対的に低くなっているといわざるを得ない。
電力以外の再生可能エネルギーにも重点を
また、選択肢では電力に大きな焦点が置かれ、それ以外のエネルギー利用についての議論が不十分であるが、割合として大きい燃料・熱需要を満たす上でも、再生可能エネルギーは重要な役割を担うことが可能である。運輸や産業部門をはじめ、家庭や業務などあらゆる部門において、太陽熱や地中熱、バイオマスの熱利用などを積極的に活用していくことを選択できるようにすべきである。WWFのエネルギーシナリオでは、2030年時点で燃料・熱需要の40%を再生可能エネルギーでまかなえることを示している。
15シナリオ、20~25シナリオにも追加対策後オプションを
ゼロシナリオについてのみ、「追加対策後」として温暖化対策を強化するオプションとしているが、15シナリオおよび20~25シナリオに関しても、同様のオプションを設けるべきである。また、強化オプションでは、再生可能エネルギーの割合を5ポイント、省エネ(最終エネルギー消費)の割合を3ポイント高めるに留まっているが、いずれも数十ポイント高めるオプションも示すべきである(表 2)。
表2:政府選択肢とWWFシナリオの比較
4:CO2排出量の多い石炭火力発電から天然ガス火力発電へシフトするべき
いずれは化石燃料から脱却すべきであるが、2020年、2030年などの過渡期の温暖化対策としては、火力発電の化石燃料の比率で、石炭から天然ガスへのシフトを速やかに進展させていくことが不可欠である。ところが、提示された選択肢では、省エネ度が選べないばかりか、化石燃料比率も選べず、温暖化対策の選択肢といえるものではない。中環審の示した選択肢において、省エネや天然ガスシフトの進展による「温暖化対策高位ケース」や「中位ケース」があったことを踏まえると、どの選択肢においても、温暖化対策の強化が可能であることがわかる。
中期的な温暖化対策は、化石燃料の中でもCO2排出量の多い石炭火力から、より少ない天然ガス火力へとシフトすることを進展させることが重要
同じ化石燃料の中でも、石炭火力、石油火力、天然ガス火力の順にCO2排出量が多く、天然ガス火力は平均して約4割、石炭火力発電よりもCO2排出量が少ない。新技術によって石炭火力からのCO2排出量は少なくなっていくことが見込まれるが、LNG(液化天然ガス)火力には及ばない(図 3)。温暖化対策が待ったなしに急務であることを考えると、日本における2020年、2030年の火力発電構成は、LNG火力へのシフトを最大限に進めるべきである。
図 3:火力燃料別のCO2排出量(kgCO2/kWh)
(出所)国立環境研究所AIMプロジェクトチーム, 2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会における議論を踏まえたエネルギー消費量の見通しの仮試算(その6)p67(2012/5/28)
温暖化対策と逆行する石炭を重視した選択肢となっている
今回の選択肢では、中環審が天然ガス火力シフトを鮮明にしているのに対し、総合エネ調の化石燃料比率は、コストの低い石炭火力重視であった。総合エネ調から出された選択肢案と、中環審から出された選択肢案を比べると(表 3)、原発15%ケースでは、それぞれ約50%を占める火力の内訳は、総合エネ調では石炭:LNGの比率が2:1に対し、中環審(高位ケース)では石炭:LNGの比率は1:2と大きな開きがある。
結果としてエネルギー・環境会議から示された選択肢においては、化石燃料比率については、中環審と総合エネ調の中間をとっただけとなった。つまり、原発比率のみを選べる3つの選択肢において、化石燃料比率を選べる選択肢は示されなかった。
これでは省エネや再エネの普及で温暖化対策を行うとしても、石炭火力発電が温存されることで、効果が相殺されてしまう。
表 3:2030年各シナリオにおける火力発電の燃料別構成
石炭には適切な環境コストが課されるのが当然
そもそもこれまでの日本の温暖化対策の失敗は、原発大幅増設と設備利用率の向上に頼るあまり、省エネや燃料転換、再生可能エネルギー普及策の十分な導入を怠ってきたことにある。エネルギー安全保障の名の下に石炭利用が拡大されてきたが、内実は石炭価格の低下が招いた石炭火力発電所新増設ラッシュであった。
日本のCO2排出量増加(1990年から2007年)が、石炭火力発電所増加分によるCO2排出量増加とほぼ同じであったことからも、石炭火力重視が日本の温暖化対策を妨げてきたことが明らかである。また原発計画が事故や地元の反対などで予定通り進まず、さらなる石炭火力発電所の利用増加につながってしまった。今後は決して同じ轍を踏むべきではなく、石炭火力を急速に計画的に縮小させていかなければならない。
石炭には環境負荷の高さがコストとしてかかるべきであり、炭素への価格付け政策が導入され、適切な価格帯で制御されれば、石炭のコスト優位性というのは本来ないはずである。したがって今後も石炭にコスト優位性があることを前提とした火力燃料構成の設定はありえない。したがって、どの選択肢においても、化石燃料比率でもっとLNG火力を増加させてしかるべきである。
どの選択肢において、温暖化対策については深堀りするべき
今回の選択肢においては原発比率は選べるが、上記のように温暖化対策を選ぶ選択肢はない。したがってどの選択肢においても、さらなる温暖化対策が可能であることはWWFシナリオとの比較においても示すとおりである。
5:原子力発電所について
着実な原発廃止方針の策定が必要
東京電力福島第一原発事故の経験を踏まえ、日本は、原子力発電所への依存を断ち切っていかなければならない。同事故が明らかにした原子力発電所が持つ安全性リスク、そしてそれに対処するための政府・企業のガバナンスと対応能力の欠如、核廃棄物の最終的な処分方法の未解決など、以前から指摘されてきた問題も含めて、様々な問題が再度浮き彫りとなった。
原則として、以下のような方針をとるべきである。
再稼働は5条件を満たした後のみに
まず、再稼働については、以下の5条件が達成された場合のみ再稼働が行われるものとする(詳細は下記「WWFジャパンの原発再稼働5条件」参照)。
- 信頼できる原発規制新体制の確立
- 事故原因を踏まえた新安全基準の適用
- 原発事故防災体制と危機管理の抜本的な見直し
- 被害想定範囲に応じた地方自治体との安全協定と地域社会の再稼働への同意
- 中長期的な脱原発依存の実現の工程表の提示
原発は着実に廃炉していくプランを立てる
次に、以下を最低限のラインとして、早期の廃止を目指していくことにする。
- 新規の原子力発電所は、(着工中のものも含めて)建設しない。
- 既存の発電所については運転開始から30年経ったものから順次運転停止し、廃炉にしていく。
- ただし、既存の発電所のうち、安全性のリスクが高いと考えられるもの(地震・津波のリスクや福島第一と同じ格納容器形式など)については、2012年の時点で停止し、廃炉工程を開始する。
- また、立地地域および周辺地域の住民から反対の意志が表明されているものについても、早期に停止・廃炉にしていく。
- さらに、今後、省エネルギーや自然エネルギーの普及スピードが早くなる場合は、停止・廃炉時期を早める。
特に、上記の省エネルギー促進、自然エネルギーの普及、そして化石燃料構成比のシフトを早期に達成できれば、より早期のフェイズアウト(2030年までにゼロシナリオ)も十分に可能であり、望ましい。
早期に運転停止・廃炉するべき原発としては、WWFジャパンのエネルギー・シナリオでは、福島原発と同型のものや地震のリスクなどの評価に基づいて下記を挙げている。
女川:1号、福島第一:全基、福島第二:全基、浜岡:全基
東海第二、島根:1号、伊方:全基、敦賀:1号
その後に、より包括的な検討の基に発表されたものとして、原発ゼロの会が発表した「危険度ランキング」等も参照するべきである。
【参考情報】WWFジャパンの原発再稼働5条件
1. 信頼できる原発規制新体制の確立
- エネルギー供給と安全対策を明確に分けた体制:原子力規制庁が設置されていること
- 独立した権限:新しい規制組織は、安全を確保するための諸規制の制定において独立した権限を持つこと。また、電力会社や原子力事業などの利害関係者から離れた中立的な立場の体制を整えること
- 放射性物質を適用対象とするよう環境基本法および関連法の改正を至急すすめること
2. 事故原因を踏まえた新安全基準の適用
- 政府事故調・国会事故調・民間事故調の調査結果をもとに、事故の根本原因(津波想定、想定地震動、組織的な不作為等)に基づいた新しい安全基準を再検討すること
- 新しい安全基準については、国際的な組織を含む中立な立場からの評価を十分に受けること
- その新しい安全基準をすべての原発に再適用し、津波対策などの措置が完了していること。また、その基準適用自体が、中立的な立場から検証されること
- 自然は想定できない事態が起こりうることを理解し、予防原則を最優先に考えること
3. 原発事故防災体制と危機管理の抜本的な見直し
- 事故時の放射能拡散シミュレーション等、被害予測を全原発地点で公開し、迅速かつ的確に対応できる防災計画・危機管理体制が構築されていること
- 現実的な事故対応の準備と防災訓練の実施計画があること
4. 被害想定範囲に応じた地方自治体との安全協定と地域社会の再稼働への同意
- 放射能拡散シミュレーション等の被害予測に応じた範囲に含まれる地方自治体と、原子力安全協定を締結すること
- 原子力政策の基本である公開の原則に則り、客観的な情報が提示された上で、当該範囲に含まれる自治体住民の中で、熟議がされていること
5. 中長期的な脱原発依存の実現の工程表の提示
- 旧型や老朽化した原発、地震や津波などの危険性の高い地域の原発を早期に運転停止し、廃炉にしていく計画や、その他の原発の運転終了までの期間などの計画を示し、政府の主張する「脱原発依存」の工程が具体的に示されること
- 使用済み核燃料の現実的な長期管理方策が提示されること
6:経済的影響について
経済的影響を過度に強調するべきではない
経経済的影響に関する諸試算の解釈は、脱原発や温暖化対策の強化によって、GDPの成長速度は下がるが、大きな影響はない、という結論となる筈である。
2030年自然体ケースでのGDPと比較した際の差は、ゼロシナリオで-1.3~-7.4%、15シナリオで-0.3%~-4.9%、20~25シナリオで-0.3%~-4.6%となっている。しかし、いずれのケースでも、2010年と比較すれば、GDPは10%以上の成長を達成しており、マイナス成長に陥ることはない。
また、家庭への負担については、一ヶ月当たりの電気代の増加分が示されている。それらを概観すると、ゼロシナリオでは月4000円~1万1千円、15シナリオでは4000円~8000円、20~25シナリオでは2000円~8000円の幅での電気代増加が試算されている。
しかし、使われている各モデルそれぞれでの幅に着目して見ると、国立環境研究所のモデルでは全て4000円、大阪大学伴教授のモデルでは2000~5000円(3000円の幅)、慶應大学・野村准教授のモデルでは8000円~1万1千円(3000円の幅)、RITEモデルでは8000円~1万円(2000円の幅)と、シナリオ間の幅はあまり大きくない。
これら3つのシナリオ間には、原発比率に大きな差があり、かつ再生可能エネルギーについても差があるにもかかわらず、大きな差が出ていないということを踏まえると、電気料金の上昇の多くは、化石燃料費用の増加によってもたらされることが分かる。
このような内情を踏まえ、経済的影響を過度に強調するべきではない。
7:国民的議論の実施のあり方について
本パブリックコメントも含め、「エネルギー・環境に関する選択肢」については、「国民的議論」がなされることになっていた。しかし、これまでの実施状況を見ると、とても「国民的」とは呼べず、極めて限定的な議論にとどまってしまっており、改善が必要である。
以下では、国民的議論として実施されている3つの事項それぞれの問題を挙げる。
パブリックコメント:告知の期間・内容ともに乏しい;結果発表には工夫を
まず、パブコメという制度自体の一般市民の中での知名度が高くない状況でやるにしては、期間が短かった。当初、本パブリックコメントの募集が開始された時には、その締切は7月末であった。
「春」と以前から発表していた「選択肢」の提示が6月末にずれ込んだにもかかわらず、国民的議論の締切はそのままで実施するという姿勢は、国民的議論の軽視、ひいては国民の意見の軽視ととられても仕方がない。開始後、締切が8月12日まで延期され、少しだけ状況は改善されたが、夏休み等の時期と重なっており、実質的な延期期間はそれほど長くない。
また、パブリックコメントを実施していることの広報努力が不充分であり、「国民的」と呼べる程、多くの人には知られていないし、その努力が見られない。新聞・テレビ・ラジオ等のマスメディアへの案内協力の要請や政府自身による広報などによって、「選択肢」議論そのものの存在とパブリックコメントを含めた意見募集の存在を知らせる努力がより一層必要であった。
パブコメの結果の公表については、透明性を確保するため、提出されたパブリックコメント自体を公開するべきである。
また、何らかの集計を行う際には、3つの選択肢以外を選択したコメントについては、内容に応じて独自の分類を行うべきである。たとえば、本意見のように気候変動対策の重要性を強調しているものと、経済成長のみを重視しているものを、同じ「その他」などの形で分類することは絶対に避けなければならない。
意見聴取会:募集方法・実施方法に問題があった
全全国11カ所で行なわれた意見聴取会については、いくつか実施上の問題が起きた。
1つ目は、開催案内発表から締切までの期間の短さである。開催案内発表から最初の聴衆会(さいたま市で開催)の申込締切までは、1週間に満たなかった。民間や市民団体の努力によって、それでも多くの人は申し込んだようだが、人々に知ってもらうという意志が見えない。
2つ目は、意見表明者の「枠」の配分が、シナリオの支持者の数を反映していない点である。これまでに開催された聴衆会では、ゼロシナリオでの意見表明者の数が多く、15シナリオ、20~25シナリオの意見表明者の数はそれに比べて少なかったという。少数意見であっても、意見を述べる権利が確保されることは大事ではあるが、圧倒的な差があるにもかかわらず、9人の枠を3等分するのでは、意見表明者のバランスが会場の「世論」を反映しない。特に、後述するように、今回の意見聴取会では会場参加者は意見を述べることができないという点を考えると、意見聴取会での意見のバランス全体が誤った形で代表されることになる。最初の3回の会への批判を受けて、枠を12名に増やし、枠の割り当ての改善がされたようである。この改善が適切に行われることと、以下の4つ目の問題で述べるように、会場参加者の意見表明の時間を作るなどの改善が必要であった。
3つ目は、地域外からの意見表明者が複数名選ばれた事例があったことである。わざわざ全国11ヶ所で聴衆会を開催する理由としては、各地域での意見を聞くことがまず理由として考えられる。しかし、たとえば、仙台で開催された聴衆会では、9名のうち2名が東京からで、1名が神奈川からの参加者であったという。しかも、ゼロシナリオを支持したのはいずれも宮城県の人で、地域外の人々は、15シナリオ、20~25シナリオを支持し、それに電力関係者が加わっていたという。ゼロシナリオを望んだ人が多かった地元の人たちは、倍率が高いから意見を出せず、倍率が低いから関東圏の人が15シナリオや20~25シナリオについて発言を出来るというのは歪な構造である。会場の通常参加はともかく、意見表明参加者については、せめて当該地域内に在住者もしくは職場を持つものに限るべきではないか。でなければ、何のために全国11ヶ所で開催するのかが分からない。
4つ目は、各意見聴取会で、会場参加者からの意見を聞く機会がなかったことである。9~12名の意見表明者は、それぞれ時間にして10分を割り当てられ、発言ができた。これで合計1時間半~2時間である。聴衆会の開催時間は2時間~2時間半だったので、前後の政府の説明を合わせると、それでほぼおしまいである。せっかく参加した会場参加者は、アンケートに意見を記入することができるのみである。これでは100~200名の人々に参加してもらう意味が半減してしまう。より時間を長くとり、会場からの意見・質問を複数とったり、会場での挙手によるアンケートをとってみたりするなど、会場参加者に何らかの意見表明の場を与えることが必要であった。
討論型世論調査の実施:限定的な実施に留まった
今回、新たな試みとして、討論型世論調査(DP)というものが実施された。この実施については、これを検討している研究者自身から既に短期間での実施について、準備ができないとの懸念が表明されている。また開催地域も限定されるため、極めて限定的な形での結果しか得られないと予想できる。こうした新しい方法を試すこと自体は歓迎されるべきだが、規模・準備期間ともに不充分である。
さらに、通常型の世論調査については、少なくとも現在はマスメディアによる世論調査に頼り切るという姿勢が打ち出されている。マスメディアが独自に行うことは重要ではあるが、それに加えて、政府主導でも行うべきではなかったか。
以上、繰り返しになるが、今回の「国民的議論」はその名には値しない状況となっている。今回の意思決定において、「国民的」議論を本当に行うのであれば、
- 期間は最低3ヶ月以上予定しておおまかなスケジュールを示す
- 政府広報および民間マスメディアにも力を入れてより多くの人々にこの議論の存在自体を知ってもらう努力をする。ドイツのように公共放送が10数時間連続で有識者を交えての国民議論を喚起するなど
- 各地での意見交換会も複数回開催して、議論の成熟をはかる
というような取組みがあってもよかったのではないかと考える。特に、今回のエネルギー・環境の選択肢についての議論は、国民の中でも意見の隔たりが大きい問題であり、多くの国民が論点を認識し、その決定のオーナーシップを認識するためには、十分な期間の確保が必要である。