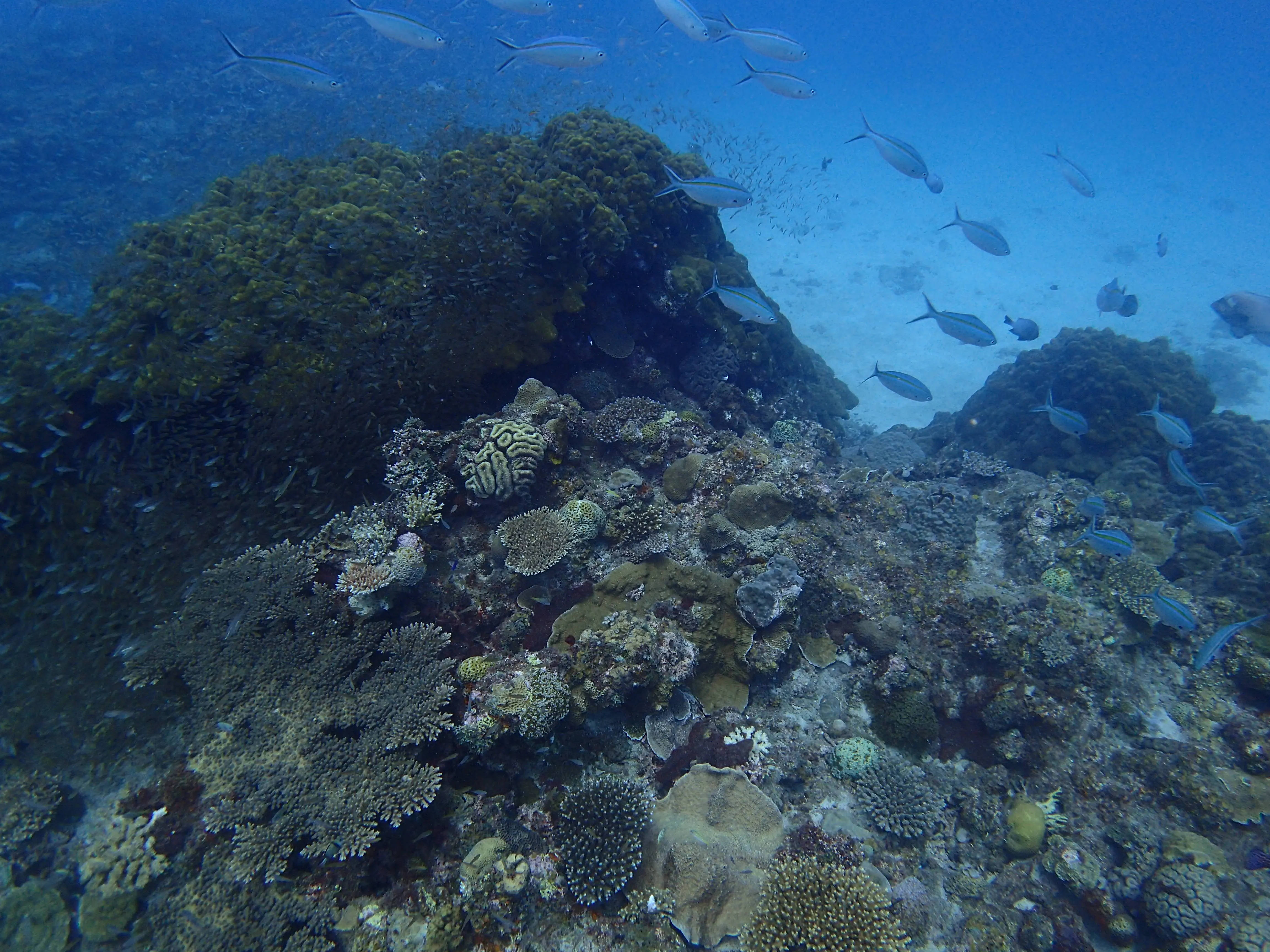【動画あり】旧稲葉集落で進む水辺再生~西表島浦内川での活動レポート
2024/01/12
- この記事のポイント
- 世界的に貴重な自然が今も残る、日本の南西諸島。ここでは、危機に瀕する陸水域の環境と、そこに生息・生育する希少な野生動植物を回復する活動が、重要となっています。WWFジャパンは、かつてイリオモテヤマネコが身近に見られた沖縄県の西表島・浦内川流域の旧稲葉集落で、地域の皆さんや研究者等と連携した水辺再生の取り組みを進めています。この活動の進捗についてレポートします。
試験池に戻ってきた生物の調査
WWFジャパンは現在、環境省の「西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務」を受託し、地域の方々と協力しながら、様々な活動を進めています。
▼関連リンク:西表島・浦内川流域における陸水環境再生の取り組み
https://www.wwf.or.jp/activities/activity/5412.html
これは、かつてイリオモテヤマネコが餌場としていた、西表島の浦内川流域・旧稲葉集落の乾陸化が進む水田跡地で、水辺を再生する取り組みです。
この活動の一環として、今年度はじめに実施したのは、水田跡地に昨年度掘削した池に、どのような生物が戻ってきたかを確かめる調査でした。
2023年3月に掘削した池とその周辺で、6月から12月にかけて調査を実施しました。その結果、水辺の創出からわずか半年のうちに、数種類の希少な湿地性植物や水生昆虫が戻ってきていることが確認されました。

旧稲葉集落での植物調査の様子(2023年9月)

内貴章世氏(琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設)作成資料より引用。2023年6月から10月にかけて実施された植物調査で確認された、掘削池周辺に新たに生育した維管束植物。
A. ミズワラビの普通葉, B.ミズワラビの胞子葉, C. ウスゲチョウジタデ(環境省・準絶滅危惧、沖縄県・絶滅危惧II類、竹富町自然環境保護条例指定種), D.ウスゲチョウジタデの花, E. オモダカの蕾と花, F. オモダカの葉と花序, G. コナギ, H. タヌキアヤメ(環境省・絶滅危惧Ⅱ類、沖縄県・絶滅危惧IB類、竹富町自然環境保護条例指定種), I. タヌキアヤメの花, J. フタバムグラ.

旧稲葉集落での水生昆虫調査の様子(2023年10月)

トビイロゲンゴロウ、オキナワスジゲンゴロウ(環境省・沖縄県の絶滅危惧Ⅱ類)、ヒメガムシ等、3 月に掘削した池に戻ってきた水生昆虫。2023 年 10 月と 12 月に実施された調査では、これらのほかシャープツブゲンゴロウ、シナコガシラミズムシ、マメガムシなど合計 30 種を超える水生昆虫の生息が確認された。
合意された水辺再生のビジョンと再生計画
それまでの生物調査やヒアリング・協議の結果を踏まえ、2023年10月26日、今後の水辺再生のビジョンや再生計画を話し合うワークショップを開催しました。
参加したのは、西表島エコツーリズム協会、浦内川観光、旧稲葉集落の元住民・地権者、琉球大学・東海大学の研究者、環境省西表自然保護官事務所、WWFジャパンです。

夜遅くまで続いたワークショップでは、参加メンバーから様々な提案やアイディアが出され、今後の活動に向けた活発な話し合いが行われた。
このワークショップでは、旧稲葉集落の対象地をどのような場所にしていくかをまとめた、「イナバ水辺再生ビジョン」が合意されました。内容は次の通りです。
- イリオモテヤマネコをはじめ多様な生き物がにぎわう水辺の再生
-かつては普通に見られた水田等の淡水湿地環境
-平良彰健さんが見た水鳥が舞うイナバの原風景
-イリオモテヤマネコの生息環境(餌場) - 「保全ゾーン」と「体験ゾーン」のゾーニングにより保全と利用を両立
-2つの考え方の池を維持することで、イナバ全体として多様性豊かな環境をつくる - 「保全ゾーン」は、特に希少な水生生物(水生昆虫・湿地性植物等)の 生息・生育地をまもるための水辺として保全
-希少種の保全・再生の場
-調査研究の場、モニタリング - 「体験ゾーン」は、一定のルールのもとでイナバの自然、歴史、文化を学ぶ環境教育、エコツーリズムの場として活用
-生物観察・農耕体験
-イナバの歴史と自然の恵みを活かした暮らしを学ぶ
-利用ルールの作成 - 西表島エコツーリズム協会を中心に、多様な主体との協働による持続的な保全と利活用を実現
-研究者、行政機関、WWF等民間団体との連携 -学校における環境学習への活用と協働
-エコツアーにおける利用と協働、収益の保全作業への活用など
ワークショップでは、このビジョンを形にするべく、生息地保全とエコツーリズムでの利活用という2つの目的に資する、従来よりも大規模な池を作ることも決まりました。
水辺再生計画の実施~保全と利活用2つの池作り
2023年12月8日と9日に、新たに2つの池を作る作業を行ないました。
この作業には、西表島エコツーリズム協会や琉球大学西表研究施設の関係者など西表島民の皆さんに加え、島外からも、水生昆虫のモニタリング調査を担当している東海大学・北野忠氏の研究室メンバー、旧稲葉集落での環境教育に携わってきた大阪ECO動物海洋専門学校の教職員と学生の皆さん、環境省西表自然保護官事務所、WWFジャパンからもスタッフが参加しました。

作業風景(2023年12月8日)。旧稲葉集落の水田跡地は一面に草地が広がり、まずは草刈りから。西表島内から参加した熟練メンバーが、3台の草刈機を駆使して、池の用地周辺の土が見えるようにした。

作業風景(2023年12月9日)。植物の根切りをしながら、カマで土を切り出し、クワで掘り起こし、泥を運んで、畦道を作った。島内外の、所属も様々なメンバーが入り混じり、力を合わせて、手作業による掘削を進めた。
2日間の作業にはのべ51人が参加し、今まで草に覆われ水面のなかった場所に、新たに2つの池が出来上がりました。
また、池の周辺には畔も作られ、浦内川河岸から池への歩行路もできました。

対象地の作業前の様子。

対象地の作業後の様子。約280㎡の四角い池(写真、中央)と約92平方メートルの丸い池(写真、中央左側)を作った。草刈りを待つ間に、2023年3月に掘削した池に繁茂した水草等を除去するメンテナンスも行ない、もとの水面も回復した(写真中央下、中の島のある池)。

12月の池作りに参加した皆さん。1日目

2日目
作業中には、カメ、カエル、ヘビ、トンボ、ゲンゴロウ、サギ等の鳥類など、様々な野生生物が姿を見せてくれ、稲葉の生物相の豊かさを実感しました。

ヤエヤマイシガメ。すぐ後には子ガメの姿も。

ヤエヤマアオガエル。成体もオタマジャクシもたくさん見られた。

作業現場では様々な野鳥の姿も見られた。

作業に合わせて、西表島エコツーリズム協会の方が「マーニー」(コミノクロツグの島での呼称)の葉など近くに生えていた植物で作ってくれた臨時トイレ休憩所。携帯トイレを使い環境に負荷をかけないだけでなく、中はとても快適。かつての旧稲葉集落では、様々な自然の素材を活かした暮らしが営まれていた。
今後の活動とプロジェクト実施メンバー
2024年以降の活動では、新たに創出された池周辺での生物モニタリングを続けるとともに、浦内川流域にかつてあった稲葉集落の自然と暮らしを学ぶ体験型エコツーリズムの開発を進める予定です。
それにより、2023年に合意された「イナバ水辺再生ビジョン」を具現化し、1960年代までは西表島で普通に見られた、イリオモテヤマネコやその生息を支えるさまざまな動植物でにぎわう豊かな水辺の再生を目指します。
<プロジェクト実施メンバー>
西表島エコツーリズム協会
浦内川観光
琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設(内貴章世氏)
東海大学(北野忠氏)
環境省西表自然保護官事務所
WWFジャパン(野生生物グループ)