外来生物と気候変動と動物由来感染症
2021/05/26
はや梅雨の季節。
関東では初夏を思わせる日もある中、鳥たちの子育てが賑やかに始まっています。
そんな折、あれっ?と思う鳴き声を聴きました。
声の主はスズメほどの鳴禽ソウシチョウ。海外から持ち込まれた外来生物の鳥です。

綺麗な声で見た目も愛らしく、そのゆえに日本にペットとして持ち込まれたソウシチョウ。野外に逃げるか放されるかして野生化した個体の子孫が外来生物として定着しました。
この声を聞くと、いつも身近なところに外来生物が存在することを痛感させられます。
しかし、こうした外来生物は、目に見えるものばかりではありません。
IUCN(国際自然保護連合)が指定した、世界の外来生物のワースト100の中には、菌類のような小さな生物も含まれています。
東アジア原産で、中南米やオーストラリアで、多くのカエルなどの両生類を絶滅に追いやっている、カエルツボカビ症はその最たる例といえるでしょう。

中南米に分布するフキヤガマの1種。フキヤガマ属のカエルは94種中、4種が絶滅、残りの8割以上が絶滅の危機にあり、その原因にはカエルツボカビ症や気候変動が挙げられています。昨年12月に更新された、絶滅の危機にある世界の野生生物のリスト「レッドリスト」でも、多くの両生類の危機が明らかにされました。
さらにこうした微生物は、近年の気候変動(地球温暖化)により、もともとの気候や気温では生存できなかった場所にも、分布を広げる危険性が指摘されています。
以前ならば、夏には生きられても、冬に寒くなると死滅していた生きものが、温かくなることで生き延び、繁殖できるようになるためです。
これは同時に、生き延びた生物が媒介し、時には人にも感染する、動物由来感染症のリスクを高めることにつながります。
深刻化する森林破壊によって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に続く感染症が、いつ発生してもおかしくなくなってしまった今の地球上で、さらなる脅威となりつつある、気候変動や外来生物の問題。
その深刻化が、生態系のみならず、私たちヒトの暮らしにも影響や危険を及ぼし始めている、ということを、より広く伝えてゆかねばと思います。
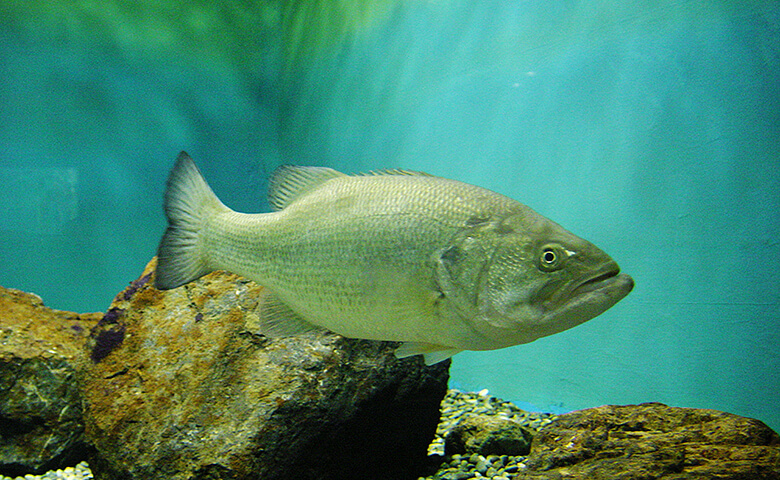
外来生物問題は深刻な環境問題ですが、その生物自体が悪いわけではありません。原因はあくまで、それを持ち込んだ人の側にあります。外来生物を増やさない生物の飼育や管理は、人に問われる大きな責任です。






















