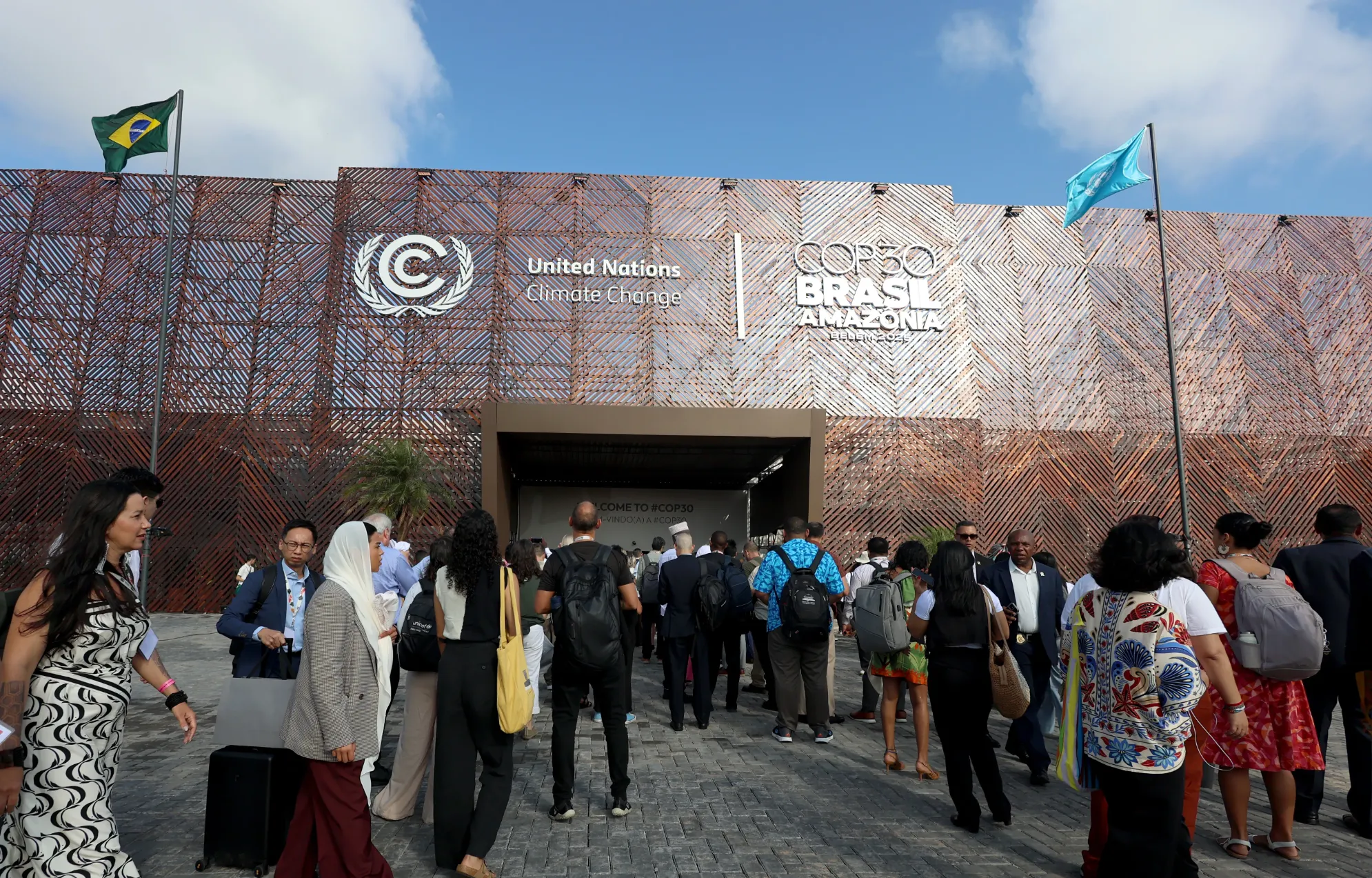「2020年目標」の引き上げを求めて
2014/12/10
南米ペルーのリマより、温暖化担当の山岸です。
ここで開かれている国連気候変動会議(COP20)の会期中、私たちは毎日、その日の国際交渉の焦点について記者会見を行なっています。
8日には、COP20 の3つの論点の一つである「2020年までの削減努力の底上げ」をテーマに選びました。
各国は今、COP16で採択された「カンクン合意」に基づき、2020年までの自主的な目標を掲げ、温暖化対策を行なっています。

2020年までの削減目標に関するWWFの記者会見
しかし、その目標値はすべて足し合わせても、世界の気温上昇を2度未満に抑えるために必要な削減量の、半分にも達しません。そのため、2020年までの削減努力の引き上げが重要な論点とされているのです。
8日の会見では、EU、米、豪のWWFのスタッフたちとともに、私も日本の課題について話しました。そのメッセージはひとつ。石炭による火力発電からの脱却です。
開会2日目、日本政府が「気候資金」支援に入れた途上国への石炭火力発電所への融資を理由に化石賞を受賞しましたが、国内でも石炭火力発電への依存を強めています。

日本の石炭火力発電の問題点について話しました
石炭火力発電での消費を含めた日本の石炭消費量の1990年から2012年の間の増加分を、単純にCO2排出に置き換えると、1億4,000万tにもなります。これはパキスタン1国のCO2排出量を上回る値です。
さらに、35もの石炭火力発電所の新設が計画されています。再生可能エネルギーへの転換に向かう世界の潮流に逆行した、これらの計画が実現すれば、長期にわたって大量の排出が固定化されることになるでしょう。
一緒にこの会見を行なったWWFアメリカのスタッフは、「2013年に米国で新設されたエネルギー施設の70%は再生可能エネルギーだった」と述べていました。

会見後、海外メディアの取材を受けました
WWFでは、シミュレーションに基づき、「2050年にはエネルギー需要は100%、再生可能エネルギーでまかなえる」という可能性を示し、その実現を訴えてきました。2020年、そして2050年の未来の姿を決めるのは、今の世代が下す判断です。

登壇者を待つ記者会見場