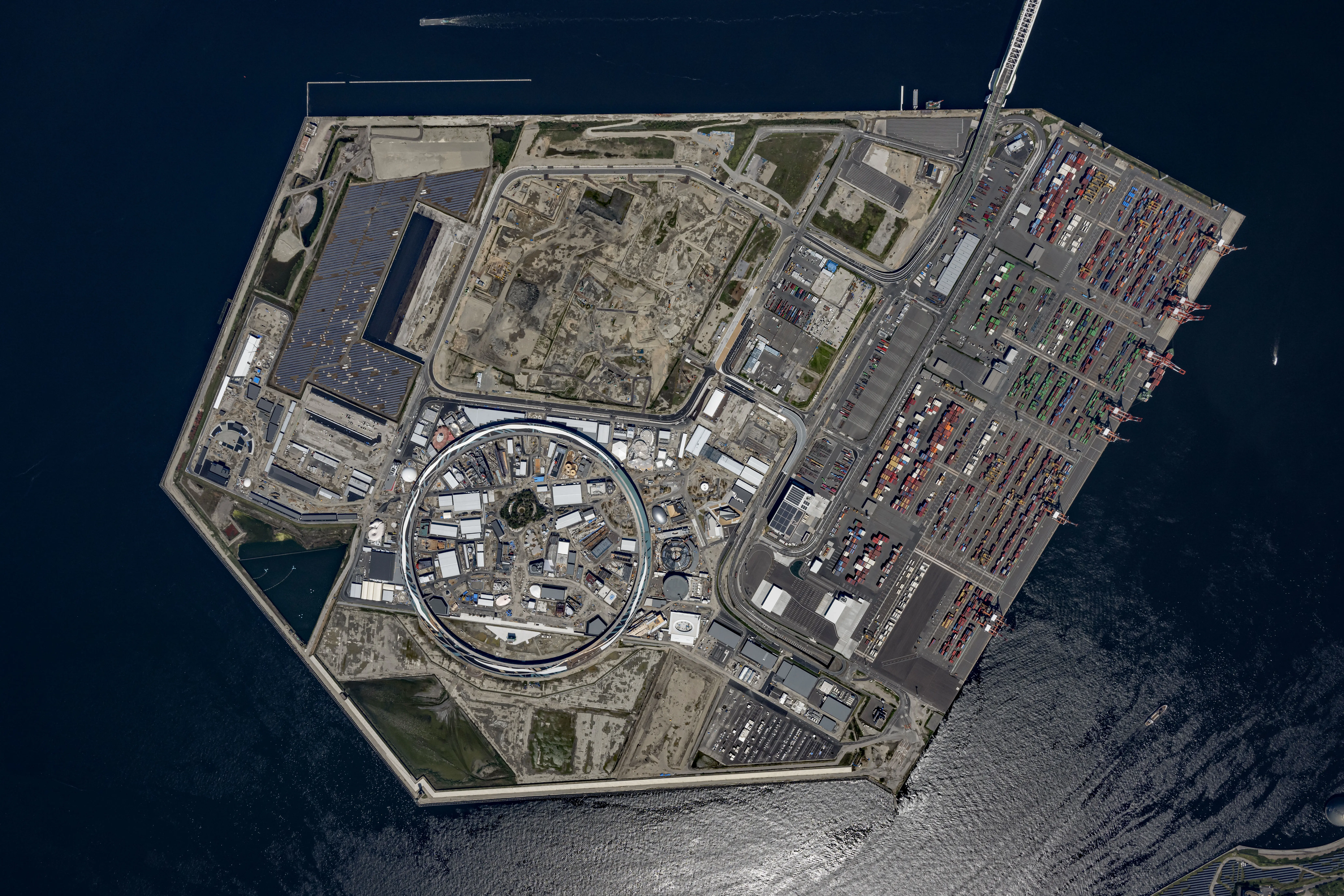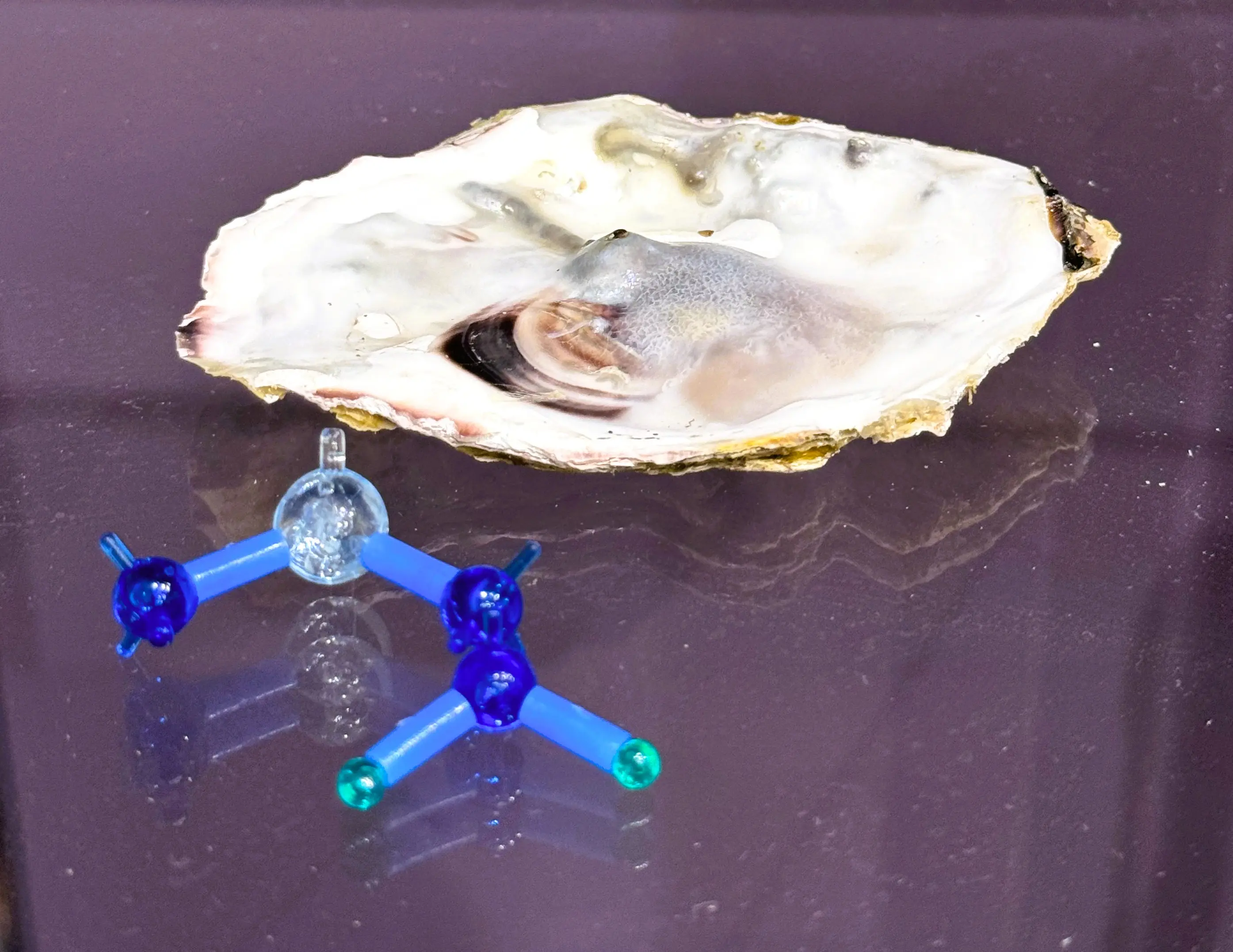生物多様性基本法が成立!
2008/05/27
2008年5月28日、生物多様性基本法が成立しました。国内で初めてとなる生物多様性の保全を目的としたこの基本法には、WWFなどの自然保護団体が提案していた政策の検討段階での市民参加や、より強力な環境アセスメントの導入、国内の自然保護にかかわる各法律の改正などの要点が盛り込まれており、2010年に名古屋で開催が予定されている第10回・生物多様性条約会議に向けた弾みにもなることが期待されます。
日本の自然保護史に新たな1ページ
5月22日、衆議院本会議で与野党の賛成によって、生物多様性基本法案が可決。27日の参議院環境委員会での質疑と、28日の参院本会議での可決を経て、生物多様性基本法が成立しました(公布・施行は6月6日)。
この基本法は当初、WWFジャパンを含む44の国内の自然保護団体が結成した「野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク」が、長年成立を求め、2003年にその原案を各政党の国会議員に提案していたものです。
この提案を受けて、民主党は2007年のマニフェストで「野生生物保護基本法」の制定を公約。与党も有識者や関係機関から意見を募り、検討を始めるなど、法制定への動きが本格化しました。
実際に成立した生物多様性基本法には、ネットワークが重要項目として提案していた、政策の検討段階での市民参加や、従来のアセスメント(開発事業などによる環境への影響評価)よりも強力かつ対象範囲の広い、事業の計画段階からの環境アセスメントの導入、生物多様性の観点を踏まえた個別の法律の改正などが盛り込まれており、今後、日本の環境に関連する国内法が、大幅に強化されることにつながることが期待されます。
これまでの法律と何が違う?
今回成立した「生物多様性基本法」は、これまでの日本に無かった、野生生物や生息環境、生態系全体のつながりを含めて保全する、初めての法律です。
もちろん、すでに国内には、「鳥獣保護法」や「種の保存法」「特定外来生物法」など、生物多様性の保全にかかわる数々の法律があり、施行されています。
しかし、「鳥獣保護法」はあくまで駆除や狩猟などの対象となる鳥獣に対象が限られており、「種の保存法」や「特定外来生物法」も、それぞれ絶滅が懸念される少数の生物の保護や、特に被害が大きいと認められている一部の外来生物のみを扱ったもので、到底、生息環境を含めた野生生物の包括的な保全を実現できるものではありません。
その点、生物多様性基本法は、これらの自然保護にかかわる法律の上位に位置する「理念法」であり、各法律の施行状況を確認し、必要であればその改正や状況の改善を求めることができます。
また、生物多様性の保全に配慮しながら、自然資源を持続可能な方法で利用することや、環境を脅かす可能性のある事業などが開始される前に、問題を「予防的」に解決すること、またそれらの実施に際して一般市民の意見を考慮することなど、国際的には広く行なわれていながら、日本ではまだきちんと導入されてこなかった重要な政策が、この法律によって実現される可能性が高まることになりました。
名古屋での生物多様性条約締約国会議に向けて
今回の生物多様性基本法の成立は、2010年に名古屋で開催されることになっている、第10回・生物多様性条約締約国会議に向けて、大きな弾みとなるものです。
生物多様性条約は、日本を含む世界の締約国に、それぞれの国に「生物多様性国家戦略」の策定を義務付けていますが、この「戦略」には、「法律」としての裏づけがありませんでした。この結果、国の環境行政の指針である「戦略」は、実効性が約束されない、「かけ声」どまり、となっていたのです。
しかし、生物多様性基本法の成立は、この状況を大きく変えることになります。法が定めた、日本としての生物多様性保全のための計画が、これからは実効性を約束された政策となるからです。
また基本法では、都道府県や市町村でも、それぞれの地域の生物多様性保全戦略を作ることを促しており、広く地域に根ざした生物多様性保全の取り組みが、今後さらに広がってゆくことも期待されます。
理念を示した基本法ではありますが、画期的なその内容が、日本の自然保護の歴史における、大きな足跡となることは間違いありません。
「生物多様性基本法」が理念に終始して終わるのか、実際の保全活動に役立てられるのか、それはこれからの日本の取り組みにかかっています。
記者発表資料2008年5月27日
生物多様性基本法を読み解く 基本法のポイントはここ
生物多様性基本法案は、22日の衆議院本会議で与野党の賛成をもって可決し、参議院に送られた。本日、参議院環境委員会で質疑が行われている。近日中に本会議で可決し、生物多様性基本法が成立する見通しである。
この基本法をNGOとして歓迎する理由は以下の通り。
1.野生生物を広く覆う法律が初めて制定された
我が国には、野生生物に関する法律として鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法などがあるが、それぞれに生物種の対象範囲が限られていたり、選定基準が設けられていたりして、法律の網の目から抜け落ちている野生生物が多い。
我が国は生物多様性条約の批准国として(92年署名、93年条約発効)、対応する国内法を整備する必要があった。これまでの政府見解は、既存の複数の法律を組み合わせることで生物多様性が確保されるとの考えから、同条約を批准する要件を満たしているとして、新法の制定をしてこなかった。
しかしながら、絶滅のおそれのある野生生物が多数あり、外来種の強い脅威にもさらされていることなどから、生物多様性の保全に直接的に結びつく法律の制定が望まれる状況にあった。既存の法律の運用だけでは、我が国の生物多様性を保つことがむずかしいのが現状である。
今回、生物多様性基本法が制定され、野生生物を広く覆う法律が制定されることは、同法の下に、各種の法律が有機的に整理されていくことを意味する。ともすれば、個別法による対応でバラバラな印象を与えていた我が国の生物多様性保全の取り組みが、統合的に実施される環境が整う。
2.持続可能な利用の定義が明示された
生物の多様性確保を目的とした法律であるから、国土や自然資源の利用にあたっては、生物多様性が保たれることが前提となるべきである。国内外をみても人間による開発行為等によって、生物種の絶滅や生態系の破壊、森林の減少、海洋生物資源の減少に見舞われている。このことは本法の前文にも書かれているとおりである。
開発行為にあたって、適切な指針を持たないがために、生物多様性の低下を招いてきた。本法の第1条の定義に、生物多様性の長期的な減少をもたらさない方法で、生物多様性の構成要素の利用をする旨の記述がある。このことは、開発行為にあたって、乱開発等に歯止めをかける力があるものとみることができる。
3.予防的な取り組みが明記された
本法第3条3項の基本原則に、「予防的な取組」という言葉がある。予防原則という考えは、92年の国連環境開発会議(UNCED)リオ宣言で示された。この考えが我が国に取り入れられるまでには多くの時間を要したが、近年、化学物質の分野を中心に議論が積み重ねられるようになった。
今回、法律の条文そのものに「予防的な取組」という記述が見られるのは、大きな前進である。
予防原則と予防的な取組のあいだにはやや隔たりがあるものの、「予防的な取組」という表現は、現時点では妥当なものとして評価できる。
生物多様性や生態系の現況把握や将来予測に関しては、科学的にすべて解明しうるわけではないので、科学的な知見がそろわない早期の段階で策を講じるという予防的な取組はことのほか大切になる。
4.生物多様性国家戦略が法定計画に
我が国では、生物多様性条約第6条の定めに従って、国家戦略が策定されてきた。95年10月に最初の「生物多様性国家戦略」が閣議決定され、02年3月には改訂されて「新・生物多様性国家戦略」となった。昨年11月27日には再度の改訂があり「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定された。
二度の改訂作業を経ているのは世界に誇れる点であるが、この国家戦略の最大の弱点は実効性がともなわないことである、との指摘がかねてからあった。
つまり、国家戦略が策定されても、政府は、その実現に対して明確な責務を負うものではなかった。第三次戦略を策定する際に開かれた懇談会・審議会でも、法的な位置づけがないために効力に乏しい、との意見が複数の委員から出されていた。
今回、生物多様性基本法の第11条に国家戦略の策定がうたわれ、法的な位置づけを得た。つまり、生物多様性国家戦略は今後、法定計画としての性格を帯びることになり、そこに書き込まれた各種施策・目標の着実な実行が求められるようになる。今後は国民への約束事項となるのである。
5.生物多様性保全の地方への波及効果
生物多様性国家戦略は、先の記述のとおり、国レベルでは改訂を重ねてきたが、都道府県や市町村にはほとんど意図が伝わっていなかった。たしかに、第三次生物多様性国家戦略策定のあと、千葉県と埼玉県が本年3月に各県版の生物多様性戦略を策定したことが目を引く。両県に続き、兵庫県や愛知県・名古屋市が策定の意思を持っていると聞くが、それでも先進的な自治体の取り組みにとどまっている。
本法は、第13条に都道府県及び市町村の「生物多様性地域戦略」を定めるよう努めることとしており、地方への波及効果が期待できる。努力規定ではあるが、明確に地域戦略の策定を促しており、これまで以上に、各地で戦略策定の取り組みが広まるものと思われる。生物多様性をめぐる事情は地域ごとにことなるものであるから、地域特性をふまえた戦略の策定は大いに歓迎すべきことである。
6.政策形成への民意の反映が明記された
第21条2項には、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映する旨の記述がある。欧州のオーフス条約をみるまでもなく、政策形成に民意を反映させることは、欧州では常識となっている。我が国では、参考意見として意見聴取がなされる程度であるが、「政策形成に民意を反映し」という明快な文言は、欧州並みに近づける後押しとなる可能性がある。
7.事業の計画立案段階からの環境影響評価
第25条において、生物多様性に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者等は、「その事業に関する計画の立案の段階からその事業の実施までの段階において」、影響調査、予測または評価を行うこととされている。
現行の環境アセスメント法は、事業段階の影響評価であり、事業の骨格が決まってからの評価であるため、大きな計画の変更はむずかしく、影響を受ける人や野生生物、自然環境にとって意味のある法制度とは言い難いとの声が強い。
意味のある環境アセスメントを行うには、なるべく早い段階から実施して、計画の大幅な変更や事業自体の中止も含む選択肢を提示することが大切である。第25条に計画段階からの環境影響評価が言及されているのは、アセスメント制度の前進と受け止めることができる。
国では昨年4月、計画段階からのアセスメントである「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」を策定した。ただし、法制度化されていないので、義務的なものではなく、その名の通り指針である。今回の基本法に明記されたことは、戦略的環境アセスメントに法的な裏づけを与えることにつながるものであり、期待を抱かせる。
8.個別の法律の改正に道を開く
附則の第2条に、種の保存法や自然環境保全法、自然再生推進法、その他生物の多様性の保全に関わる法律の施行状況を検討し、必要な措置を講ずるとある。
野生生物や生物の多様性に関する法律には、長年、改正を待たれている法律があるが、改正の日程になかなか上らないでいる。その象徴的なものは"種の保存法"であるが、生物種の絶滅を防ぐはずの同法の効力が弱く、法律として十分に機能しているとは言い難い。我が国において絶滅のおそれがあるとしてレッドリストに記載されている種の3%未満しか、同法の定める「国内希少野生動植物種」になっていない。
種の保存法は、92年の国会で可決成立してから、16年にもわたって抜本的な改正を受けていない。社会的状況の変化に応じて、期待されるような法改正を行わないでいるのは、生物多様性条約批准国にふさわしい対応とは言えない。今回の生物多様性基本法の附則に同法の改正が書き込まれた以上は、時宜を見てなるべく早く改正の日程に載せることが強く望まれる。
その他の法律についても、我が国の生物多様性を保全するのに効力が十分でないものがあり、こうした法律を順次改正していくことが期待される。
9.国民が生物多様性に配慮した物品を選び取ること
第7条には、国民の責務として、生物多様性の重要性を認識した上で、日常生活の中で、生物多様性に配慮した物品を選択することが書かれている。
我が国は、食糧、医薬品、木材、その他の生物資源、自然資源の多くを海外に依存している。知らないうちに、世界の生物多様性に大きな負荷を与えているのである。
国民がこの自覚の下に、環境への負荷の小さな製品を選び取ることなくして、生物多様性基本法の精神が生かされることはない。同法は、国や地方自治体、事業者のみならず、国民一人ひとりにも生物多様性保全の責務がおわされていることを示している。
以上の通り、生物多様性基本法のすぐれた点を列挙してみた。これまでの法律にはなかったような、好ましい条文をいくつも抱えた法律であることは確かである。
ただ、基本法は、ほかの多くの基本法と同様に、原則として理念をうたったものであり、それだけで、ただちに強制力を持って、世の中を変えるには至らない。
この基本法が生かされるも、ただの理念どまりに終わるも、私たちの取り組み次第である。
本法の制定を歴史の転換点として、生物多様性の保全に向けて、大きく社会の舵を切るとき、「人類の存続の基盤」(前文)が確かなものになり、「恩恵を将来にわたり享受できる」(前文)ようになる。前文では文化の多様性についての言及もあり、視野が広いものとなっている。
また、人類にとっての価値だけではなく、数十億年かけて地球上に作り出された生命や生態系、それ自体が内包する価値が損なわれることなく、受け継がれていくことにもなるはずである。
当会として、今般の生物多様性基本法の制定を歓迎するものである。
関連サイト
野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク