新工場稼働により原料不足?APP社への懸念高まる
2016/05/19
2016年4月、WWFを含むインドネシア国内外の12のNGOが共同で、製紙メーカーAPP社の今後の原料調達に対する懸念を発表しました。同社がスマトラ島で1980年代からはじめた紙パルプ生産のために、200万ヘクタール以上の自然の熱帯林が伐採され、その操業が周囲の環境や社会そして気候変動問題に及ぼしてきた影響は、世界から注目されてきました。
消えていったインドネシアの熱帯林
インドネシアのスマトラ島とカリマンタン島(ボルネオ島インドネシア領)で、過去約30年にわたり紙パルプ生産のために自然林原料を調達してきたシナル・マス・グループ(SMG)の製紙メーカー、APP(アジア・パルプ・アンド・ペーパー)社。
これまで、東京都の面積の約9倍にあたる200万ヘクタール以上の熱帯林が同社のために皆伐され、その一部は紙パルプ原料を生産するための植林地へと転換されました。
大規模な自然の熱帯林の破壊は、スマトラトラやゾウなどといった絶滅の危機に瀕する野生生物の生息地が減少するなどの環境面の問題だけでなく、地域社会との紛争という社会的問題にも及んでいます。WWFを含む数多くのNGOが、インドネシアの森林破壊や社会問題をこれ以上悪化させず、環境や社会に配慮した生産活動へとシフトするよう現地企業や政府、購入企業にも働きかけを行ってきました。
しかし、同様の問題が指摘されてきた製紙メーカーAPRIL社とともに、この地域で原料調達され製造された紙原料、紙製品は日本を含め世界中に輸出されています。特にコピー用紙は、日本に流通するコピー用紙の4枚に1枚がインドネシアからのもので、ティッシュ、トイレットペーパーなどの紙製品も大手オフォス通販や量販店を通じて販売されています。
2013年2月にAPP社は「森林保護方針」を発表。サプライチェーンにおける「森林破壊ゼロ」や「パルプ原料の100%を持続可能な植林木から調達する」等の持続可能性に関する誓約をし、その後も森林回復なども追加的に誓約しています。ところが、2015年3月にはAPP社に原料を供給するサプライヤーの植林地で警備員による殺人事件が発生。原因とみられる地域コミュニティとの土地利用をめぐる紛争は、同社自身の調べでも木材供給サプライヤーの伐採許可地全体で、数百件にのぼることが明らかになっています。

APP社の工場

泥炭湿地の森

植林地(プランテーション)として開発された森。手前の直線が水を抜き、伐採した木を運ぶための水路。
泥炭湿地の開発による影響
スマトラ島やカリマンタ島の低地や沿岸部には、地中に大量の炭素を含む泥炭湿地と呼ばれる土壌が広がっています。これは植物などが何千年もかけて未分解のまま堆積して出来た熱帯性の湿地です。植林地や農地を開発するためにこの泥炭湿地に水路をつくり排水し、乾燥させることにより大量の温室効果ガスが地中から排出されています。
さらに乾季になると、この泥炭湿地を人為的に乾燥させた土地で毎年のように問題になる火災は、さらなる温室効果ガスの排出につながり、深いところで地下数十メートルにもなるといわれる地中の炭素についた火を消すことは非常に困難です。
年によっては数カ月以上も続く火災とその煙は、国境を越えたシンガポール、マレーシアなどでも人々の健康や地域の経済に影響を与えています。特に2015年後半に起きた火災の多くはAPP社のサプライヤーの管理地で確認され、このためシンガポールでは同社製品の不買運動も起こりました。
2015年10月、WWFが発表したAPP社の購入企業と投資家向けのアドバイザリー(勧告)において、WWFはAPP社による「森林保護方針」とその後に発表された100万ヘクタールの森林再生と保全の計画の誓約にいくつかの進展を認めつつも、同社の管理する土地では、依然として自然林の減少と違法伐採が続き、社会紛争も未解決のままであること、また100万ヘクタールの森林再生と保全に関しては、計画策定の初期段階にあり詳細が欠けることなど、多くの懸念があることを発表しています。
2016年4月、新たに発表された12のNGOによる共同調査は、APP社が調達する植林木原料が不足する可能性に関するものです。現時点でインドネシアには同社のパルプ工場が2つあります。今後、スマトラ島南スマトラ州に建設中の世界最大規模のパルプ工場(OKI工場)が生産を開始した場合、現在の同社サプライヤーの植林地だけでは、既存の2工場とOKI工場が必要とする原料を長期にわたって供給し続けることは不可能とあります。

インドネシアと周辺国で大きな問題になっている火災による煙害(ヘイズ)。

消火活動には軍隊も出動し対応している。

煙害で曇った町。健康被害も深刻化している。
WWFインドネシアの森林担当、アディティヤ・バユナンダは「APP社は、自社の植林地が3つのパルプ工場の需要を満たす木材を長期的に生産できるという、信頼できる計画をまだ一つも公表していない。木材原料が不足した場合、同社が『森林破壊ゼロ』の誓約を履行せず、自然林由来の大量の木材を再びスマトラのパルプ工場で使い始めるのではないか」と懸念を述べたうえ、「購入企業や投資家は、購買や投資の検討にあたり、APP社の持続可能性への取り組みと木材原料の調達計画を検証するため、真に独立したアセスメントを求めるべきだ。そうしたアセスメントを通して持続可能な操業がなされていることを検証しない限り、買い手もインドネシアにおける新たな森林破壊の波に加担するリスクがある」と強調しています。
下記は、本件に関する12団体共同の発表です。
「森林破壊ゼロ」の誓約企業がインドネシアの森林と泥炭地に新たなリスクをもたらす
WWFインドネシア 2016年4月20日
インドネシア国内外の12のNGOが新たに行った調査により、「森林破壊ゼロ」の誓約をして注目を集めるAPP(アジア・パルプ・アンド・ペーパー)社が、持続的な木材供給の見通しもないまま、世界でも最大規模のパルプ工場をインドネシアの南スマトラ州に建設中であることが明らかになった。
4月22日には、世界各国の代表者が参集し気候変動に関するパリ協定の署名式が行われるが、今回発表されたAPP社の巨大パルプ工場プロジェクトについての分析結果は、このインドネシアおよび中国で最大の紙パルプメーカーが、「森林破壊ゼロ」のコミットメントや2014年の森林に関するニューヨーク宣言、2015年のパリでのCOP21で表明した気候変動に対処するという誓約を果たせない可能性を示唆している。
WWF、ウェットランド・インターナショナル、レインフォレスト・アクション・ネットワーク、インドネシアのアンチ・フォレスト・マフィア連合等、この調査を共同で行った団体によると、この巨大パルプ工場が操業することで、インドネシアがこの地域での壊滅的な火災を防ぎ、気候変動に関する国際的な誓約を果たすことが、かなり困難になるという。
WWFインドネシアの森林担当、アディティヤ・バユナンダは、「APP社は、自社の植林地が3つのパルプ工場の需要を満たす木材を長期的に生産できるという、信頼できる計画をまだ一つも公表していない。木材原料が不足した場合、同社が『森林破壊ゼロ』の誓約を履行せず、自然林由来の大量の木材を再びスマトラのパルプ工場で使い始めるのではないかと懸念している」と述べている。
この調査報告書の分析によると、現在インドネシアに2つあるAPP社のパルプ工場と新たに建つ工場がフル稼働した場合、同社が今持っている植林地だけでは、たとえ植林木の成長が速かったとしても工場の需要を満たすには十分でない。木材が不足すれば輸入すると同社は発言しているが、報告書によれば、それにはかなりの追加的なコストがかかり、新工場の収益性に影響が出る可能性がある。
OKI紙パルプ工場と呼ばれるこの新工場建設プロジェクトへの投資額は30億ドルにのぼり、インドネシア国内におけるAPP社の木材需要は50%以上増える予定だ。そして原料の多くは炭素を大量に含んだ泥炭地に造成された植林地から切り出されることになる。工場建設の資金は主に中国国家開発銀行とICBC(中国工商銀行)ファイナンシャル・リーシングから25億ドルの融資を受けたため、APP社は財政的にも新工場をフル稼働せざるを得ない状況にある。
2013年にAPP社は、サプライチェーンにおける「森林破壊ゼロ」や「パルプ原料の100%を持続可能な植林木から調達する」等の持続可能性に関する誓約をした。その5か月後、同社はOKI巨大紙パルプ工場を建設すると発表した。
この調査報告書では、新工場に木材を供給する製紙用植林地の生産性を脅かす主な要素として、壊滅的な火災、泥炭地の地盤沈下と浸水、社会紛争、病害虫を挙げている。これらの植林地は、2015年にインドネシアで発生した大規模な火災でかなりの被害を受けた。同報告書が引用した分析によると、APP社のサプライヤー4社が管理する伐採許可地のうち、29万3000ヘクタールが2015年の火災で焼えたという。ここには8万6000ヘクタールのアカシア植林地が含まれ、南スマトラ州におけるAPPグループの植林面積の26%に当たる。その結果、APP社の役員も同グループが「木材供給不足」に直面していることを認めている。
またこの報告書では、シナル・マス・グループが南スマトラ州に保有する伐採許可地の77%が炭素を大量に含んだ泥炭地にあるとし、APP社の植林地が長期的にも集約的なパルプ材生産を継続できるか疑問を呈している。泥炭湿地は、植林地開発のために排水し乾燥させると非常に燃えやすい状態になる。時間の経過とともに、こうした泥炭地の多くが浸水という問題にも直面することになるだろう。というのは、泥炭地を排水すると地盤が沈下して地表面が少しずつ下がり、それが長期的には浸水につながることがあるからだ。同じスマトラ島にあるカンパール半島の泥炭地に造成した植林地に関する2015年の調査によると、地盤沈下とこれに伴う浸水の結果、製紙用植林地とアブラヤシ農園の多くが数十年のうちに使えなくなり、結果として、経済的にほとんど、もしくは何の用途もない劣化した景観になってしまうという。
国際的なNGOでウェットランド・インターナショナルの泥炭地の専門家、マルセル・シルビウス氏は、「南スマトラ州の泥炭地はカンパール半島よりも一般的に泥炭の層が浅いので、APP社の植林地はかなり速く浸水状態まで沈下するだろう。実際に一部の植林地では既に雨期になると浸水が起きていて、このまま泥炭地からの排水を続けた場合、OKI工場に木材を供給するための植林地がいつまで生産性を保てるのかという重大な問題を提起している」と述べている。
APP社は、同社自身の調べで、5つの州にある製紙用の伐採許可地と土地が重複する地域コミュニティとの間に数百件の紛争を抱えている。土地紛争が起きたりコミュニティの生計に悪影響が生じたりすると、操業の停止や植林地の損傷、破壊、伐採許可地の縮小、場合によっては暴力事件といった事態につながり、植林地の生産性が低下する。この報告書によると、APP社はこの3年間、紛争解決に向けた地域コミュニティとの協議を誓約してきたが、結局3つのコミュニティと部分的な合意をしただけに終わっている。
南スマトラ州のNGOで、APP社のサプライヤーの植林地で紛争を抱えるコミュニティと緊密な活動を続けているフタン・キタ・インスティチュートのアイディル・フィトリ氏は、「長年にわたって植林地が引き起こしてきた損害と紛争という負の遺産に取り組むには、APP社が地域コミュニティの土地保有権と使用権を尊重することが欠かせない。我々はAPP社が、OKI工場のためのパルプ原料を確保するために、関係するコミュニティから自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)を得るという適切な手続きを踏むことなく、植林地の拡大に動くのではないかと憂慮している」と述べている。
WWFインドネシアも参加し、現地で森林のモニタリングを行う複数のNGOの共同プロジェクト、アイズ・オン・ザ・フォレストによると、現在スマトラ島に2つあるAPP社の工場のために、これまでに200万ヘクタール以上の自然林由来の木材がパルプとなった。同グループは長年にわたり、森林生態系を破壊し、慣習地から地域コミュニティの住民を追い出し、炭素を大量に含んだ泥炭地を開発して地球温暖化に影響を及ぼしてきたことで批難を受けてきた。ところがAPP社が2013年に持続可能性への誓約をしたことで、同社に対する世界的な反対運動は弱まり、批判の少ない環境が作り出された。そしてその間にAPP社は新パルプ工場を建設した。しかし、巨大なOKIパルプ工場の操業によって、かつてない膨大な木材原料が消費されることに懸念が高まっている。
WWFのアディティヤ・バユナンダは、「購入企業や投資家は、購買や投資の検討にあたり、APP社の持続可能性への取り組みと木材原料の調達計画を検証するため、真に独立したアセスメントを求めるべきだ。そうしたアセスメントを通して持続可能な操業がなされていることを検証しない限り、買い手もインドネシアにおける新たな森林破壊の波に加担するリスクがある」と強調した。
共同執筆者: Koalisi Anti Mafia Hutan, Woods & Wayside International, Hutan Kita Institute, WWF, WALHI, Wetlands International, Eyes on the Forest, Auriga, Forest Peoples Program, Jikalahari, Elsam, Rainforest Action Network
原文(英語のみ)
共同調査報告書(英語のみ)
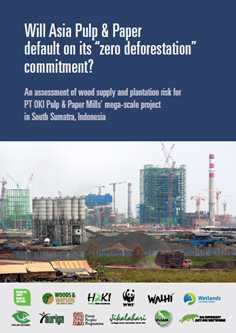
発表されたレポート













