島嶼の生態系を守るために~外来種問題を考えるシンポジウム報告
2017/06/06
ユネスコの世界自然遺産への登録が実現しようとしている、南西諸島。台湾から九州まで連なるこの島々には、沖縄諸島や八重山諸島、奄美諸島などが含まれ、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなど固有の野生生物も少なくありません。しかし、こうした生物は今、島外から人の手で持ち込まれた「外来種」の深刻な脅威にさらされています。島という閉じた環境の中で、問題を解決し、本来の自然を守るためには何が必要なのか。WWFジャパンと日本自然保護協会は2017年2月25日、この外来種問題を考えるシンポジウムを開催しました。
南西諸島の自然と外来種問題
亜熱帯性の森林や、マングローブ、数百種のサンゴが生育する海、その自然の多様性と固有種の多さから「東洋のガラパゴス」とも呼ばれる南西諸島。
沖縄県北部に生息するヤンバルクイナやノグチゲラ、奄美大島に生息するアマミノクロウサギなど、世界中でその地域にしか生息していない野生の動植物が、そこには数多く生息しています。
その独特の島嶼生態系は、海に隔てられた「島」という環境の下、気候や環境条件、また共存する他の野生生物との競争の中で、長い年月をかけて育まれてきました。
しかし、人間によるさまざまな活動により、その自然は今、大きく失われようとしています。
本来その地域に生息していなかった生物が、人によって島外から持ち込まれ、地域固有の自然環境や野生生物を脅かす「外来種」問題の深刻化も、その一例です。

南西諸島の島々

ヤンバルクイナ
脅かされる島の固有種たち
南西諸島で問題になっている外来種としては、沖縄島や奄美大島に持ち込まれたマングースが有名ですが、生態系に影響を及ぼしている動物は、他にも多くあります。
飼育されていたイヌやネコなどが逃げ出し、野生化したノイヌやノネコなども、ケナガネズミやヤンバルクイナなどを捕食し、深刻な影響を与えているほか、日本国内の他の場所から持ち込まれた昆虫などの小さな外来生物も、さまざまな被害をもたらしています。
そして、これらの生きものの中には、人間が意図的に野外に放したものだけでなく、意識しないまま、荷物や資材などと一緒にその島に持ち込んでしまった例があることも知られています。
この外来種による影響は、沖縄や奄美、八重山など南西諸島の島々をはじめ、世界中の島嶼地域で認められており、中には島の固有種を絶滅に追い込んでしまうなど、重大な環境問題の一つとして対策が求められています。
南西諸島ではこれから、ユネスコの世界自然遺産への登録が実現しようとしていますが、その結果として、観光客が増え、さまざまな形で持ち込まれる外来種が増える可能性も懸念されます。
こうした島嶼独自の生態系を守るために何をするべきなのか。
WWFジャパンと日本自然保護協会は2017年2月25日、外部から専門家を招きその課題を解説するシンポジウムを開催。
外来種問題の概要と、国際的なその対策に向けた動き、さらに島嶼生態系が受けるその影響と、今後の南西諸島の保全に向けた重要な点を検討、指摘しました。

ケナガネズミ

シンポジウムの様子

会場 中央大学駿河台記念館
▼シンポジウムの詳細についてはこちらをご覧ください
| 名称 | 外来種問題を考えるシンポジウム~島嶼の生態系を守るために~ |
|---|---|
| 日時 | 2017年2月25日(土) 12:30~16:30 |
| 場所 | 中央大学駿河台記念館 670教室 〒101-8324 東京都千代田区神田駿河台3-11-5 |
| 参加者数 | 約80名 |
| 主催 | WWFジャパン、日本自然保護協会(NACS-J) |
| 後援 | (公財)自然保護助成基金、沖縄生物学会 |
| 基調講演 | 五箇公一(国立環境研究所) |
| 話題提供 | 権田雅之(WWFジャパン)、佐々木健志(琉球大学博物館(風樹館))、安部真理子(日本自然保護協会) |
| パネルディスカッションコーディネーター | 草刈秀紀(WWFジャパン) |
外来種防除のために
最初に、国立環境研究所の五箇公一氏より、外来種が持ち込まれる経路には、ペットや緑化植物としての需要や、天敵駆除を目的とした「意図的」な場合と、人や物資の移動の際に付着・混入する「非意図的」場合があることを説明。
その深刻な例として、ペットとして人気が出たアライグマが、飼育の難しさから飼育放棄されたり、逃げ出したりして、野生化・繁殖し、在来種や農作物を食べ荒らす生態系・農業被害が出ている例や、沖縄や奄美で毒ヘビのハブを食べると期待され持ち込まれたマングースが、実際には主な活動時間帯の違いからハブを食べず、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギ等の希少種を捕食している例などを解説しました。
また、外来種が病原菌やウィルス等を体内に保有している場合、人獣共通の感染症を媒介する危険性があることにも触れ、外来種問題は生態系保全のためだけではなく、人間の生活を守る上でも重要な問題であると指摘しました。
五箇氏は次に、2005年に施行された「特定外来生物法(特定外来種による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」についても解説。
この法律で「特定外来生物」に指定された種は、自治体が責任もって駆除することが義務付けられている一方で、自然環境下で繁殖を続ける生物を完全に駆除するためには多くの費用や時間、労力が継続的に必要であり、現行の体制下では自治体のみでは充分な対策が難しい場合も多いこともお伝えしました。
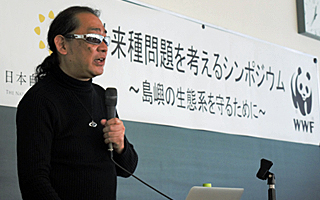
国立環境研究所 五箇公一氏

アライグマ

カミツキガメ。特定外来生物に指定されている
世界的な認識の高まり
次に、日本自然保護協会の安部真理子氏より、国際的な流れとしても、外来種問題への対策が求められていることを説明しました。
2016年9月にハワイで開催されたIUCN(国際自然保護連合)の第6回 世界自然保護会議では、日本自然保護協会やWWFジャパンを含む日本国内の6団体で「島嶼生態系への外来種の侵入経路管理の強化」を求める勧告を提案。それが参加諸国により採択されました。
このように、「一度入った外来種を取り除くことは困難であり、侵入の予防が最も重要である」という認識が、国際的にも高まっています。
国境を越えた移動だけでなく、国内で生態系が異なる場所間の移動でも外来種が生じることから、今後、世界自然遺産登録や軍事化が進むにつれ確実に物資の移動が多くなる奄美・琉球諸島地域においても、予防の観点から対策をしっかりと行うべきであると強調されました。
その一例として、沖縄県名護市の辺野古周辺で進められている米軍基地建設の問題を解説。建設資材や土砂が、奄美大島や徳之島など、島外6県7箇所から調達される予定であり、外来種の侵入が懸念されていることをお伝えしました。
辺野古の海には、マングローブやサンゴ礁など貴重な自然が残り、絶滅危惧種であるジュゴンの日本最後の生息地となっていますが、こうした場所での埋め立てに際しても、本土や島外から持ち込まれる土砂に紛れて、あらたな外来種が入り込む可能性があります。
安部氏は、そのリスクが高いことを指摘すると共に、同じ気候帯である沖縄本島、奄美大島間での移動であっても、島ごとに生態系が異なるため「県内外来種」となること、また一方の島ではまだ確認されていない外来の害虫の卵や植物の根等が混入し移動・拡大する被害を防ぐためにも、慎重な対応を求めることを強調しました。

日本自然保護協会 安部真理子氏

辺野古の海
島嶼地域ならではの外来種問題
沖縄県には1200種を超える外来種が定着しており、その種数は日本の外来種の半分近くに達することや、亜熱帯地域に属する沖縄では、ウリミバエに代表されるような熱帯系の農業害虫が多いこと、また主要な島ごとに生物相が少しずつ異なるため、島間の人為的な移動による県内外来種が生じやすいことなどを指摘。
また、すでに多くの外来種が定着している沖縄県では、生態系や人的被害を予測しつつ限られた予算の中で優先的に対策すべき種を早急に選定する必要があることを強調。
定着後の対応には膨大な予算や労力を要するため、早期発見・早期対策のための市民も巻き込んだ監視体制を構築する必要があり、特にペットなどを介して外来種と関わりの深い子どもたちへの教育は重要なため、教員の研修や、学校の授業に外来種教育を盛り込むことが望ましいとのお話でした。

琉球大学博物館(風樹館) 佐々木健志氏
ノネコ・ノイヌの脅威
WWFジャパンで南西諸島の保全プロジェクトに携わるスタッフの権田雅之からは、地域の固有種を守る上では、飼いネコ・飼いイヌが野生化した、ノイヌ・ノネコへの対策が重要であることをお伝えしました。
野生化し、自然の中で繁殖するようになったノネコやノイヌが、沖縄地域の固有種を捕食する大きな脅威となっている例として、固有種であるアマミノクロウサギをくわえているノネコの写真が撮影されたことや、フンの中からヤンバルクイナの羽が見つかったことなどを紹介。
また、2005年には飼い猫の適正管理のための条例(飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例)が施行され一時はその個体数を減らしていたアマミノクロウサギも、その後また数が回復傾向にあることも指摘し、自治体による継続的な防除計画の策定と実行や、住民への普及啓蒙、また地域を巻き込んだ監視体制の強化が重要であること強調しました。

WWFジャパン 権田雅之
地域内から防ぐために
続いてのパネルディスカッションでは、WWFジャパンの草刈秀紀がコーディネーターとして、来場者からの質問へ答える形で進行しました。
多くの質問が寄せられる中で、特に活発な議論となったのは、外来種問題の普及啓蒙についてです。
外来種防除のためには、予防3原則と言われる「入れない、捨てない、広げない」ために、地域住民間での普及啓蒙と、協力した監視体制が鍵となります。
しかし、外来種の防除とは即ち「生物を守るために、生物を駆除する」ということ。この妥当性や緊急性を、真に理解し行動してもらうことに苦労している、という声が登壇者からも聞かれました。
また、そもそも外来種問題は人間が引き起こしたものであり、外来種の生物に罪があるわけではありません。そのことを忘れず、意図的・非意図的に関わりなく、本来存在しない場所へ生物を持ち込むようなことがないように、予防を前提にした取り組みの徹底が望まれます。
法整備や自治体による防除の取り組みに加え、いかに多くの個々人に伝え、地域内での監視体制を強化してゆくかが重要であることを強調し、シンポジウムは閉幕となりました。

パネルディスカッション コーディネーター:WWFジャパン 草刈秀紀
長期的な視野での保全を
自然環境下で培われた生態系のバランスや、地域固有の生物は、一度人の手によって損なわれれば、再生することは極めて困難です。また、一度持ち込まれ、定着してしまった外来種を根絶することも、同様に非常に難しい取り組みとなります。
豊かな自然環境や、独自の生態系の貴重性が認められているからこそ、ユネスコ世界自然遺産への登録を目指している、南西諸島地域。
今後、観光需要の高まりに伴い、多くの人や物資の移動や開発が見込まれる中で、貴重な環境や生態系の保全と、持続可能な利用の両立を、どのように実現していくか。
地域での取り組みに加え、予防を大原則とした、長期的な視野での保全・利用計画が求められています。

講演資料
- なぜ外来生物は増えるのか? その防除の成否の鍵は何か?〜生物多様性の復元を目指して〜 国立環境研究所 五箇公一
- 沖縄の外来種問題について 琉球大学博物館(風樹館) 佐々木健志
- 地域と連携した外来生物問題の取り組み~奄美大島での活動事例~ WWFジャパン 権田雅之
関連情報
※お詫び 2017年6月6日の本稿の公開にあたり、事務局のミスで講演者の皆さまにいただきました修正が、一部反映されないままとなっておりました。大変申し訳ございませんでした。修正につきましては、6月7日午後の時点で全て反映いたしました。関係者および、読者の皆さまに心よりお詫び申し上げます。













