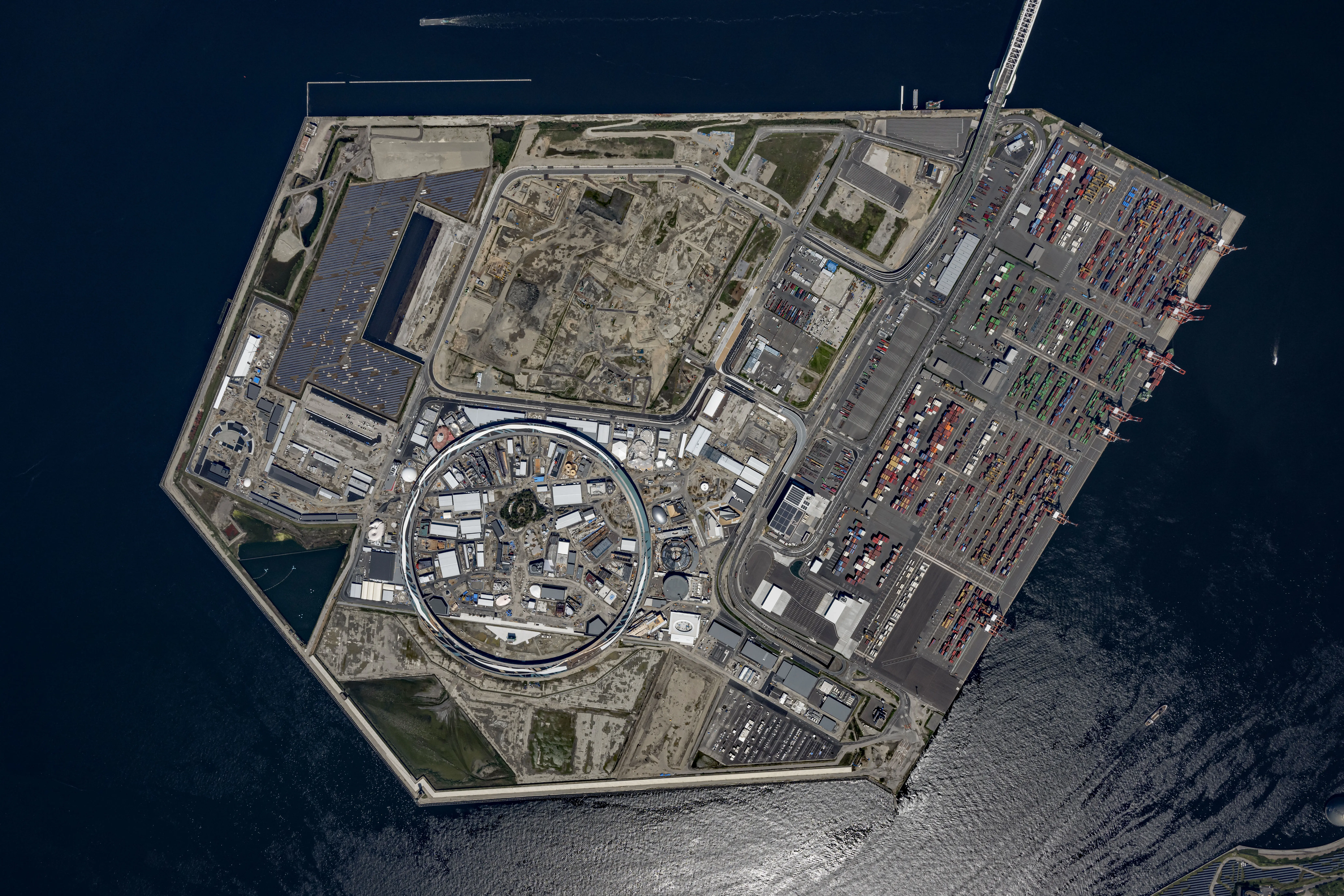ボルネオの森の豊かさを測る~森林の利用と保全の両立に向けて
2014/09/09
世界有数の熱帯林に覆われた赤道直下の島、ボルネオ島。ここには、アジアゾウやオランウータン、スマトラサイ、ウンピョウといった希少種をはじめ、多種多様な野生生物が生息しています。しかし一方で、木材のための伐採やアブラヤシなどのプランテーションが進んだ結果、 過去半世紀に急速に森が失われてきました。そうした中、現場では今、WWFの支援のもと木材伐採企業が自らの手で森の豊かさを測り、その保全と利用の両立をめざす取り組みを進めています。
止まらない森林破壊
インドネシア、マレーシア、ブルネイの三国にまたがり、今も手つかずの原生林が残るボルネオ島。地球上でここでしか見られない固有種も多く生息するこの島は、1980年代半ばまで、面積の75%が豊かな熱帯林に覆われていました。
しかし、現在までに森は50%まで減少、今もその勢いは衰えません。主な原因は、森林伐採や石炭の採掘、紙の原料となるアカシアの植林地への転換、また植物油(パーム油)として私たちの生活にもなじみ深いアブラヤシのプランテーション拡大などです。
森の消失は、貴重な生物多様性を損なうだけでなく、地球温暖化を深刻化させることにもつながります。炭素を固定している樹木が伐採され、農地転換されることにより、大量の二酸化炭素(CO2)が大気中に放出されるためです。実際に、インドネシアやアマゾンといった熱帯の森林消失に伴うCO2の排出は、世界全体の排出量の2割を占めています。
こうした問題を背景に、インドネシア、マレーシア、ブルネイの政府は、WWFの働きかけのもと、2007年、「ハート・オブ・ボルネオ」宣言を発表。世界的にみても際立って豊かなボルネオの生物多様性を守りつつ、森の恵みを持続可能な形で利用していくため、国境を越えて取り組むことを約束しました。


ボルネオ島では急速に森が減少している
伐採企業が取り組む森の利用と保全
こうした活動の一環として、WWFジャパンも現在、日本の知見を活かしながら、インドネシアの現地企業の取り組みを支援しています。
フィールドは、島中央部に位置するクタイバラ県およびマハカムウル県。約240万ヘクタールものまとまった規模の森が残り、全長980キロを誇るマハカム川が流れるエリアです。
このマハカム川は絶滅の恐れがあるイラワジイルカの生息域であり、さらにその上流の森では2013年、この地域では絶滅したと考えられていたスマトラサイ(亜種名ボルネオサイ)の生存が20年ぶりに確認され、世界中から注目が集まりました。
県内で木材の伐採を手掛けている企業は20を数えますが、そのひとつがラタ・ティンバー社。東京都の約半分の面積に匹敵する約10万ヘクタールの森の伐採権を所有する同社は、毎年約6万立方メートルの木材を伐採、その一部は合板やフローリングに加工されて日本へも輸出されています。
しかし、ラタ・ティンバー社は、見境なく森を皆伐し、利益を追求しているわけではありません。ボルネオの豊かな森林資源を、ビジネスの基礎として慎重に扱い、その持続可能な利用を心がけています。
たとえば、伐採にあたっては、種子を散布する「母樹」を保護したり、林冠をつながった形で広く維持できるように樹木を残したりなど、森林の回復を助ける試みを実践。さらに、林道の敷設にも計画性と効率に配慮することで、人の手が森の環境に及ぼす影響を、できるかぎり抑える工夫に取り組んでいます。
さらに同社は、森林環境や地域社会への配慮を国際的に認証する、FSC(R)(Forest Stewardship Council(R):森林管理協議会)の認証を取得、その基準に即した操業を営んできました。


マレーグマの子ども

マハカム川沿いにある、ラタ・ティンバー社

左:伐採現場の様子。右:いかだを組み、川を利用して丸太を搬出する
森の「豊かさ」を測る
では、こうした伐採企業による森林管理の実践が、実際にはどれだけ森の保全に貢献しているのでしょうか。WWFジャパンは2012年より、京都大学北山兼弘教授(森林生態学)らのチームが開発した指標を用いて、「森の豊かさを測る」取り組みを支援しています。
2014年6月には、北山教授よりラタ・ティンバー社をはじめとする現地の関係者に対し、その検証の進捗が報告されました。
検証のための調査は、森の全域で、すべての動植物を対象に行なうことが理想ですが、広大な森では現実的にはかないません。そこで、北山教授は、対象となる森の一部で調査を行ない、樹種や木の直径といったデータを集め、その種数や構成を解析することで、森全体がどのような状態かを測る手法をとっています。
調査はまず、自然林から森林破壊が進んだエリアまで、森の荒れ具合を6つのレベルに分類します。さらに、「プロット」と呼ばれる調査地点を、各レベルで10カ所ずつ、合計60カ所、ランダムに設定し、それぞれの地点で樹種や木の太さを実際に測ってデータ化しました。
そして、樹種の構成に基づいて調査地点の「森の豊かさ」を計算し、さらに衛星画像と照らし合わせながら調査地点以外の「森の豊かさ」も求め、地図に表しました。これによって、森の現状が全域でよくわかるようになり、多くのエリアで、伐採にも関わらず「森の豊かさ(生物多様性)」が比較的よい状態に保たれていることが見えてきました。
交通の要所であるマハカム川に近く、農村が点在している東部の森では、相対的に大きなダメージを受けていることも分かりました。インドネシアでは、国や地方自治体の保護区や、企業の伐採地であっても、地域住民が入り込んで主食のコメを生産したり、高収入につながるアブラヤシ農園のために森を切り拓いたりすることが少なくありません。
こうした行為は、厳密には法律に抵触する問題となる場合もありますが、代々この地に暮らしてきた人々にとっては、慣習的に利用してきた森でもあるのです。そのため保全の現場では、地域住民との信頼ある関係づくりも重要な要素となっています。

調査の様子。写真中央が北山教授

木の直径をはかり、データを集める。
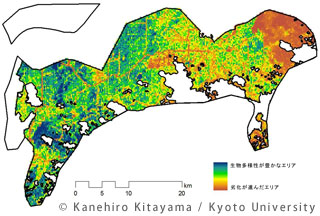

川沿いに村が点在する。
「REDD+(レッドプラス)」のモデル事業への貢献
本調査は、また一方で、インドネシア政府による「REDD+(レッドプラス)」のパイロットプロジェクトとしても注目されています。
何も対策をせずに森を伐採し続けた場合と、適切に守りながら利用している場合とでは、失われる森の規模は異なります。その差を木々が蓄えている炭素量に換算し、経済的なインセンティブを与えることによって、森林保全活動に付加価値をつけてCO2を削減するしくみ、それがREDD+です。つまり、森を保全することで、CO2の排出を防ぎ、温暖化を防止する取り組みです。
このためには、保護あるいは適切に管理されている森が、どれくらいの炭素量を保持しているか、評価することが欠かせません。「森の豊かさ」を測る調査は、この炭素量を評価するものでもあります。
今回の報告では、ラタ・ティンバー社の森は1ヘクタールあたり平均約172トンの炭素を保持していること、その地理的な蓄積状況は、生物多様性の豊かさと同様の傾向がみられることが指摘されました。
地方政府の森林局や、県内の他の木材企業の関係者も集まり、耳を傾けた北山教授の調査報告は、適切な森林管理の実践が、生物多様性の保全と炭素の蓄積に寄与することを、科学的に証明する第一歩となったのです。
今後は解析を続けるとともに、再びデータ収集を行ない、経年変化をみたうえで林業のあり方を評価することにしています。さらに、FSC認証を取得していない他の伐採企業の森でも、同じ手法を導入して経年変化の違いを比較することで、適切な森林管理の優位性を明らかにすることができないか期待されています。
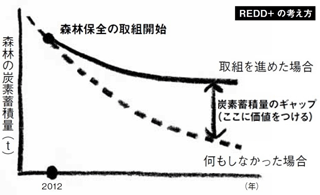
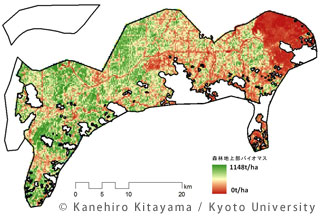

北山教授の報告に耳を傾ける関係者たち
企業自らの取り組みに「自信」を!
北山教授の手法は、できるだけ簡素で経費がかからず、樹種の特定を除けば高度な専門性がなくとも実行できることをめざしています。
またこれまでは、伐採による悪影響ばかりが注目されてきましたが、この手法ではポジティブな効果も定量的に示せることから、企業が自ら、自分たちの森を評価する指標として、広く取り入れる可能性も期待されています。今回の一連の調査も、京都大学の技術指導とWWFの支援のもと、ラタ・ティンバー社自身の手で進められました。
これまで、伐採企業といえば、森林破壊の張本人のように見られてきました。今も、そうした企業が多くあることは確かです。
しかし一口に伐採といっても、自然林をすべて切り拓いて植林地や農園にする方法ばかりではありません。ラタ・ティンバー社のように、自然林から商業価値のある木を「抜き伐り」しつつ、伐採した木の周辺の森を適切に管理することは、熱帯地域で生物多様性を保全するうえで、非常に大切な役割を果たしています。
さらに、現場で森に接し、その豊かさに依存してビジネスを手掛ける企業が、森の健康状態をきちんと把握し、持続可能な管理に配慮するならば、それが森林の保全を進めるうえで大きな力となることは間違いありません。
WWFインドネシアのスタッフは、「森の豊かさを客観的に評価することは、将来にわたって自社の森で操業を続けられるかどうかを把握するという重要な経営課題でもある」と話します。北山教授も「この手法のメリットは、企業が自らの手で森の状態を把握できること。自分たちの取り組みが客観的にも認められることで自信を持ってほしい」と話してくれました。
長期にわたる地道な取り組みではありますが、環境や社会に配慮した森林経営が広がれば、日本の消費者も、ボルネオの森を破壊することなくつくられた木材製品を入手できることになります。
WWFジャパンは、さまざまなステークホルダーと協力しながら、森林破壊と木材、炭素と温暖化、地域社会の問題にも目を向け、ボルネオの森を守ってゆくための取り組みを進めていきます。

森の利用と保全の両立に取り組むラタ・ティンバー社のスタッフ。


日本のホームセンターで売られている、ラタ・ティンバー社から材を仕入れている製材会社(ティルタ・マハカム社)の合板。