マグロの漁獲方法
2009/09/10
北半球と南半球、それぞれ高緯度から赤道周辺まで、広大な海域を回遊するマグロは、各海域の漁場で漁獲され、運ばれています。現在、マグロを獲る主な方法としては、3つの漁法が使われています。
どうやって獲るか?
延縄(はえなわ)漁法
日本で開発された漁法です。漁具は、幹縄と枝縄、その先につけた釣り針で構成されています。幹縄が海底に沈んでしまわないように、幹縄にはブイ(浮き)が取り付けられます。針のついた枝縄を40~50メートルの間隔でつり下げた幹縄は、船上に引き上げる時には、引き縄の役目を果たします。
延縄漁法は、比較的大きなマグロを釣り上げます。マグロを1匹1匹釣り上げるので、マグロの傷みが少なく、高品質が要求される刺身向けマグロを漁獲するための漁法といえます。しかし、2000~3000の釣り針に一匹ずつ付けた冷凍のサンマやイカなどの餌に対し、かかるマグロはわずか数匹程度(1トン前後)。しかも、1回の操業で繰り出される幹縄の長さが数10キロから100キロに達するため、縄を投げ込み、マグロをつり上げるまで、作業に丸1日近くを要してしまうなど、多大な作業、餌や燃料が必要です。
また、枝縄の先の釣り針につけられたマグロの餌を、ウミガメや海鳥など他の野生生物が食べ、針に引っかかって死んでしまう「混獲」の問題も発生しています。

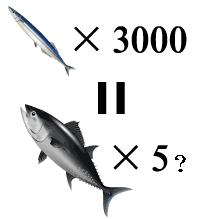
巻き網漁法
大型の網を円形に広げて、泳ぎ回る魚を群ごとすばやく包み込むようにして獲る漁法です。群を網で囲むと、網の底をしぼって囲みを小さくします。円を描く網の直径は、200メートルから1000メートルにもなります。缶詰用のマグロは主にこの方法で獲られます。
群を網で囲むと、網の底をしぼって囲みを小さくします。円を描く網の直径は、200メートルから1000メートルにもなります。缶詰用のマグロは主にこの方法で獲られます。
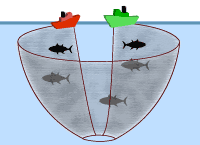
巻き網漁は、網を絞り込んだ後、船上に引き上げます。狭めてゆく網の中でマグロが暴れたり、網の中のマグロの重みでマグロ自体が押しつぶされたりするため、マグロが傷つきやすく、あまり刺身向けにはされません。しかし、日本近海では小型のクロマグロをこの巻き網漁で漁獲し、メジという呼び名で、刺身用に販売しています。メジは、小型のため脂ののりが悪く、価格も比較的安いのが特徴です。 また、巻き網漁は、蓄養用のマグロを獲る漁法としても使われます。巻き網で漁獲したマグロは船上に引き上げず、海中で曳航用の生け簀に移し、沿岸の生け簀まで曳航し、蓄養が行なわれる仕組みです。
巻網漁法は、漁獲の方法としては、効率がよく、一度に大量のマグロを獲ることができます。しかし、これが乱獲を引き起こしたり、獲る必要のない、他の魚や生物も一網打尽にしてしまう、といった問題にもつながります。
一本釣り漁法
最も古い歴史をもつ漁法で、長さ4~6メートルの竿を使って、漁船から釣り上げます。自動で糸を巻き上げる機械と、人間の手を使って、100キロ以上もあるマグロを引き上げ、最後は銛でえらの部分を刺して仕留める漁法です。大型のマグロになると、一匹釣り上げるのに、1~2時間もかかることがあります。
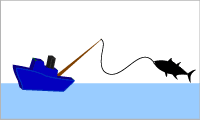
運搬について
マグロの運搬:生マグロと冷凍マグロ
海から港へ、また海外から日本へ運ばれてきた、刺身用マグロは、大きく分けて2つの販売経路で国内に流通します。一つは東京にある築地市場などの卸売市場を経由する経路(場内流通)。もう一つは、卸売市場を経由しないでマグロが売られる経路(場外流通)です。













