「持続可能なシーフード」でペンギンの海を守れ
2014/08/22
日本のちょうど反対側に位置する南米の国チリ。その南部沿岸は、多くの野生生物が息づく「命の海」です。しかし今、この海ではサケ(サーモン)養殖場の急激な増加に伴い、海洋環境への悪影響が懸念されています。WWFジャパンは、日本がチリで養殖されたサケの最大の輸入国であることから、WWFチリと協力して、この養殖業を環境や地域社会に配慮した「持続可能」な産業に転換することで、多くの野生生物が生きる海の自然を守る取り組みを行なっています。2014年7月までの活動報告をお届けします。
大事な海域はどこ? 指標種が示す豊かな海
チリ南部の沿岸に位置するチロエ島。 その周辺には、マゼランペンギンやフンボルトペンギンなどの海鳥や、オットセイ、ウミカワウソなどの海獣類、さらにはシロナガスクジラを含む大小の鯨類が集う、自然の豊かな海域が広がっています。
現在、その保全に取り組むWWFチリでは、海域内で特に重要な地域を選び、優先的に保全地域に指定するよう働きかける活動を行なっています。
この重要地域の選定は、自然環境の指標となる野生生物を数種選んで生息状況を調査し、それぞれの個体が集中しているエリアや繁殖場所を明らかにすることで行なわれます。
複数の野生生物の情報を地図上で重ね合せ、複数の鳥や野生動物が集まっている場所があれば、そこを重要エリアとする手法です。
WWFチリはまた、保護区の設置についても、人の侵入を厳しく禁じるエリアだけを作るのではなく、地域社会の住民たちが水産資源などを持続可能な形で利用できる、保全利用が可能な場所も広く設定することを目指しています。
その理由は、地域の理解と参加が無ければ、貴重な自然環境を長期的に保全してゆくことは、どうしても困難になるからです。
海の生態系の保全と、地域の暮らし・産業をいかに両立させ、持続させてゆくか。
WWFチリでは、その取り組みのカギとして、ASC(養殖管理協議会)による漁業認証を、現地の海で普及させる活動を行なっています。

マゼランペンギン
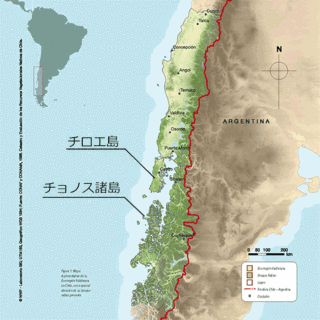
チリ南部周辺海域地図

チリ南部の海。複雑な地形が海岸線を縁どる。

養殖場

サケ
海を脅かすサケの養殖
このチリ南部の海の自然に今、大きな影響を及ぼしているのが、サケ(サーモン)の養殖です。
サケはもともとチリには生息していない魚です。それが1970年代、日本から養殖技術と共に持ち込まれ、産業化されてきました。
サケ養殖は、1990年代から盛んになり規模を急速に拡大。現在は、ギンザケやサーモントラウト、アトランティックサーモン(大西洋サケ)といった、さまざまな品種が養殖されています。
こうした養殖サケは、ほぼすべてが海外向けの輸出産品です。日本はその最大の輸出先で、ギンザケについてはその9割を輸入。日本企業の資本も、現地の養殖場に投下されています。
しかし、こうしたサケの養殖場では、糞などによる海や湖の汚染や、新しい魚の病気の伝染、その病気の伝染を防ぐために大量の薬が使用される、といった問題が生じています。
さらに、養殖場の外へサケが逃げ「外来生物」となることで、もともと存在した生態系への悪影響も懸念されています。すでに、逃げたサケはこの地域一帯で10世代ほど世代交代を繰り返しているとみられ、定着していることも確認されています。
こうした問題を解決する手段の一つは、すでに基幹産業として根付き、多くの人たちの暮らしを支えているこの養殖業を、「持続可能」なものに変革してゆくことです。
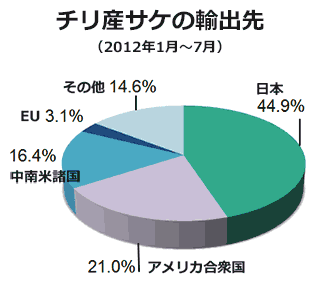

漁業も盛んに行なわれている

サーモンの養殖場
「持続可能な養殖」のカギとなるASC
そこでWWFチリとWWFジャパンでは2012年より、この海域でサケ養殖を手掛ける企業に対し、ASC(養殖管理協議会)認証を取得するよう働きかける取組みを開始しました。
ASCとは、国際的な第三者機関で、周辺の自然環境や地域社会に配慮した「持続可能な養殖業」を認証し、それが一目でわかる独自のラベルを製品につける取組みを行なっています。
このASCの基準には、水鳥などの重要な生息地周辺での操業を認めないとする条件や、サケが自然界に逃げるのを防ぐため、幼魚の育成を自然の湖で行なわないことなどが含まれています。
また、地域社会への配慮のあり方についても、労働環境の保証や、認証取得をめざす養殖業が地域住民の理解を必ず得ることも義務付けています。
つまり、このASC認証を取得するためには、その養殖業が「持続可能」なものとなることが、必然的に求められているということです。
もちろん、こうした課題を解決するのは容易なことではありません。
急激に拡大する養殖業は、チロエ島をはじめとする沿岸一帯に、外からの人の流入を引き起こし、町によっては10年で人口が3倍に膨らみ、治安や風紀の悪化などが指摘されている例もあります。
現在、サケ養殖にかかわる3つの企業がASC認証の取得を目指していますが、いずれも「地域の理解を得る」という項目では、まだ及第していません。
それでも、この3企業のASC認証取得に向けた審査は、2014年7月時点で順調に進んでいます。WWFも引き続き、地域の人の理解を得るための改善を支援しながら、最終的な認証の取得を目指していきます。

地元の海の小規模な漁業者

持続可能な養殖業の証であるASC認証のマーク

ミナミウミカワウソ

フンボルトペンギン
プロジェクトの今後に向けて
このチリと日本のWWFが協力して取り組むプロジェクトでは今後、ASC認証の取得拡大に加え、保護区を新たに設置するための活動を強化していく予定です。
マゼランペンギンを含めた、海の環境の指標となる海鳥や、海獣類、シロナガスクジラなどの調査、さらにすでに設置されている保護区での現状調査が、その基礎となる取り組みです。
またチロエ島では、サケ養殖場の拡大に伴い、サケの加工プラントと、それが必要とする電力の増加をまかなうため、風力発電所の建設も計画されていますが、これがフラミンゴなどの渡り鳥が通るコース上にあることから、そうした計画の見直しなども、課題となる見込みです。
地域の人たちとの協力については、ASCとサケ養殖についての普及活動のほか、すでに小規模で始められている、海鳥やイルカを目玉にしたエコツアーへの支援も行ない、地域経済の自立と、持続可能な暮らしの確立を目指してゆきます。
外からやってきた企業などが、その場所にある自然や恵みを一方的に利用し、保護するのではなく、いかに地域が主体となって取り組むか。
それを追求しながら、保護区の設置、そしてASCの普及を進めて、海の自然と人の暮らしを守るために、WWFは引き続きチリ南部沿岸でのプロジェクトを推進してゆきます。

チロエ島内陸部。こうした場所にも鳥たちがやってくる

地元のおばさん。地域の保護区を管理している

自然保護と漁業の両立はできるのか。チリの海では挑戦が続く。












