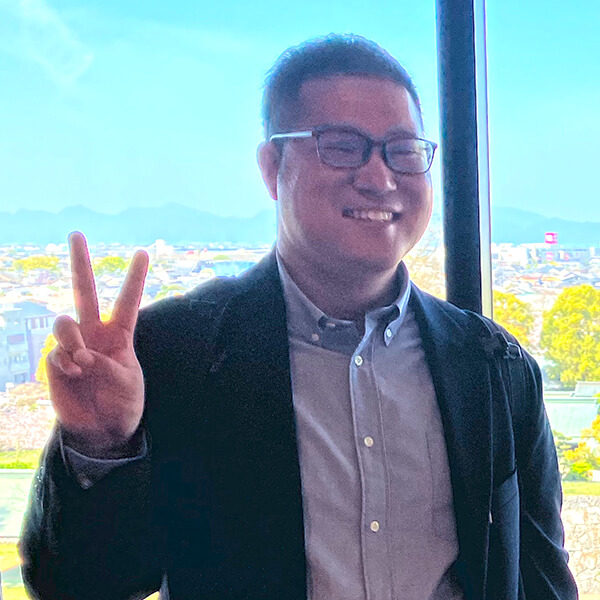Interview 卒業生インタビュー株式会社エーゼログループ
Seminar ゼミ
(1)「プラスチックをめぐるサーキュラーデザインと実装」ゼミ
プラスチックの大量生産・消費・廃棄に起因する問題が、脱炭素社会の実現、生物多様性の回復を阻害し、人の健康をも脅かしています。2040年までに世界のプラスチックの生産量は2倍に増加し、海洋への流出量も3倍になると推定されています。
メンター
採択者
Asuka
石井 明日夏
TERRANAUT#サーキュラーエコノミー #消費行動 #シュノーケリング
プロフィール
Kodai
加藤 広大
amu株式会社#アップサイクル #サーキュラーエコノミー #拡張家族
プロフィール
Yudai
松尾 雄大
BORDERLESS SENEGAL SARL#プラスチック #アップサイクル #まちづくり
プロフィール
Natsuka
村上 捺香
鯖江市地域おこし協力隊#廃材 #資源循環 #ものづくり
プロフィール
Erika
松本 恵里佳
#環境 #食 #デザイン
プロフィール
(2)「自然と調和した地域づくり」ゼミ
森、海、川、里山、草原、湿地など豊かな自然を基盤として私たちの社会・経済は築かれています。そういった自然資本と密接に結び付く農業・漁業・林業・観光業などを通し、自然と調和した持続可能な地域づくりが求められています。
メンター
採択者
Arisa
新庄 ありさ
AMAホールディングス株式会社#海 #共創 #タグボート
プロフィール
Gento
三枝 弦人
農林水産省#トランスフォーマティブ・イノベーション政策 #プラネタリーヘルス #消費者の行動変容
プロフィール
Haruyuki
太刀川 晴之
株式会社エーゼログループ#生物多様性 #里山 #ビオトープ
プロフィール
Haru
向山 遥温
特定非営利活動法人夢ノ森伴走者CUE#絆 #平和 #まちづくり
プロフィール
Tatsurou
森本 達郎
森庄銘木産業株式会社#森 #地方創生 #カーボンニュートラル
プロフィール
(3)「サステナブルビジネスとイノベーション」ゼミ
サステナブルな社会を築くために、食・住まい・衣料・へルスケア・エネルギー・インフラ・ファイナンス・スポーツ・娯楽など、私たちの暮らしに関わるあらゆる領域において、システムチェンジが求められています。
メンター
採択者
Oji
赤石 旺之
株式会社Wildlife Ventures#野⽣動物 #⽣物多様性 #アフリカ
プロフィール
Katsuki
大西 克直
合同会社秋田里山デザイン#サプライチェーン #アグロフォレストリー #ダイレクトトレード
プロフィール
Ryosuke
橘木 良祐
Molt#昆虫 #魚 #養殖
プロフィール
Daichi
波崎 大知
JINEN株式会社#Regeneration #Travel #AI
プロフィール
Yuya
村上 雄哉
福井県立大学#釣り#食#自然
プロフィール
Takuya Hasegawa
長谷川 琢也
LINEヤフー株式会社
東日本大震災の後、被災地の農産物などをネット販売する企画を立ち上げたことをきっかけに、宮城県石巻市に移住。地域を活性化させ、次の世代に続く水産業を実現するため、地元の若手漁師と共にフィッシャーマン・ジャパンを立ち上げ、水産業のイメージを「カッコよく」「稼げて」「革新的な」という「新3K」に変えていくことを目指している。
Daisuke Hara
原 大祐
Co.Lab 代表取締役
1978年生まれ。神奈川県大磯町在住。漁村農村お屋敷まちが混在する大磯に惹かれ、地域資産をいかした暮らしづくりを実践中。地域のインキュベーション(県下最大の朝市「大磯市」の運営)、6次産業化(漁協直営の食堂プロデュース、加工場の運営)、里山再生(コミュニティ農園「大磯農園」の運営)、空き家空き店舗再生(カフェ、立ち飲み、本屋、雑貨店運営)、働き方改革(森のようちえん併設コワーキングスペース 「Post-CoWork」の運営)などローカルエコシステムの再構築に取り組んでいる。
Takashi Uemura
上村 崇
epiST株式会社 代表取締役社長/CEO
005年、AI・データサイエンスをコアとする株式会社ALBERTを創業、代表取締役社長に就任。
Asuka Ishii
石井 明日夏
TERRANAUT#サーキュラーエコノミー #消費行動 #シュノーケリング
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要廃棄物の環境インパクト可視化サービス
Kodai Kato
加藤 広大
amu株式会社#アップサイクル #サーキュラーエコノミー #拡張家族
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要漁師の魂の価値化 廃漁網アップサイクル素材amuca
Yudai Matsuo
松尾 雄大
BORDERLESS SENEGAL SARL#プラスチック #アップサイクル #まちづくり
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要セネガルにおける廃プラスチックのアップサイクルブロックの製造販売事業
Natsuka Murakami
村上 捺香
鯖江市地域おこし協力隊#廃材 #資源循環 #ものづくり
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要福井鯖江からはじめる、廃材見える化事業「廃材商人」
Erika Matsumoto
松本 恵里佳
#環境 #食 #デザイン
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要PRECIOUS PLASTIC KYOTOを環境教育とアップサイクルイノベーション拠点へ
Arisa Shinsho
新庄 ありさ
AMAホールディングス株式会社#海 #共創 #タグボート
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要シン・ブルーオーシャン戦略
Gento Saegusa
三枝 弦人
農林水産省#トランスフォーマティブ・イノベーション政策 #プラネタリーヘルス #消費者の行動変容
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要プラネタリーヘルスダイエット〜食卓からはじまるフードシステムの再創造〜
Haruyuki Tachikawa
太刀川 晴之
株式会社エーゼログループ#生物多様性 #里山 #ビオトープ
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要ビオ⽥んぼプロジェクト
Haru Mukoyama
向山 遥温
特定非営利活動法人夢ノ森伴走者CUE#絆 #平和 #まちづくり
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要次世代の、次世代による、次世代のための「絆育む蜜源の森構想」~揺るがない価値を里山に~
Tatsurou Morimoto
森本 達郎
森庄銘木産業株式会社#森 #地方創生 #カーボンニュートラル
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要森林カルテ
Oji Akaishi
赤石 旺之
株式会社Wildlife Ventures#野⽣動物 #⽣物多様性 #アフリカ
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要ケニアで⼈とゾウの軋轢を解決する養蜂事業
Katsuki Onishi
大西 克直
合同会社秋田里山デザイン#サプライチェーン #アグロフォレストリー #ダイレクトトレード
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要コーヒー生産の森林栽培・付加価値向上の支援による、持続可能なグローバルバリューチェーン創出事業
Ryosuke Tachibanaki
橘木 良祐
Molt#昆虫 #魚 #養殖
■自己紹介/経歴
九州工業大学生命情報工学科卒。カエルの衝突回避行動を研究
どんな仕事も長続きせず、人生に思い悩む
宮崎県椎葉村にて、キャビアの養殖・加工を担い、養殖の奥深さを知る
カンボジアに移住し、昆虫ベンチャーで、コオロギの研究開発を担う
アメリカミズアブの飼料事業を立ち上げ中
■事業タイトル/概要食品廃棄物を飼料や肥料にアップサイクルするカンボジアでのサステナブルなアメリカミズアブ養殖事業
Daichi Hasaki
波崎 大知
JINEN株式会社#Regeneration #Travel #AI
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要STAY.EARTH
Yuya Murakami
村上 雄哉
福井県立大学#釣り#食#自然
■自己紹介/経歴
■事業タイトル/概要淡水養殖のための昆虫飼料
Group Session 集合セッション
キックオフ
環境課題をとりまく現状や6か月間のプログラムのロードマップを確認しました。詳しくはこちら
中間セッション
メンター陣との個別メンタリングを通し、課題の確認と残り3か月のアクションプランの発表を行いました。詳しくはこちら
ファイナルセッション
6か月の締めくくりとして、事業モデルを振り返りながら、環境課題解決に向けた今後の取り組みと決意を発表しました。詳しくはこちら
Input Session インプットセッション
実施講義
「ToC(Theory of Change)講義」WWFジャパン自然保護室長
「WWFジャパン事例紹介:国内森林プロジェクト」WWFジャパン森林グループオフィサー
「生物多様性保全で起業をするという選択」株式会社バイオーム 藤木庄五郎氏
「WWFジャパン事例紹介:海の生物多様性と持続可能な水産業の価値」WWFジャパン海洋水産グループ長
「共感を呼ぶパーパスブランディング」Accenture Song Droga5 Tokyo
「生物多様性市場の創出に向けて」株式会社シンク・ネイチャー代表取締役 琉球大学教授 久保田康裕氏
Fieldwork フィールドワーク
WWF ジャパンが長年地域に根差した保全活動を実践してきた、沖縄県石垣島の白保を訪問しました。実施報告はこちら から御覧ください。