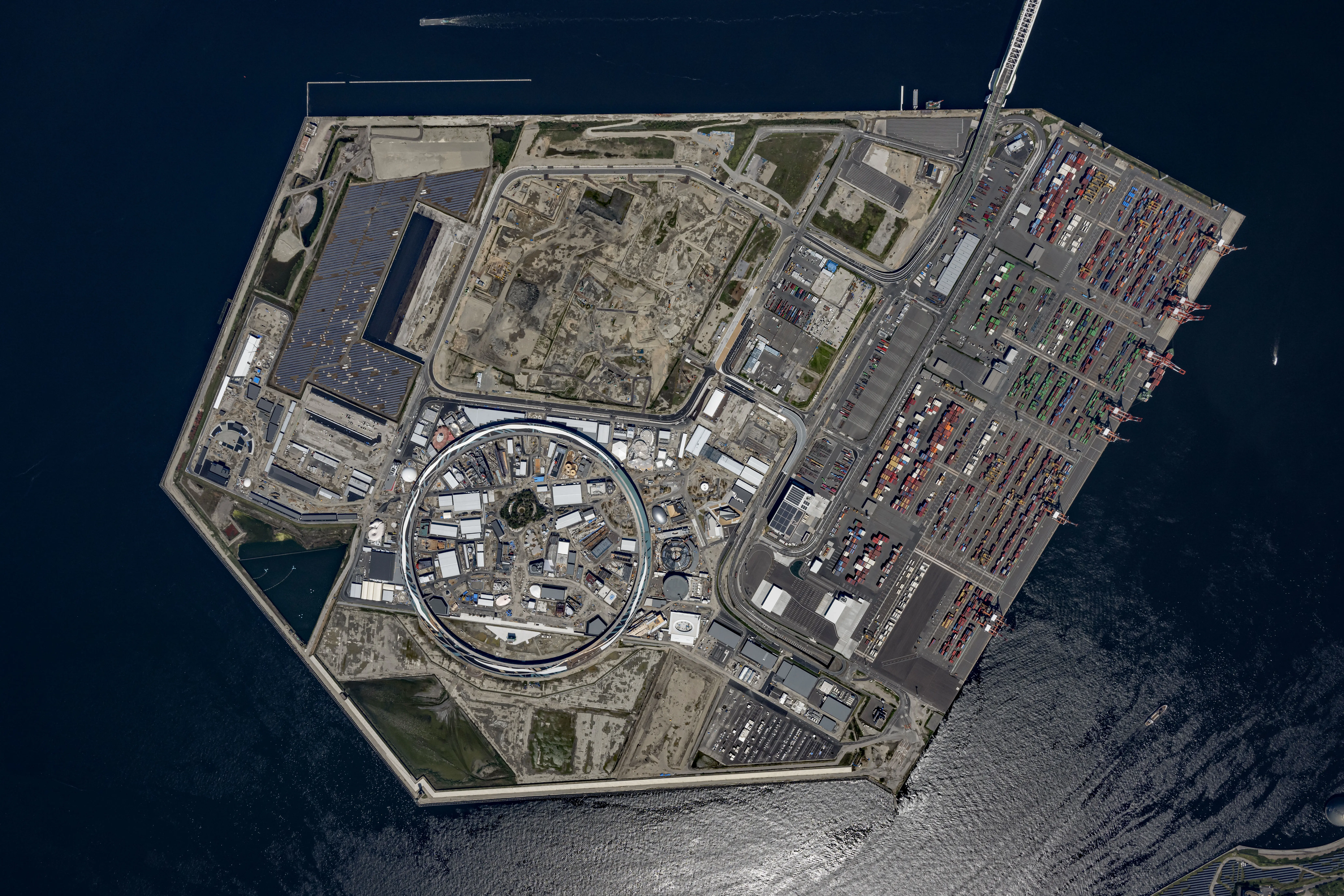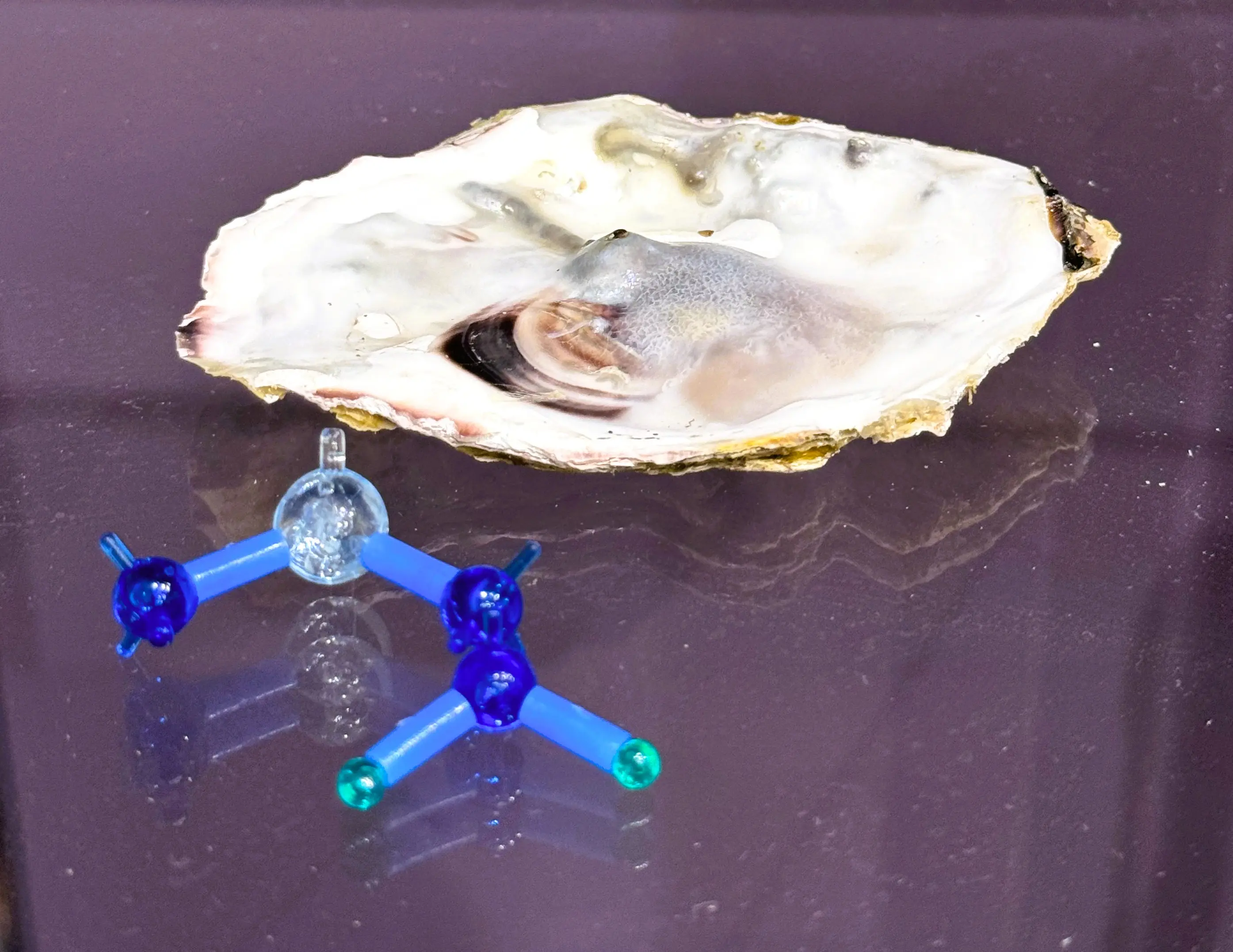【COP19/CMP9】国連気候変動ワルシャワ会議、閉幕
2013/11/27
11月11日から2週間の会期で開催されていたポーランド・ワルシャワでの国連気候変動会議(COP19・COP/MOP9)は、会期をさらに1日延長した23日土曜日の夜にようやく終了しました。今回のCOP19は、各国の2020年までの取り組みの底上げをはかる一方、2020年以降の新しい国際枠組みに向けて、明確な道筋を描けるかどうかが今回の会議の大きな焦点でした。
(*2020年以降の新しい国際枠組みは2015年に合意することになっているため、2015年合意と呼ばれる)
主な結果
2020年までの取り組みの底上げについては、残念ながら望まれたような具体的な決定はありませんでしたが、WWFが期待していたAOSIS(Alliance of Small Island States;小島嶼国連合)の提案が部分的に取り入れられ、希望が残りました。他方、2015年合意へ向けた道筋は、焦点である目標の決定方法について「事前協議型の目標決定方式」を前提として、目標案を先に国連に提示するという形が見えてきたことは一つの成果として挙げられます。しかし肝心な国別目標案の提示時期は極めて曖昧な時間軸の設定となり、さらに具体的な事前協議についても決められず、多くの課題を残しました。
議長国であるポーランドは、そのエネルギー源の多くを石炭に依存していることから、石炭の活用を議論する「国際石炭・気候サミット」を、COP期間中にわざわざ開催することを決めているなど、議長国自体の姿勢に市民社会から疑問の声が挙がっていました。
また、会期中の第1週目に、日本やオーストラリアが目標を後退させるという発表を相次いで行い、「削減努力の底上げを」という議論に水を差す結果となりました。特に日本は、AOSIS、イギリス、EUなどの政府から公式に懸念を表明され、国際メディアにもその後退が大きく報道されるなど、悪い意味で存在感を示すことになってしまった会議でした。
この会議の注目点を、以下の3つのトピックに絞って、議論と成果について報告します。
- 2020年の削減努力の底上げと2015年合意への道筋
- 気候変動による「損失と被害(Loss and Damage)」に関する国際メカニズムの設立
- 途上国に対する長期的な資金支援に関する議論
2020年の削減努力の底上げと2015年合意への道筋

現在の気候変動に関する国際交渉で一番の主要な論点は、2020年以降の新たな温暖化対策の枠組みに向けた議論の進展と、2020年までの取り組みを加速することです。COPの議題の中で特に重要なものには特別作業部会が作られて議論が進められるのが常なので、これら二つの議題について、2011年に南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17でダーバンプラットフォーム特別作業部会(以降ADPと呼ぶ)が設立されて、議論が進められてきました。ワークストリーム1では、2020年以降の新たな温暖化対策の枠組みについて、ワークストリーム2では、2020年までの取り組みの強化について話し合われています。
ワークストリーム1の2020年以降の議論においては、新枠組みの中身について議論され、特に目標の決定方法と、新枠組みの構成要素について、集中して議論が行われました。一方、ワークストリーム2の2020年までの取り組み強化においては、交渉で各国の2020年目標を引き上げることが政治的に困難である中、いかに実質的に削減努力の底上げを図れるかが議論されました。中でも特筆すべきは省エネルギーと再生可能エネルギー(以降再エネと呼ぶ)の技術と政策推進の決定です。以下に分けて説明していきます。
1.1. 2020年以降の新枠組み議論について(ワークストリーム1)
1.1.1. 新枠組みの排出削減目標について:「事前協議型の目標決定方式」


新枠組みの中心となる削減目標については、「各国が国内で決定した目標案を国連に提示する。最終的に決める前に、お互いの目標案を国際的に事前協議し、(可能ならば)目標案を見直してから、最終決定していく」という形を多くの国が前提としていることが共通認識となりました。いわば「事前協議型の目標決定方式」です。この事前協議の場で、国際的に比較・検証する中で、理想的には2度未満達成目標との妥当性や、先進国と途上国間の衡平性を検討していくプロセスが確保されれば、より野心度の高い全体目標となっていくことが可能となる方式です。この「事前協議型の目標決定方式」を暗黙裡に前提として、目標案を先に国連の場で提示するという形が合意されたことは一つの成果として挙げられます。
ちなみにこの事前協議型の目標決定方式は、2013年の3月にアメリカが提案し、その後に欧州連合や日本、ブラジルなど一部の途上国も同じような提案を出して、共通認識となったものです。本来は産業革命前に比べて2℃未満に抑えるために必要となる削減量はわかっているわけですから、それを各国に配分していくという形が最も望ましいのですが、今の政治情勢では非常に困難であるため、次善の策として浮上しました。目標の提示時期や事前協議の内容については各国間で意見の差があるため、今回のCOP19で激しい交渉が行われました。交渉は2つに絞られます。まず1つは、国別目標案を国連に提示する時期です。そしてもう1つは事前協議に関する取り決めについてです。
1.1.1.1. 国別目標案について
時期を明示しようとするEUやLDC(Least Developed Countries;後発開発途上国)グループ、AILAC(Independent Alliance of Latin American Countries;先進的なラテンアメリカ6か国グループ )に対して、インド・中国などが属するLMDC(Like-minded Developing Countries;同じ考えを持つ途上国グループ)が「まずは先進国が2020年までの削減努力を深堀りするべきだ。その努力不足を2020年以降の枠組みで途上国に押し付けるのは許せない。提示時期の明示は先進国だけでよい」と激しく対立しました 。
結局「COP21のかなり前に提示することを招聘する」となり、きわめて曖昧な表現になってしまいました。ただし「準備のある国は2015年第一四半期までに出す」という表現が括弧書きで付け加えられています。しかしそれでも世界各国にとっては2014年1年間+2015年前半という短い期間で、国内における2015年合意の国別目標案(おそらく2030年ごろの目標?)を決める作業を加速(日本においては開始)しなければならないことは明白になっています。
また目標を指し示す言葉として、「目標」(target)や「約束」(commitment)という法的拘束力を連想させる強い言葉ではなく、「貢献」(contribution)というやや弱い言葉が使われることになりました。この背景には、新枠組みではすべての国を対象とするのだから、目標は同じ言葉であるべきとする先進国(と一部の先進的な途上国)に対して、途上国の削減努力は先進国の義務的な努力とは違うとする新興途上国との強い対立があります。しかし、「貢献」という言葉になったからといって、先進国が国全体の数値目標以外の形式で目標を持つことは、現在の国際交渉の場ではほぼ想定され得ません。
1.1.1.2 事前協議について

この「事前協議型の目標決定方式」においては、目標案を提出した後にどのような協議を行うかが、新枠組みの目標の野心度を決めることになります。もともとこの方式を提案したアメリカは、目標案の内容の明確化と透明性を掲げています。「明確な目標案を提出して、比較可能性を高め、究極のゴールから照らしあわせて各国の目標案レベルがどの程度妥当かということを見ていく。結果として足りないということがわかるならば、国際的なピアレビューの圧力で各国が見直すこともありうる(ただしそれは各国の裁量)」ということで、主に目標案の明確化と透明性を念頭に置いています。一方途上国グループの中で特に温暖化の影響に脆弱なアフリカグループは、この事前協議に「科学から見た妥当性、歴史的責任を鑑みた衡平性」の概念を入れて行うべきと主張し、2週目の最初に出されたADPの共同議長の決定文書案には、「妥当性・衡平性・同等性公平性を考慮するためにして」事前協議を行うという文言が入りました。
また、続く共同議長案では、目標案を検討するプロセスへの言及、さらには衡平性に関するワークショップを2014年6月の補助機関会合で開催して議論を進めるというプロセスが入っていました。会議ではEUなどの先進国もこの衡平性のワークショップ開催に賛同していました。ところが、インド・中国を中心とする途上国グループLMDCが強くこれに反対し、結局最終の決定文書からは、この衡平性への言及もワークショップも落とされてしまったのです。最終決定文書では、出された目標案について「明確化や透明性をはかることができるように」という文言だけになってしまっています。
今回の会議の決定そのものには、事前協議の具体的な文言はありません。しかし、少なくとも、目標案を事前に提出する方向で議論が進んでいることを踏まえると、事前協議を行うことが前提で交渉は進んでいるといえます。
結論として事前協議については、今の段階では目標案の明確化や透明性をはかることはほぼ共通認識となりましたが、本来必要である「科学から照らし合わせた妥当性や、各国間の衡平性」などの議論ができるかどうかが未知数ということになります。
なお、目標が、どの温室効果ガスを対象とするのか、総量なのか原単位なのか、森林吸収分を含むのかなどの内容については、今回では規定するような項目は入りませんでしたが、2014年のCOP20において削減目標に関して出すべき情報を決めることが要求されています。
- ※ 1 AILACの名称は、日本語に普通に訳すと「独立中南米カリビアン諸国連合」となります。
2 *途上国グループの対立構造の説明は後述。
1.1.2.新枠組みに入るべき要素について

目標と並んで重要な事項が、新枠組みに入る構成要素が何になるのかを決めていくことです。2015年に合意するためには、遅くとも2015年6月までには決定文書のドラフトが出来上がっていなければ間に合わないため、骨組みとなる構成要素について議論を前進できるかどうかも、今回の会議の目指された成果でした。2012年のCOP18の決定において、構成要素については2014年のCOP20において本格的な議論がなされることになっており、今回はそのための下準備となる議論が必要でした。
共同議長の努力で2週目の最初に出てきた決定文書のドラフトには、附属書として、"例示的な構成要素"が並べられていたのですが、ノルウェーやAILACが賛成したほかは、先進国・途上国がこぞって反対し、2回目の決定文書ドラフトからは姿を消し、ランクを下げてADPの結論文書の付属書に落とされたのです。さらに強硬な反対が相次ぎ、日本も「共同議長の会議ノートのような形で残すだけでよいのではないか」と後ろ向きな発言。とうとう最終の決定文書にもADPの結論文書からも姿を消してしまいました。ただ2014年3月から行われる最初の会合から、構成要素について詳細に検討していくことになっています。また非常に弱い表現ながら、「2015年の5月までに交渉文書案が出来上がっていることを目指す」ということも前回のカタール・ドーハでのCOP18決定文書の前文の中に入っているため、最低限まだ間に合う作業計画は入っているといえます。
この構成要素の交渉では、先進国と中国・インドなどの途上国グループLMDCが期せずして手を組んで同じ主張を行う形となり、AILACやLDCなどの途上国グループと対立したのが印象的でした。
1.2. 2020年までの取り組みの強化について(ワークストリーム2):
特筆すべき進展は、再エネと省エネ政策&技術の推進提案

2020年までの取り組みの強化については、唯一の進展とよべるものは、小島嶼国連合が提案した「再生可能エネルギーと省エネルギーの政策&技術推進」です。これは2020年の各国の目標を引き上げようとしても、現状の膠着した状態では政治的に非常に困難なので、せめて目標引き上げに間接的につながる可能性のある再エネと省エネ政策と技術の推進を、国際的に促そうというものです。これは、もともとAOSIS(小島嶼国連合)からの提案です。各国の思惑で、対象が再エネと省エネに限らず「削減可能性の高い行動(機会)」全部となって、焦点が薄められた感はありますが、なんとか政策&技術の検討と導入促進を図るプロセスには合意することができました。この議論も小島嶼国連合という途上国からの提案にもかかわらず、LMDC「同じ考えを持つ途上国グループ」が反対し、一方EUやアメリカ・日本は賛同を表明するという、途上国・先進国が入り乱れた対立構造が見られました。
世界の勢力地図が塗り替わって、温暖化交渉における各国の思惑も従来とは大きく変化していることを実感する交渉ともなりました。
1.3.対立の構造的変換

これまでの交渉は、歴史的に排出責任のある先進国に対して、資金援助を求める途上国というのが伝統的な対立軸でしたが、今回特に鮮明になったのが、途上国グループの中で意見の統一がもはや不可能となり、途上国同士での対立が鮮明になったことです。気候変動枠組条約が採択された1990年代に比べて、中国・インドなど新興国が急速に発展し、途上国の中でも開発程度に大きな差が生まれていることを背景に、これら新興国やベネズエラ、サウジアラビア、フィリピン等を中心に「同じ考えを持つ途上国」(LMDC)という新たなグループが形造られ、活発に発言するようになりました。これらの国々がとる立場は、先進国の責任を明確化することに大きな主眼があり、その姿勢は時として教条的にすら写ります。これに対し、途上国の中でも、側のコロンビアをはじめとする先進的なラテンアメリカ6か国グループ(AILAC)、それに後発開発途上国グループ(LDC)は、総じて交渉の進展を目指しており、公にLMDCグループと激しくぶつかるようになったのです。特に交渉の最後の局面では、EUが、AILACやLDCとともに少しでも交渉の進展をとらえようと粘るのに対し、LMDCが強く反対し、結果として進展をはばんでしまったことが印象に残りました。
なぜLMDCがこのような消極的な交渉態度だったかについては、3つのことが考えられます。まずLMDCの構成国を見ると、利害の違うグループが同床異夢で協働しているのがみてとれます。中国・インドなどの開発著しい新興国、もともと交渉の進展を好ましく思わない産油国、それにラテンアメリカの反市場主義国で原則を重んじる国々、それに温暖化の影響に非常に脆弱で危機感の強いフィリピンなどの構成となっているのです。これら非常に多様な国々が、思惑が違いながら期せずして利害が一致して同じ行動をとっていることがわかります。
共通するのは、まず先進国の2020年削減目標の低さに強い危機感を抱いていることで、すべての国を対象とする2020年以降の枠組みにおいて、途上国に先進国の2020年までの努力不足分まで責任を押し付けられると反発していることが一番大きな理由です。

2013年9月に発表されたIPCCの第5次評価報告書は、2度未満を達成するためには今後大気中に排出できる量には限りがあることを明確に示しました。それによると今のままの排出を続けたら、あと30年以内に2度未満を超えてしまう排出量に達してしまいます。2020年までの先進国の削減量不足は、のちの新枠組みにおいてより大きな削減を果たさなければならないことを意味するのです。したがってLMDCグループは、まず先進国が2020年までの削減量を全体として40%にすることを強く要求し、そのことが議論されないまま、途上国も対象とする2020年以降の枠組みだけの議論を進めることは許さない、という主張です。特に今回は日本やオーストラリアの目標の後退がLMDCグループの消極的な交渉態度に口実を与えた点は否めません。

しかしもう一つの理由として、特に排出を急増させている新興国が、2020年以降のすべての国を対象とする枠組みにおいて、自らに国際社会からかかってくる削減努力へのプレッシャーを警戒しているという点も大きいと思います。そのため1990年当時の附属書1国(先進国)、非附属書1国(途上国)という区分を、2020年以降も継続させていくべきという強い主張を繰り返しました。今回ブラジルが提出した「歴史的排出量への各国寄与分を算定する方法論をIPCCに依頼し、国別目標案の策定の際の参照指標とする」という提案を強く支持して、歴史的責任のみを強調していたのもその一環だと思われます。もちろん歴史的責任は、新目標案を策定する際に考慮するべき大きな柱であり、事前協議にはあるべき項目ではありますが、これのみが事前協議の指標という主張は、他の国々には受け入れられるものではありません。事前協議にはほかにも科学との妥当性や、衡平性、比較可能性など様々な指標が議論されている最中です。特に、もともと衡平性の概念導入をCOP17(2011年、カンクン合意)で最後まで強く要求していたインドが、今回のCOP19では、衡平性を議論するワークショップ開催の作業計画にまで反対したのは、解せない行動でした。先進国と途上国の差異化は当然2020年以降の新枠組みでも必要であることに疑念を抱く国はないと思いますが、1990年当時と大きく変わっている世界の情勢を反映して、差異化も進化させていく必要があると思います。それを1990年当時のままに留めようとする主張は、交渉の進展を阻むものであり、今後のLMDCグループにとって再考すべき大きな課題と言えるでしょう。
一方、今回特に鮮明になってきた交渉の進展に前向きな途上国グループの存在は、暗くなりがちな温暖化交渉の中における希望の星と言えそうです。もともと温暖化の影響に脆弱で、開発が遅れているがゆえに自らの排出量は少ない後発開発途上国グループや小島嶼国連合は、交渉の進展に前から寄与している面がありましたが、ちょうど中間途上国の中で、声を上げ始めたラテンアメリカ6か国グループAILACは、特に今回交渉のダイナミズムが変化してきていることを象徴していたように思います。印象的だったのが、LMDCが「共通だが差異ある責任原則」をたてに先進国と途上国の1990年当時の差異化を固定化することを主張するのに対し、AILACは「共通だが差異ある責任原則は、交渉の進展を妨げるために使うものでなく、交渉を前に進めるためにこそある。先進国と途上国の差異化は当然必要だが、時代と共に進化させる必要がある」と発言していたことです。AILACが結成されたのは2012年からですが、なぜ積極性を見せ始めたかについては、まず2014年のCOP20のホスト国ペルーの存在が挙げられます。COP20の成功を願っての積極性ということです。さらにボリビアやベネズエラといったLMDCに参加している反市場主義のラテンアメリカ諸国と違って、資本主義を取り入れて発展している国々である点も挙げられます。また2010年に結成された「野心的な行動のためのカルタヘナ・グループ」の出身であることも一因と思われます。このカルタヘナ・グループというのは、国連の交渉グループではなく、先進国・途上国の枠を超えて温暖化交渉の進展を議論する非公式のグループで、EUやイギリス、ドイツといった先進国とAILACグループ、AOSISの一部が一緒になってこれまで数回会合を開いて、先進的な議論を重ねてきたと伝えられます。その影響を受けていることもあるでしょう。様々な地政学的な分析が必要ですが、途上国の中で力をつけはじめた中間途上国が積極的な声を上げ始めたことは、今後の交渉の明るい光と言えるでしょう。
1.4. 国際交渉の予定まとめと今後の課題

今後の国際交渉の予定をまとめると図のようになります。結論として、「事前協議型の目標決定方式」を前提として、目標案を先に提示することが弱いながらも入り、新枠組みの要素については、2014年早々から議論を加速し、2015年5月ごろには交渉文書案を目指すことになっています。いわば、非常に弱いながらも2015年に合意するための必要最低限の作業計画は今回のCOP19決定に入っていると言えます。課題はこれらの実行について「要請、招聘」するなどの弱い言葉に留まっている点で、実際に一つ一つ進めていけるかどうかが勝負となります。
今後のADPの課題としては、2020年までの取り組み強化(ワークストリーム2)においては、省エネ、再エネを中心に各国の削減の取り組みを促進する専門家プロセスを発展させて、いかに具体的な削減・適応の取り組みの底上げにつなげるか、そして2014年にある国連気候サミットの場や、大臣級レベルの会合を最大限に活用して、首脳レベルの関与で削減取り組みの底上げをはかれるかにあります。
一方、2020年以降の枠組み作り(ワークストリーム1)においては、目標案の提示のあとに行う事前協議について、妥当性や衡平性を踏まえた目標の見直しの可能性を含んだ事前協議の確保ができるかが最も大きな課題です。この事前協議において何を行うかによって、事前に提示する国別目標案が、単にカンクン合意のように自主的な目標を発表するだけに近い形になってしまうのか、それとも科学との妥当性などを見ながら交渉して高めていけるかの分かれ道になります。遅くとも2014年のCOP20において合意する必要があると思います。
そして、2015年合意の構成要素については、2014年中になるべく早く要素に合意し、遅くとも2015年5月までには交渉文書ができあがるように進めていけるかが大切です。
上記国際交渉を踏まえての今後の日本の課題としては、暫定値である2020年目標の見直しの議論を国内で早急に進め、省エネ、再エネなどの可能性を最大限に活かした目標へと速やかに更新することがあげられます。特に2014年9月にあるバンキムン潘基文事務総長の気候サミットに首脳が参加する際は、野心的な目標へと変更したことを発表する場として最高の舞台になると考えられます。
同時に、今の国際交渉では、2020年以降の新枠組みに提示する目標案(2030年ごろ)を遅くとも2015年の早いうちに国連に提示することを国内でも強く認識する必要があります。実はあと1年半しかありません。(2013年12月段階)。まだ全く2030年に向けての削減目標案の議論が始まっていない現在、早急に議論を開始し、日本として世界の温暖化対策に貢献していく姿勢を見せる必要があります。これは、日本にとって関心の高い中国やインドに削減努力を促すためにも不可欠で、自らがまず国内削減をすることを示さなければ、「歴史的責任のある先進国のリードがない」という理由で新興国が動かない口実をいつまでも与えることにもつながってしまいます。日本が2030年に国内においてどの程度の削減努力を行うのか、あと1年半でしっかりと決めていくことが大切です。
2.「損失と被害」に関する国際的なメカニズムの設立
2-2.「損失と被害」とは?
昨年のカタール・ドーハでのCOP18において、「損失と被害」に関する国際的なメカニズムをCOP19で設立することが決まっていました。
「損失と被害」とは、気候変動の緩和対策(排出量削減対策)や適応対策(影響に対応する対策)を行ったとしても、どうしても発生してしまう気候変動影響によって発生する「損失と被害」に対して、どのように対応するのかを議論する分野です。
具体的には、異常気象等による被害や、海面上昇に伴う土地の消失・移住・コミュニティの崩壊、生物種の絶滅など、「適応」しきれる範囲を超えて発生してしまう損失と被害が念頭に置かれています。
2-3.「損失と被害のためのワルシャワ国際メカニズム」の設立
現状、既に気候変動枠組条約の下では「適応」対策を進めるための仕組みは存在しますが、こうした「適応を超えたところ」で発生する「損失や被害」に対応するための仕組みは存在しません。
このため、その仕組みを設立するべきだというのが、海面上昇などの脅威にさらされる島嶼国を中心に強い主張として途上国側から挙がっていました。
しかし、実際に発生した損失と被害を、気候変動に関係しているものとそうでないものとに区分するのは難しく、ともすれば何についても、資金支援を要求される事態になってしまうことを先進国は懸念し、この国際メカニズムの設立に躊躇していました。
ただし、前述したように、国際メカニズムを今回設立すること自体は、昨年のカタール・ドーハでのCOP18の決定で予定として決まっていました。その中で、1つ大きな議論となったのは、「損失と被害」に関する国際メカニズムを、気候変動影響への「適応(adaptation)」とは別分野として設立するか、それとも、既存の適応の仕組みの下におくのかという争点で、途上国と先進国の意見が分かれました。途上国は、国際メカニズムを適応とは独立した分野として設立することを主張し、先進国は適応の延長線上にあるものであると主張しました。途上国側としては、独立した分野として設立することで、「適応の一分野」として埋没して扱いが曖昧になることを恐れ、先進国の側としては、むやみに新しい仕組みを設立することを嫌って、作るとしても適応の下に設立するべきであると主張しました。
他の分野の交渉に時間がかかったこともあり、交渉は最終日までもつれこみましたが、最終的には、「損失と被害に関するワルシャワ国際メカニズム設立」(以下、「ワルシャワ国際メカニズム」)が最終的に合意されました。
位置づけは、途上国と先進国の意見対立を反映し、やや複雑な入れ子構造となりました。
まず、国際メカニズムそのものは、2010年に合意された「カンクン適応枠組み(CAF)」の下で設立されるという内容になりました。これには、COP22(2016年開催予定)において見直しをすることが条件となったことで、最後は途上国側も合意をしました。ここだけを見れば、ワルシャワ国際メカニズムは、「適応」の下に位置づけられたと言えます。しかし、実はそう単純でもありません。その理由は、次節で説明する「執行委員会」の位置づけがあるためです。
2-4. 執行委員会(executive committee)の設立
ワルシャワ国際メカニズムの運用を実際に担う機関として、執行委員会の設立も決められました。ただし、その設立のあり方は、上述のような対立を反映して、位置づけがやや複雑になっています。
- ワルシャワ国際メカニズムそのものは、カンクン適応枠組みの下に置かれる。
- しかし、同メカニズムの執行委員会は、COPからガイダンスを受け、説明責任もCOPに対して負う。
- 年次報告書は、補助機関(SBSTA/SBI)を通じて、COPに対して提出。
- 執行委員会のメンバーは、以下の既存組織から2名ずつで構成され、先進国・途上国のバランスをとる。メンバーが出るのは、適応委員会、後発開発途上国専門家グループ(LEG)、資金に関する常設委員会(Standing Committee)、技術執行委員会(Technology Executive Committee)、 非附属書I国の国別報告書に関する専門家諮問グループ(CGE)。ただし、これは暫定措置。
このように、執行委員会そのものは、COPに対して直接的に報告をする形となっています。カンクン適応枠組みの下には、適応を扱う適応委員会(Adaptation Committee)も設立されていますが、損失と被害の執行委員会は、組織上の位置づけとしては、適応委員会とほぼ同等の位置づけになるということになります。損失と被害の位置づけが最も低いパターンとしては、適応委員会が扱う一分野とするという可能性もありえたことと比較すれば、途上国側の意見も取り入れた形での決定となっていると言えます。
2-5. ワルシャワ国際メカニズムの機能
ワルシャワ国際メカニズムは、執行委員会によって主に運用されますが、以下の3つの機能が設定されました。
- 損失と被害に関する包括的なリスク管理手法に関する知識と理解の強化
- ステークホルダー間の対話・調整・一貫性・シナジーの促進
- 対策活動と支援の強化
COP決定にはそれぞれについて、もう少し詳しい内容の記載がありますが、具体的に何をしていくかについては、今後決まっていくことになります。COP決定では2014年3月までに最初の執行委員会会合が開催されることになっており、その場で、2年間の作業計画案を策定し、2014年のCOP20の場で決める予定となりました。執行委員会の具体的な手続き等も同時並行で議論がされ、やはりCOP20で決定がされることとなりました。
2-6. 「損失と被害」に適切に対応していくために
「損失と被害」の議論については、時として「新しい資金援助の項目」という風にとらえられがちです。無論、資金支援は「損失と被害」に対する対応の重要な要素ではありますが、それだけにこのメカニズムの役割を矮小化してしまうことは、今後の対応の遅れを招きかねません。
最新の科学的知見によれば、進行する気候変動による影響は、もはやある程度は避けられないということが常識となりつつあります。気候変動による影響が確実に発生していく中で、特にどのような分野のリスクが高く、早期かつ重点的な対応が必要されるのか、きちんとした評価を一方では行いつつ、そうした影響が実際に発生した場合の対応策についても検討をしなければなりません。誤解を恐れずに言えば、海面上昇に対して堤防を造るのが「適応」だとすれば、その堤防を超えて人々の土地にまで海面が侵食してしまった場合の対応を検討するのが「損失と被害」です。そして、そのような影響には、人々の住処や農業地等への被害もあれば、生態系の喪失といった損失もあります。そうした損失や被害は、必ずしも金銭的な価値がついたり、金銭的に回復が可能であったりするとも限りません。
気候変動がもたらしうる未曾有の影響に対して、今後、国際社会としてどのように対応していくのか。ワルシャワ国際メカニズムの下で、他の分野の機関とも協力しての対応が今後必要です。
3.資金支援拡大へ向けての道筋
3-1. 「資金のCOP?」
今回のCOP19は、以前から「資金のCOP」となることが目されていた会議でした。そのために、閣僚級の会議も予定されており、(交渉官レベルではない)政治的な後押しも受けて、議論を前に進めることが期待されていました。
しかし、会議が終了した今、振り返ってみると、「資金のCOP」と呼ぶほどの成果は存在せず、この分野での成果は極めて限定的なものであるといわざるを得ません。
「資金」に関連する議題は、主に以下の6つの議題項目に分かれて議論がされました。
- 長期資金に関する作業計画
- 資金に関する常設委員会の報告
- グリーン気候基金(GCF)の報告とGCFに対する指針
- COPとGCFの関係
- 地球環境ファシリティ(GEF)の報告
- 資金メカニズムに関する第5次レビュー
これらの他に、途上国の森林減少および劣化からの排出削減等(REDD+)の分野では、当該分野における資金支援の議論が行われました。さらに、京都議定書下の仕組みとしての適応基金(※CDMのクレジット販売の収益の一部が主な資金源の基金)、ADPに関わる場でも資金に関連する争点は議論されました。
これらの幅広い議論の中でも、最も交渉が難航し、最終日まで決着がつかなかったのは、1番目の「長期資金に関する作業計画」でした。以下では、この部分に焦点を当てて議論を紹介します。
3-2. 長期資金(LTF)への道筋
2009年のコペンハーゲン合意および2010年のカンクン合意で、「長期資金(LTF; long-term finance)」として、「2020年までに年間1000億ドルの資金」の流れを生み出すという目標が合意されました。以来、「長期資金」は重要な分野として、一方では、グリーン気候基金(GCF)や常設委員会(Standing Committee)といった制度・組織が設立されるとともに、ダーバン合意(2011年)で打ち立てられた「長期資金に関する作業計画」の下で、この「1000億ドル目標」をいかにして達成するのかについて議論が続けられてきました。
今回の交渉の争点は、この「1000億ドル目標」へ向けて具体的な「道筋(pathway)」を描けるかどうかでした。特に途上国グループは全体として、この「道筋」を明確にすることを今回の会議では重視していました。
中でも最も先鋭的な立場をとっていたのは、中国・インドなどのLMDCグループで、この「1000億ドル目標」は、新しい約束ではなく、条約上の義務の延長線上にあるものであるとし、「道筋」として、2017年までに700億ドル、以降毎年100億ドルごとに増やしていくということに合意するべきであると主張しました。
また、AOSISや後発開発途上国(LDC)などは、この1000億ドルの中で、適応にも十分に重点が置かれることを主張していました。
また、前回以前から長く続いている先進国・途上国間の対立点としては、民間資金と公的資金の割合についての意見の違いがあります。先進国は、年間1000億ドル(約10兆円)という数字を公的資金のみで賄うのは不可能であるとして、これを主に民間資金の流れによって達成するべきであると主張しています。これに対し、途上国は、公的資金の役割を重視しています。
結論としては、今回の会議では、「20xx年までに○○億ドル」というような道筋を示すような合意や、資金源を示唆するような合意はされませんでした。その意味では、明確な成果は得られませんでした。 しかし、いくつか、今後の作業に関する重要な決定事項もありました。たとえば、以下の事項です。
- 隔年評価に合わせた各国の気候資金増加戦略・手法の提出:COP18の決定において、資金に関する常設委員会は、資金の流れに関する最初の隔年評価(biennial assessment)を行うことに合意しています。2012年12月の合意なので、最初の隔年評価は、2014年に行われることになります。この隔年評価に合わせて、各国に対して、2014年〜2020年までの期間にいかに資金支援を増加させていくかについての情報を提出することが、先進国に要請されました。
- 常設委員会に対する「気候資金」定義の要請:上記作業に並行して、常設委員会に、「気候資金」の定義を行うことが要請されました。これは、単に言葉の定義というだけでなく、どのような資金の流れが「気候資金」として認められるのかどうかを含みうるため、実は重要な議論です。
- 議論の継続とワークショップの開催:今後の会合においても、ワークショップ等の開催を通じて議論を継続することが決まりました。
- 隔年での閣僚級の対話の開催:2014年〜2020年の間、隔年で閣僚級の対話が開催されることになりました。この対話は、主に上述の提出された戦略・手法やワークショップでの議論をベースにして行われることになっています。
総じて見ると、前回のCOP18決定および今回のCOP19決定によって、「隔年ごと」の気候資金の評価体制がつくられたと言えます。つまり、1000億ドル目標への具体的な数字の確保には至らないかったものの、そこへ至るまでのチェックポイントは整備されたといえるでしょう。
1000億ドルという数字は、途方もない数字にも見えますが、世界経済フォーラムの試算では、「2℃未満」目標達成のために必要な資金の流れは、7000億ドルという試算もあります 。現在は下火となってしまっている資金源の議論も含めて、いかに、世界的な資金の流れ全体を、低炭素・脱炭素の方向へと変えていくのかの議論の活性化が急務となっています。
3-3. GCF・適応基金などの議論
上記の長期資金の議論に加えて、注目を集めたのが2つの基金をめぐる議論でした。
1つはGCFをめぐる議論です。GCFは、事務局が韓国に設立され、いよいよ運用が開始されますが、現時点まで、まだ資金を拠出した国はあまりありません。今回の会議では、GCFの「運用化」のために、早期に資金拠出することを途上国が求める場面が多くありました。これに対して、先進国の多くは、2014年の最初の2回のGCFの理事会会合(2月および5月)において、基金が資金を受け取り、管理し、計画し、支出するための主要手続の合意をする予定となっているため、その中身を受けて、資金の拠出については検討したいという意思を示していました。今回の会期中には、GCF事務局を自国に積極的に誘致した韓国が拠出を表明しましたが、それ以外にはあまり目立った動きはなく、現時点ではまだ拠出を宣言している国も金額も限られています。
もう1つは、適応基金をめぐる議論です。クリーン開発メカニズム(CDM)の市場が低迷し、価格が低迷していることを受けて、CDMのクレジットからの収益の一部を資金源としている適応基金は、資金が不足しはじめています。これに伴い、適応基金理事会は、1億ドルの資金調達を目標として、各国からの独自の資金拠出を呼びかけていました。結果として、主に欧州の一部の国々からの拠出により、この1億ドル目標はどうにか達成できそうだという見通しが立ちましたが、主要な資金源をCDMに依存したこの基金の難しさが現れた会議でした。
3-4. 日本の2013~2015年資金の誓約
今回、交渉そのものとは別に期待がされていたのは、2013〜2015年の期間に関する資金の拠出でした。2009年のコペンハーゲン合意の際に、先進国各国が制約した2010〜2012年の3年間で300億ドルという「短期資金(fast start finance)」が終了し、今度は、2013年以降の資金支援について、何らかの発表が出ることが期待されていました。
日本は、今回の会期中、2013年〜2015年の3年間160億ドル(うち公的資金は130億ドル)の資金拠出を宣言しました。前回の短期資金の時に引き続き、この資金規模そのものは大変に大きいものです。しかし、今回の会議においては、日本の削減目標に対する批判があまりに大きかったことや、この資金の中身がどれだけ「新規かつ追加的」であるかについての不明確さの懸念から、高い評価を得たとは言い難い状況です。 このほか、上述の通り、適応基金への拠出を宣言したりした一部欧州諸国もありましたが、どの国も決して経済状態が良いとは言えない状態であり、具体的な資金拠出の金額という意味ではあまり目立った動きはありませんでした。
4.COP20に向けて

飢えに苦しむ台風被害者とともに、会議が進展する前断食すると
発表したフィリピン代表。共感して断食をする若者たち
今回の会議直前に、フィリピンを巨大台風ハイヤンが襲い、甚大な被害を引き起こしました。気候変動がこのまま進行した際の異常気象がもたらす影響を予見するような惨状を目の当たりにして、会議参加者の間でしきりに気候変動対策の「緊急性」を訴える声が相次ぎました。フィリピンの交渉代表は、会議の初日に、この惨状を国際社会に訴え、自らの弟が被災しながらも連日遺体を集めているという話を涙ながらに語り、会場中が黙とうをささげるという場面もありました。台風の被害者たちが飢えに苦しんでいることを受けて、フィリピン代表は会議がきちんとした成果を生むまで断食をすると宣言し、それに共感した多くの人が会議中に同時に断食をするという事態にまで発展しました。
しかし、会議はやはり難航しました。 各国がそれぞれ緊急性を言及しつつも、従来通りのポジションを訴えて、一向に違いを乗り越えて行こうという意志が見られない状況に危機感を募らせたWWF、オックスファム、グリーンピース、FoE等を含む多くのNGOが、会議終盤、抗議と懸念の意志を表明するために、「ウォークアウト」(自発的退場)という行動を実施しました。あえて、市民社会が会場を同時一斉に出て行くという行動で、危機感の深さを示したのです。
WWFとしては、多国間交渉の場としてこの国連気候変動会議のプロセスを重視しています。だからこそ、こうした通常でない意思表示を通じて、少しでも多くの人に、そして各国の代表に危機感を伝えることができればとの願いを込めて行いました。
来年2014年のCOPは、ペルーの首都リマで開催される予定となっています。
日本としても、今回の会議で受けた国際的な批判の嵐を踏まえ、国内で早急に気候変動目標を見直し、そして新しい2020年以降の目標についての検討も開始することで、引き続き、気候変動対策に積極的に貢献する意志のあることを示すことが重要です。
関連情報
問い合わせ先
WWFジャパン 気候変動・エネルギーグループ
Tel: 03-3769-3509 / Fax: 03-3769-1717
Email: climatechange@wwf.or.jp